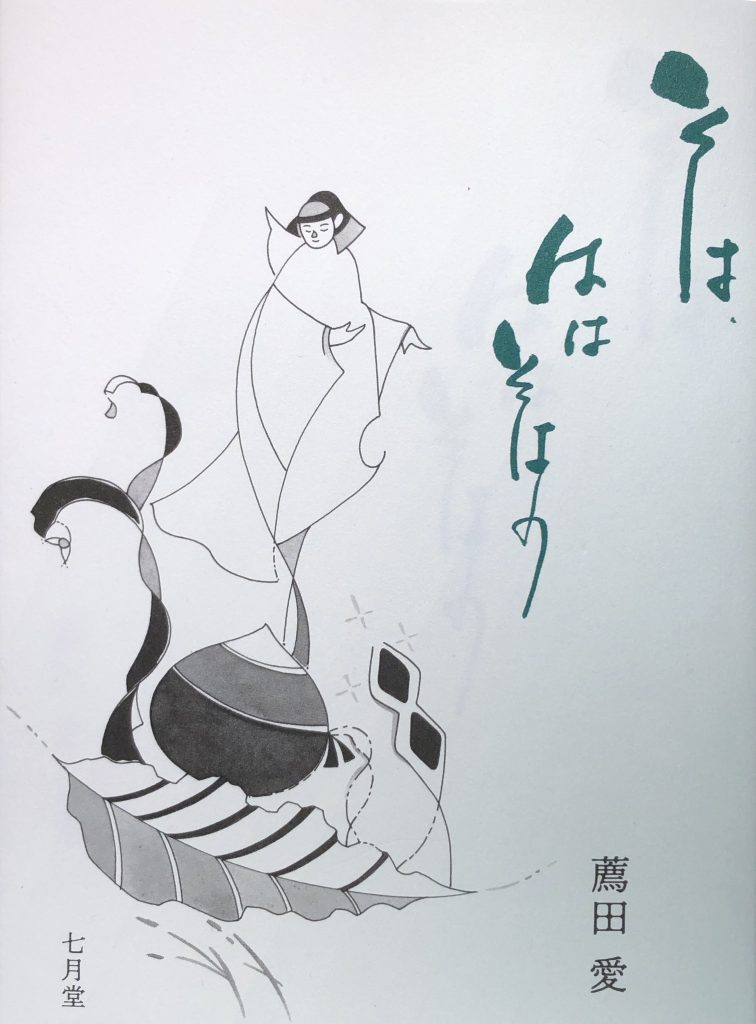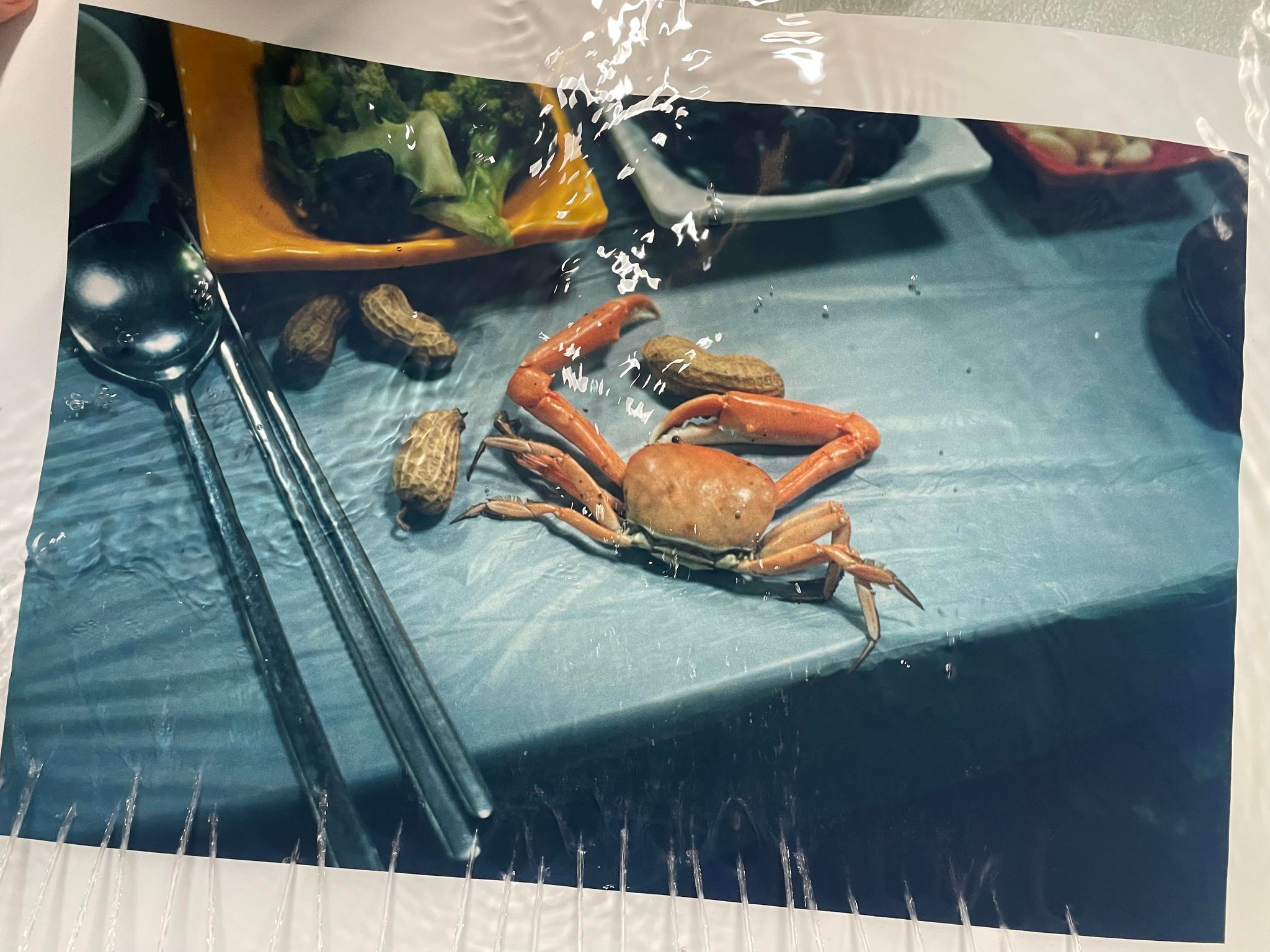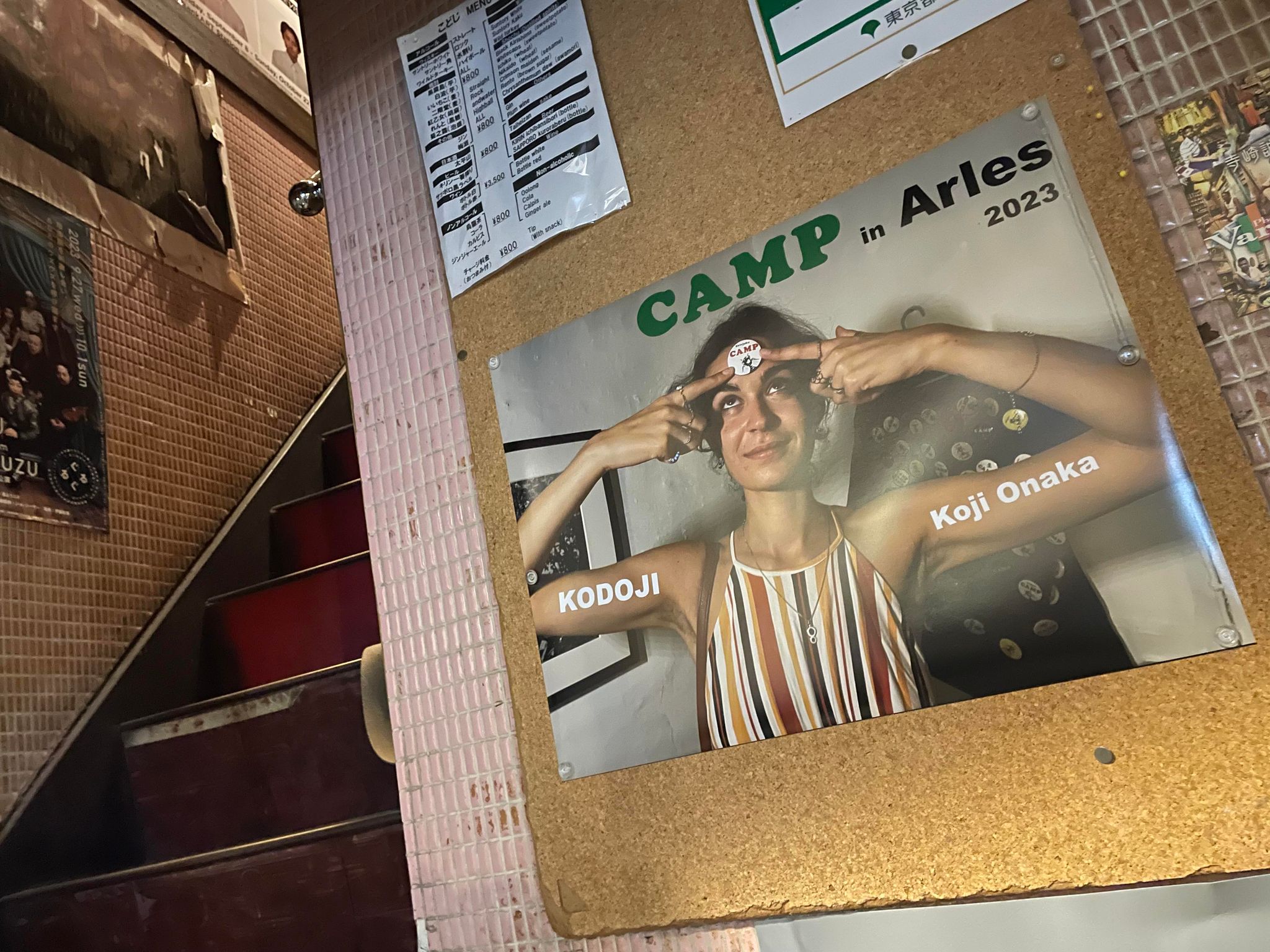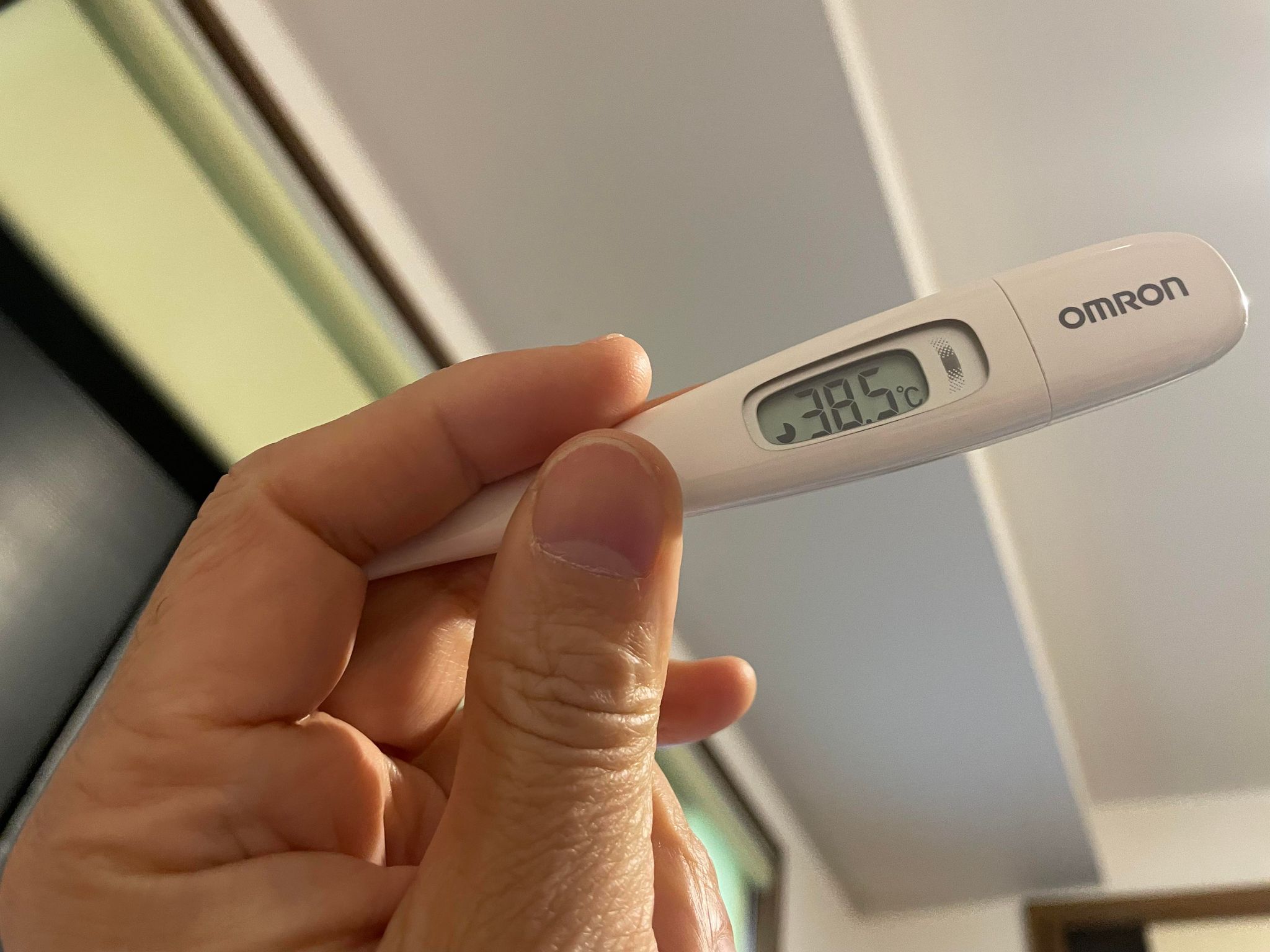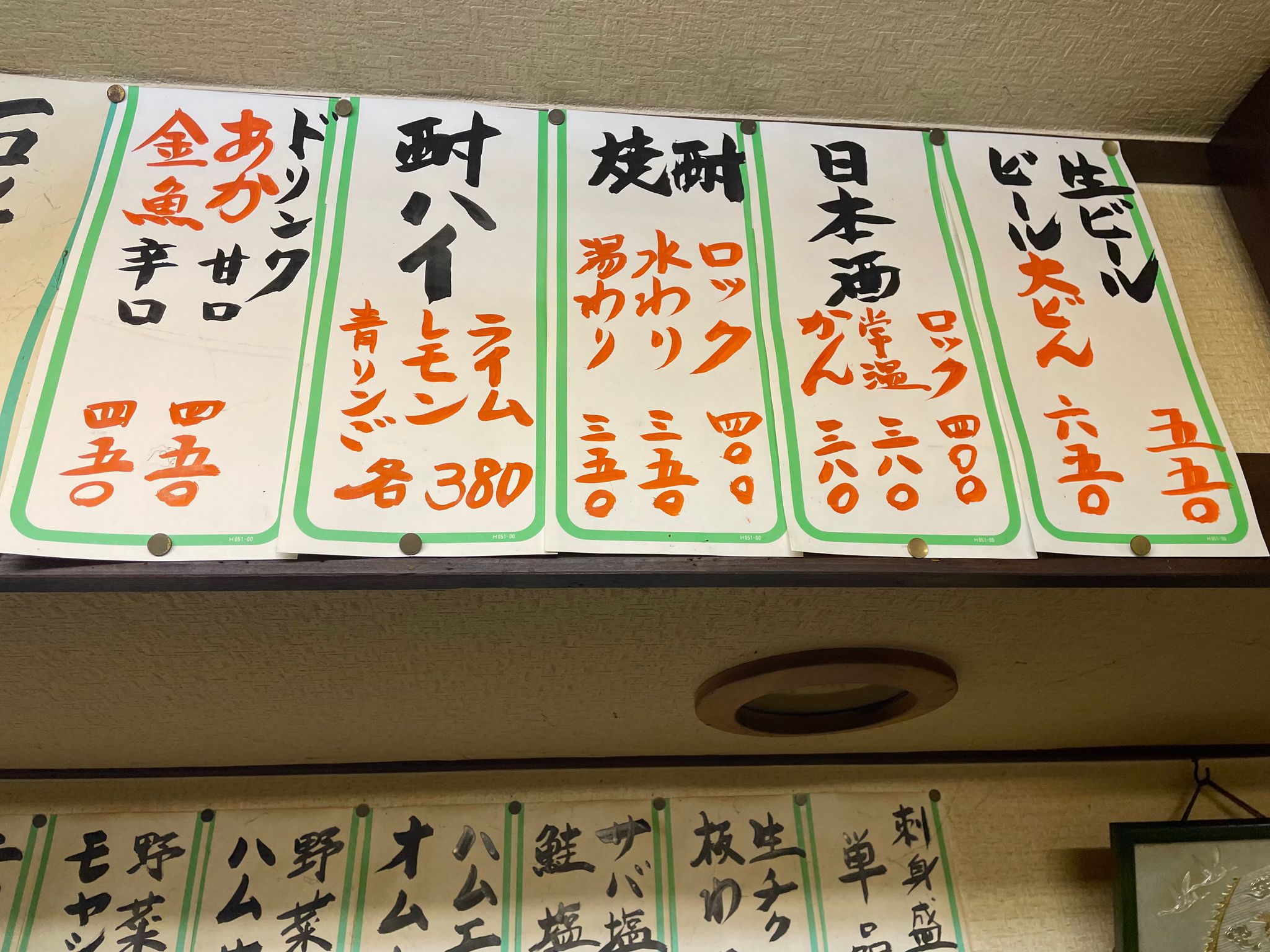長尾高弘
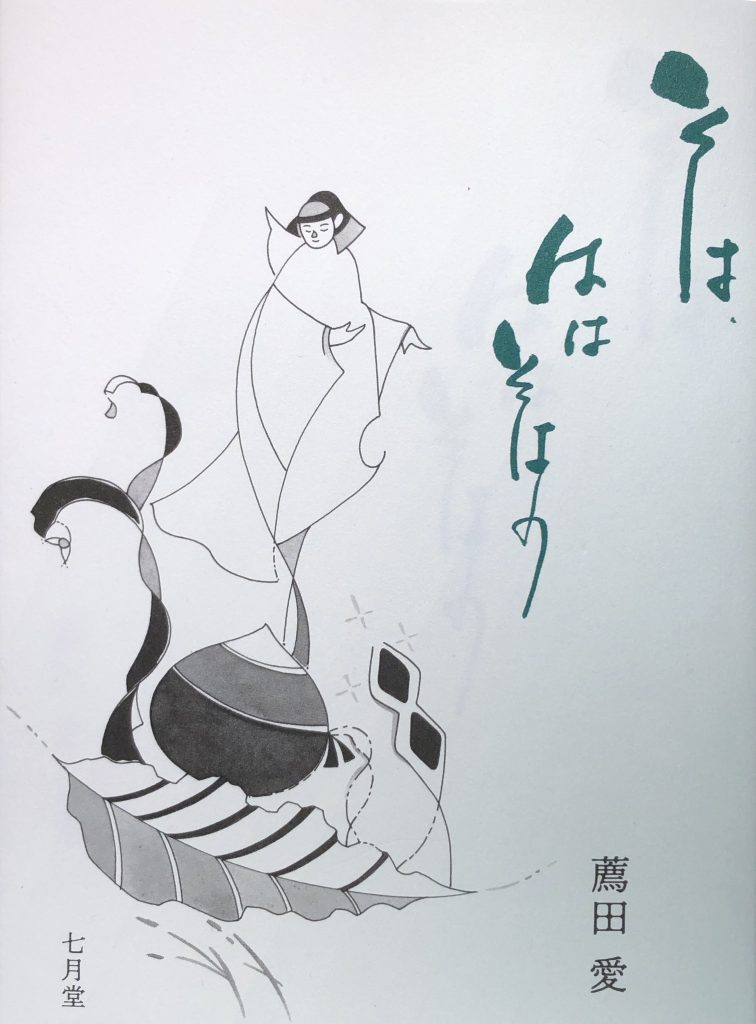
【一】
英雄伝のようなものだけでなく、時間の経過とともに人間関係が変化していく様を描いた詩も叙事詩と言ってよければ、『そは、ははそはの』は叙事詩集だと言えるだろう。ト書きのような状況説明、内心の声、実際に口にした言葉がそれぞれそういうものですよと明示されないものの(たとえば、発言だからといってほとんどは「」で囲んであったりはしないし、発言者が誰かも書かれておらず、発言者名が書かれていないから一目でここはト書きだとわかるということもない)、注意して読めば明確に区別できる(誰の発言かも含めて)ように自然にミックスされているのはかなりの力技だが、読みながらその区別が気になってくると、これは劇詩に似たものではないかと思えてくる。実際、薦田さんは劇団「燐光群」の戯曲の執筆にも参加されていたのだ。
もし、この見立てのように一つひとつの詩をある程度独立した存在として立たせつつも、全体でひとつのまとまったドラマを打ち出そうとしているのなら、詩をどのように並べて詩集を構成するかは作者にとって重要な問題になるだろう。ここで巻末の初出一覧を見ると、ページ数でも作品数でも全体の四分の三近くを占める《壱》は二〇一五年一月から翌年一月までコンスタントに十三作書かれてさとう三千魚さんのサイト「浜風文庫」(https://beachwind-lib.net/?cat=25)に掲載されたあと、さらにその翌年の一月までの間に三作書かれていることがわかる。《弐》、《參》を含めてそれ以降の作品が散発的に書かれているところを見ると、少なくとも《壱》の最初の十三作についてはある程度の構想をもとに書かれているのではないかと思うのが自然なところだろう(実際には詩集に収録されているのは十二作だけで、四作目の「卯月、うらはらの」は詩集から外したことを初出記録に注記するのを忘れられたようだ。これからは詩集に合わせて数えることにする)。作品はかならずしも時系列順にはなっていない。最初の「ふたみ、夕暮れの」は三作目の「新宮、そして伊勢の」と同じ旅行の後半だろう。
しかし、「ふたみ、夕暮れの」には、どうしても最初に入らなければならない理由があると思う。「後記」で作者自身が旅を詩に書いたと言わんばかりのことを書いているが、〈はじめてみると、旅を入り口に、家族の来し方や日常がたちあがる〉とも書いているのを見れば、〈旅を入り口に、家族の来し方や日常〉を書いているのである。実際、詩集を何度も読むとそういう感想を持つ。たしかに、〈旅〉は言葉と現実の世界をつなぐという重要な働きを担っているが、詩集の彩りであって(彩りも重要な役割だが)本題ではないように思われる。
そのような見方からすると、「ふたみ、夕暮れの」の二連目で二見ヶ浦の夫婦岩から〈めおと〉というキーワードを引き出しているのは意図的なものだと感じられる。冒頭の〈女ふたりで夫婦岩なんてね〉というところがこの詩集で最初のセリフで、これはあとを読むと〈私〉の言葉だということがわかる。そのあとの〈、と〉によって〈私〉のセリフは〈なんてね〉で終わっていることが明示されるとともに、次行の〈鼻をかむ〉で〈私〉のちょっと引いた構えが暗示される。
その次の行の〈だって〉から〈父つまり夫を送って三十年の母との旅だ〉までの四行は鼻をかむ〈私〉の内心の声だと考えられる。そのあとの〈結婚中退からの十年/めおとって響きに/ちょっとひるんだのは私〉という三行は、〈私〉の状態の説明であって内心の声を写し取ったものではない。そして、この三行によってふたりともに結婚生活は終わってしまっているが、〈母〉は死別という自らの意思と無関係な理由で結婚生活を終えなければならなかったのに対し、〈私〉は〈中退〉しているという違いが短い言葉でさりげなく示されている。初読のときはともかく、二度、三度と読むと、あとの部分で〈母〉が熱烈な恋愛結婚だったことが描かれているのに対し、〈私〉の(ここで話題になっている)結婚生活が簡単に終わってしまったように書かれているので、母と娘で(この時点までの)結婚生活のあり方に大きな違いがあることがくっきりと印象に残る。
〈仄白くにごった光が絵筆のいっぽんとして/雲を走らせる/夕闇を押し留めて伊勢湾の空は/つがいの岩をみおろしている〉という鮮やかな印象を残す四行の連以降の終盤はこの不在の〈父〉が支配している。ここで〈仄白くにごった光〉という言葉が出てくるので、次の連の〈深夜、あの岩、あの海、あの空の写真をみている/(仄白くにごった光の)〉で言及されている写真は、〈母〉とふたりで夫婦岩を見たそのときの写真だろう。
その次の〈そう/旅の翌日/これをみて/母の手に一枚のモノクロ写真/え/父だ、父が写っている/その後ろ/あ/めおといわ/夫婦岩だ/おれも行ったんだぞと言ってるみたい、と母〉と始まる最終連はうまいところで、最初の〈そう〉は前の連の〈深夜、〉という一行とともに、〈母〉から写真を見せられたのが、前の連よりも先だということを示している。このように時系列順に並んでいない箇所が多数あるところがこの詩集の作品の特徴で、これは最初に言及した演劇などではたぶんあまり頻繁に見られないところだ(映画、テレビドラマなどの映像作品にはよくあるが)。
この部分では短い各行が目まぐるしく役割を変える。〈そう/旅の翌日〉は状況説明、〈これをみて〉は〈母〉の発言、〈母の手に一枚のモノクロ写真〉は状況説明(モノクロというところがカラー写真普及前だということを示している)、〈え〉は〈私〉の発言、〈父だ、父が写っている〉は〈私〉が実際に口にしたのではなく内心の声(本当に口にしたのなら、〈あ、パパが写っている〉というような表現になっていたはずで、〈父〉とは言わないだろう。なお、〈パパ〉という言葉が出てくるのはずっとあとである)、〈その後ろ〉は〈母〉の発言、〈あ/めおといわ〉は〈私〉の発言、〈夫婦岩だ〉は〈私〉の内心の声(この二行目の〈夫婦岩だ〉は内心の声か実際に発声された言葉かは微妙だが、どうしてもどちらかに確定させなければならない理由はないと思う。なお、このように読みが同じだが表記が異なる二行が続く形はこのあとでも散見される)、〈おれも行ったんだぞと言ってるみたい、と母〉の行は〈母〉の発言であることが明示されていて、そこまでのスピード感のある行渡りに休止符を入れている。
最終連はあと五行だ。〈旅行前にしていた整理の/続きをとアルバムを開いたら〉は〈母〉の発言の続きである。ここから、〈母〉も〈父〉が写った写真に気づいたのは旅行から帰ってきてからだということがわかる。そして〈開いたら〉で行が終わっているので(たまたまページもここで終わっている)〈母〉の発言がまだ続くのかと思うと、最後の三行、〈いったいいつの社員旅行だったのか/まっすぐな目を向け/モノクロの父は〉は〈私〉の内心の声である(この詩集の作品はここでの〈母〉の発言のように省略がかなりある)。この連の〈社員旅行〉と〈モノクロ〉という言葉は経済成長を目指していた一九六〇年代を想起させるとともに、最初の十二作の影の主役が最終行の〈父〉であることも示している。
それにしても、何度かこの詩を読んで二枚の写真の関係に確信が持てるようになると、〈仄白くにごった光〉が天上の〈父〉の視線のように思えてくる。そして、〈波に洗われ続ける岩の冷たさ/注連を張るだけの隔たり/おもいもしなかった感覚がたちのぼる〉の三行に、働きづめだった(ということが十一作目で明かされる)〈父〉の姿と〈仲のいい夫婦〉(十二作目における表現)だった両親を見ていた〈子〉の視線を感じる。では、〈父〉が〈みおろしている〉〈つがいの岩〉の〈つがい〉は誰と誰なのだろうか。気を抜いているとすらすらと読めてしまうが、この冒頭の詩は非常に密度が濃い。最初から母と子の微妙な関係、母と今はいない父の濃密な関係を簡潔な言葉で説得力豊かに示している。
二作目以降、連載最後の四連作の手前まではこの一作目と比べればゆったりとしている。行数が増えているし、会話の部分が増えていく。二作目の「河津、川べりの」はおそらく〈母〉との旅行が始まったきっかけで、〈私〉は桜が好きな〈母〉が〈あとどんなにがんばっても二十回くらいしか見られないものね〉と言うのを聞いて、まだ見ていない河津の桜を見に行くことを〈母〉に提案する(この部分には思い切って旅に誘うという感じが出ており、習慣化した旅で次の行き先を提案するのとは勢いが違うので、そもそもの始まりだと思われる)。〈母〉は〈私〉からもらった桜のペンダントをつけてきて〈私〉を喜ばせる。一般に親子でも子が大人になったら互いにそれなりに気を遣わなければうまくいかない(そして相手が本当は何を考えているのかよくわからない)ものだが、そういう微妙な距離感をうまく表現していると思う。しかし、ここではまだ互いに相手を気遣っている部分が前面に出ていて、本当に緊張が走るようなことはない。
ところが、三作目からは三連続でそれぞれが失敗を犯し、たとえば三作目(先ほども触れたように、一作目の二見行きの前後に起きたことを描いていると思われる)では〈母〉の気が急いている状態で〈きゅうっと狭くなる/通路 あなたへの〉というようなことが起きる(でも終わりの方で〈やっぱりね、親子だね〉と言えるときも来る)。このようにして、ほんわりと温かくまとめた二作目よりも少しずつ微妙なところに触れて行くようになる。
五作目の「湯葉、固ゆでの」では、初めてどこかに行くのではなく都内の自宅の近所での移動の話になるが、〈気がついたら亡くなった父のポジションにおさまりかえって〉という重要な一行がある。ここは一作目からしばらく出番のなかった〈父〉が久しぶりに顔を出す部分だが、〈父〉が本格的に登場するのはもっとあとだ。
六作目の「光、長崎の」と八作目の「窓、犬山の」はこの詩集のなかでもっとも純粋に旅行を描いている。そして、信仰はないが教会に惹かれ、家族以外の人々に思いを致すという共通点がある。家族の外への視線が入ることによって詩集のスケールが大きくなっている。間にはさまれた七作目の「そうめん、極太の」は「湯葉、固ゆでの」以来の東京の話だが、〈父〉と〈母〉の故郷である四国が話題になる。ただし、四国からやってくるのは〈母〉の方の親戚である。
そして、九作目の「海、尾道の」からは〈父〉と〈母〉の故郷である四国への旅を四作に渡って連続的に取り上げ、この詩集の本題であると思われる〈家族の来し方や日常〉がその旅の間に入り込んでくる(それまでの旅は作品が書かれた年よりも前の年に行かれたものだと思うが、ここからは二〇一五年の旅行なのではないかと思う)。しかし、〈地図と映画でしか知らない町へ行く/初めての/私にとって 母にとっても/尾道〉という〈海、尾道の〉の冒頭は、新たな旅の話が続くのだろうと読者を油断させる効果がある。一行目に〈知らない〉、二行目に〈初めての〉とあって、三行目に〈母にとっても〉というのだから、過去の話に踏み込んでいくとは予想できない。四行目の〈尾道〉で初めてあれ四国に近いぞと思うが、でも〈母〉さえ行ったことがないんだよねと思ってしまうのである。
何度か読むと、このフレーズの順序はうまいなと思う。いかにも現代詩という小難しさはないが、散文では決してこのような書き方はしない。散文で書けば、たとえば〈私にとっても母にとっても地図と映画でしか知らない尾道という町に初めて行く〉というような感じだろう。これでは詩にならない。〈私にとって 母にとっても〉というのがまた絶妙で、私が行ったことがないのは当然として母でさえ行ったことがないのだと言っているように感じる。〈海にのぞむ町〉という尾道の形容詞としてもっとも月並みな言葉を使った上で(これも読者を油断させる)、六行目で〈純子さん〉という読者にとって未知の人の名前が出てくる。
その〈純子さん〉については、それまでの旅のプロセスについて十二行に渡って少々長めに語っている第二連を挟んで、第三連の三行目になって初めて〈母〉の〈洋裁学校の同級生〉だということが明かされる。〈母〉が洋裁学校に通い、結婚後、そして〈父〉の死後も洋裁を続けていたことは連載十二作のあとに書かれた「いと、はじまりの」で明かされるが、〈母〉の洋裁はここが初出だ。長い第三連の最後の六行、〈話は同級生たちのこと/純子さんの娘さんたちお孫さんたちのこと/ほんとうのところは/孫の話ができなくて寂しいのだろうと/母の内心を想像するのはこんな時/聞いてみたことはないけれど〉は記憶に残る。
そして長い第六連の最後の十一行がこの詩の肝である。そのなかでも〈大学生だったそのひとのひとこと/ダンスなんかする女の子はきらいだと/それでやめてしまうのだ母はダンスを/出会ったばかりのひとが/そんなふうに言ったからと〉という部分がとりわけ強烈な印象を残す。〈母〉の〈父〉に対する思いは並大抵のものではないということを強く感じさせる。最初に詩集を読み通したときでも、そういう箇所があったことが(どの詩のなかだったかは忘れてしまっても)記憶に残る。
次の連にも、〈ママの清楚なところがいいと/言っていたひとと母とは銀婚式を迎えられなかった/三十三回忌も終えたのよと母〉という巧みな行が含まれている。前後がうまく語られているので、引用の二行目と三行目の間にはちょっと隙間があるように感じられるが、結婚生活の方がその後の生活よりも短いことがここでさり気なく示されている。
そして最後に〈明日/私たちは海を渡るバスに乗る/父の郷里へ向かうのだ〉という三行があって、次の作品にそのままつながっていく。その「穴子、瀬戸内の」では、「湯葉、固ゆでの」で出てきた〈母は生ものと肉に加えて鰻も好まない/ただし穴子は好む〉という二行が効いてくる。作品のなかでお酒がまわってきたあたりで、〈うなぎなんて食べられないと/もっぱら穴子派だった父〉という二行が出てくるのだ。さらに最初の連を締めくくる〈せっかくだから穴子食べよう/東京と違って小ぶりなのをね/蒸すのじゃなく焼いたのをさ〉という三行と〈うなぎなんて〉の連を締めくくる〈父は/東京の穴子も食べていた/蒸して甘がらいたれを塗ったのを〉が響き合う。〈父〉(〈母〉にも共通してあると思うが)の東京に対するアンビバレントな思いが穴子で表される。もう〈家族の来し方や日常〉が全開になっている。この作品では〈パパ〉という単語が初めて登場する。家族間で使う言葉は当然〈父〉ではないが、この家では〈お父さん〉でもなく〈パパ〉だったらしいと想像させられる。家族間で使われる言葉が出てくることにより、〈パパ〉がいた頃の生活が臨場感のある形で読者にも迫ってくる。
「穴子、瀬戸内の」は〈バスは/伯方島から大島へ/さしかかろうとしている〉という三行で終わり、次の作品も引き続きこの旅のことが描かれると読者は予想するわけだが、その次の「しまなみ、そして川口の」は〈渡る/渡るということ/向こうがわへおもむくということを/かんがえていた〉という四行から成る抽象的、思念的な一連で始まる。それでも、前作は尾道から瀬戸内海の島々を経由して今治に向かおうとしているのだからと、そちらのシーンを予想していると、次の連で出てくるのは〈荒川大橋〉や〈川口〉という関東の地名である。しばらく読むうちに〈三十年以上〉前に〈父〉と〈母〉と〈私〉が三人で暮らしていた町が話題になっているのだということがわかる。そこで出てくるのは〈工場だったところはたいてい/配送センターみたいなものになっている〉とか、〈あの社宅の一画はまるっきり跡形なくて〉といったものであり、きわめつけは〈今はもうない会社に勤めていた父〉という言葉で、読者も喪失感を共有することになる。
尾道からスタートした旅のことは第三連でようやく〈ふた月前〉のこととして言及される。ここでもバスで橋を〈渡〉っている。四連目の冒頭、一行目から四行目も鮮やかな描写だが、ポイントは五行目から八行目だろう。〈領地をわかつ樽流し〉というのは備前(現在の岡山県)と讃岐(香川県)の境界が曖昧だったので、樽を流して樽がたどった道筋を境界線にしようと備前側の庄屋が提案したら、予想外に備前側を流れてしまって、ほとんどの島を讃岐に取られてしまったという伝説に由来しているらしい。人間が漁業権でもめたのである。だから、〈真鯛も章魚も穴子もでべらがれいも/波をきりわける境界線なんて知らない〉という二行が続く。〈境界線〉は〈渡る〉と〈向こうがわ〉につながる言葉だ。そして〈向こうがわ〉は異界であり、危険な場所である。
しかし、〈二十三歳の父〉と〈二十二歳の母〉は〈向こうがわ〉、すなわち〈東京〉に渡っていった。それは異界への恐怖ではなく、夢と期待があったからだろう。本四連絡橋などなかったのだから、橋を渡るよりも大変な〈船〉で渡って。そこまで思い切って行ったのに、目的の〈東京〉には落ち着けず、〈東京のへりを滑り落ちたところ〉で暮らすことになった。そして〈父〉は〈二十年あまりを働きづめに働〉いて〈たおれ〉、〈子〉は〈カロウシという言葉がなかった頃/あれを労災と言わないなら何を労災と呼ぶのかと/心をとがらせ〉た。〈おれは悔いはないが/お前たちがふびんだと言い置くくらいなら/他に途はなかったのか〉というところでは〈子〉、すなわち〈私〉は珍しく〈父〉に厳しい批判を投げつけている。ここは《壱》のクライマックスのひとつだ。
そして、連載の最終回となった「ふとん、あの家の」に続く。一方で尾道からの旅の話は続いているが、〈父〉が亡くなったあとに〈私〉が〈父〉の故郷川之江に行ったときの母との会話、〈父〉の闘病記を書いた母のエピソード(拙文の冒頭でも触れた〈恋愛結婚だった仲のいい夫婦だった〉という行で始まり〈あとがきに記した生まれ変わってもと/うまれかわってもわたしはと〉という二行で終わるこの連は鮮烈な印象を残す)、〈私〉が子どもだった頃のエピソードが入り、それらを〈ねむり〉という糸でつないでいるのは見事な技で、前作の怒りを鎮めて幸せな家族の記憶で終わる。たぶん、これが当初の構想における締めくくりだったのだろう。
しかし、作者はその締めくくりに不満を感じたようだ。ここで話が終わってしまったら、〈母〉は受け身の人、過去をひたすら懐かしむ人で終わってしまうが、そうではないということを打ち出しているという印象を残す三作が続く。
連作の連載が終わったあと、五ヶ月近くのちに発表された「いと、はじまりの」は、〈母〉が〈父〉と出会う前から得意にしていて長く生業とした洋裁のことを描いている。〈十年二十年着ても傷まない出来栄えも/あたりまえという矜持〉を持てるほどの腕前で〈自分のと娘のと/二着のウェディングドレスを縫った〉という。最後に引用されている薦田英子さんの文章(「ふとん、あの家の」で言及された〈父〉の闘病記だと思われるもの)、特に〈気取って、ミシンの上に立ったわたしに、あなたは照れもせず無邪気に歓声をあげました。/「ワァー、ぼくの花嫁さん!」/ いいながら、わたしを軽々と持ち上げて椅子からおろしました〉という最後の部分は印象的で、詩集を読み終わったあとも記憶に残る。
だが、それでも足りなかったのか、《壱》の最後に置かれた「ふたつの世界を股にかけて母は」では、白内障の手術後、〈世界が変わったみたい!〉という〈母〉のメールが引用されている。そのなかの〈手術した方をつむると、今まで当たり前だった日常がセピア色に見えるのよ〉という言葉を受けて〈ふたつの時間ふたつの世界に股をかけて踏みしめる足もと〉という詩行が〈母〉の新たな未来を寿ぐように続く。
でも、まだ作者には不満が残っていたようだ。このふたつの作品の間にはさまれた「はり、まぼろしの」は、「いと、はじまりの」補遺ということから「ふたつの世界を股にかけて母は」の前に置かれているが、《壱》のなかで最後に発表され、おそらく最後に書かれたものだと思われる。「いと、はじまりの」で〈二本の糸/二本の針が行き交って縫いあげてゆく〉と書いたことに対して、〈母〉にそれは間違いで〈針は一本〉だと指摘されたために〈それぞれ針に糸を通したふたりが/出逢って一緒に布を縫ってゆくのではなく/ひとりが糸をとおした一本の針で/もう一本の糸をたぐり寄せ/縫いあげてゆくのね〉ということになり、〈もういっぽんの糸を迎えに〉いくのは〈母の手〉だから、〈母と出逢ってふたり物語を仕立てあげてゆく父は/何を手にして、どこに立てばいいのか〉ということになってしまう。〈ひもときはじめた物語の続きをみうしない私は/今日踏み出す足を決めかねている〉という二行で終わっているのは、そのためだと言っているかのようだが、〈物語の続きをみうしな〉ったことにはもっと大きな理由があるように予感される。
【二】
皮肉にも、この一冊が本としてまとめられたのは、《壱》を書き始めたときには作者自身が想像もしていなかったことが起きたからなのだろう。《弐》、《參》にはそれが書かれている。ただし、〈重ねかさねて二年〉(「訪ない、かれの」)とか〈つきひは一年を/さかのぼる〉、〈三人で暮らそうと/春先の旅も一緒だった〉(「ばっこばっこ、ははは」)といった記述から計算すると、「訪ない、かれの」の冒頭の〈その年正月三日〉、つまり〈母〉と〈彼〉を引き合わせた食事会は遅くとも二〇一六年であり、その後の記述から考えれば二〇一五年以前でもないだろう(二〇一五年だったら〈重ねかさねて三年〉でなければおかしい)。二〇一六年の〈正月三日〉は毎月連載された最初の十三作の最後を飾る「ふとん、あの家の」の発表日でもある。とすると、そのときにはまだ「いと、はじまりの」以下の三作は書かれていない。そして、「はり、まぼろしの」が二〇一六年発表の「いと、はじまりの」を〈母〉が読んだ前提で書かれていて、三作すべてに〈傘寿〉または〈八十歳〉という言葉が含まれているので、この三作の現在時は二〇一六年(「はり、まぼろしの」は二〇一七年初めもあり得る)であることは間違いない(さらに、「ばっこばっこ、ははは」には、二〇一九年の時点で〈齢八十三〉、その前年五月に〈八十二歳〉だと書かれている)。
しかし、「訪ない、かれの」の冒頭に描かれている二〇一六年は、《壱》の最後の三作にある〈母〉を持ち上げるという空気とはまったく逆の空気が流れている。実際、正月三日のできごとについても〈野末の草むらをそよと微かに揺らす風のほんの兆し〉という不穏な一行で締めくくられている。もっとも、「訪ない、かれの」は書き下ろしであり、早くても二〇一八年の事件のあと、おそらくは《參》の「ものぐるひ」よりもあとに書かれていると考えられるので(二〇一八年に「浜風文庫」に掲載された薦田さんの作品は、引っ越しのことを描いた俳句の連作だけである。なお、巻末の「略歴」には〈二〇一八年、関西に居を移す〉とある)、二〇一六年時点とは違う意識で書かれているのは当然だろう。
それにしても、〈会わせたい人がいると母に話し〉た割に〈にこやかな母と物腰やわらかなユウキ〉の〈間でひとり冷や汗かく私〉の様子は奇妙な感じがする。普通、結婚を意識しているという相手を親に引き合わせるときには、双方が相手を気に入ってくれるかどうかという不安はあっても、結婚に向かって一歩前進するという高揚感の方が強いのではないだろうか。しかし、〈いえまじめなのはありがたいけれど/真っこう正面きりましたね〉という〈私〉にはちょっと迷惑そうな風情さえ感じられる。引き合わせの動機が〈離婚歴ある娘すなわち私の帰宅が深夜におよぶと/心配かつ不審にかられる彼女から/メールがひんびん届いたりするから〉だというのだから、どちらかというと〈母〉対策が主であり、ひょっとすると〈私〉にはまだ〈ユウキ〉と結婚するという明確な意思はなかったのかもしれないとさえ思ってしまう。
しかし、〈気がついたら亡くなった父のポジションにおさまりかえっ〉た(「湯葉、固ゆでの」)とか〈父亡きあと三十数年を何とか乗り切った/長女じゃなく長男みたいと言われる子〉(「ふたつの世界を股にかけて母は」)というように描かれてきた〈私〉の姿、その〈父〉と〈恋愛結婚だった仲のいい夫婦だった〉のに早く死に別れ、〈生まれ変わってもと/うまれかわってもわたしは〉と〈あとがきに記した〉(いずれも「ふとん、あの家の」)という〈母〉の姿を見てきた読者は、このような〈私〉の様子からも、〈ユウキ〉と〈母〉が〈私〉をめぐって競い合うとか対立するといった今後を予想せざるを得ない。〈母〉にとって〈私〉が〈父〉の完全な代理になるわけはないだろうが、〈私〉が目の前からいなくなれば〈母〉は深い喪失感を味わうことになるだろう。もっとも、〈ユウキ〉と〈母〉にそういう競合、対立の意識があるなどとは決して書かれていない。だからそんな対立があるだろうというのは読者の勝手な想像であり、そういう読者はどちらにもそんな意識はないのかもしれないとも思わざるを得ない。
その後の〈ユウキ〉と〈母〉の動きは対照的に描かれる。〈ユウキ〉は〈ほどなく「遊びに来」〉て、〈女所帯〉ではそれまでできなかったことをちゃっちゃと片付ける。〈結婚を前提におつきあいさせていただいてい〉る娘と義母になるかもしれない人とではもちろん接し方が違うが、もっとも大切な相手の身内として〈母〉のことも大切にする(それは、むしろ次の「まじなふ、ははは」で詳細に描かれるのだが)。〈私〉との距離はどんどん詰めてくるが、決して〈母〉に敵意を示すようなことはなく、二〇一八年の事件が起きるまでは〈三人で暮ら〉すという前提を崩さない。そのように描かれている。
一方の〈母〉は〈初対面のあと母から/興奮ぎみのメールがつづいた/デモドリの娘の新しい交際がそんなにも嬉しかったのか/あとに/むっつり黙り込む日があり/かとおもえば/ふたりでとる朝食のとちゅう言葉尻がとがって諍いになり/あんたは性格が変わってこわいとなじるなり席をたち/やむなく私は会社へ出かけ/夜ふけて帰ると部屋にこもっていて/食卓が席をたった朝のままの日もあり〉というように不安定化し、自壊していくように描かれる。たぶん、「ふたつの世界を股にかけて母は」や「はり、まぼろしの」と同じ時期にここに描かれたことも起きていたのだろう。
そして、「訪ない、かれの」は〈迷い〉で終わる。その〈迷い〉は〈私と/母とユウキと三人/いっしょに暮らすならどこ〉かについてのことのように書かれているが、それだけだろうか。詩にも〈もろもろ迷うちからが/尽きようとしていた〉という二行があって〈もろもろ〉という言葉が何気なく入り込んでいる。〈ユウキ〉と〈母〉の競合を予想する読者には、〈きみはそれじゃあいつまでたっても決めない/決められないよとユウキ〉が決断(引っ越し先のだが)を迫っていることが今後の波乱を予告しているように感じられる。
次の「まじなふ、ははは」も書き下ろしだが、〈あの子/あなたに気を遣いすぎて身体をこわすわよ/口にしたのだった/まるで/幼い姫の誕生を祝う席に遅れて現われた/年老いた魔女の/呪いの言葉のように〉という冒頭からまさに波乱含みだ。〈まじなふ〉は「呪う」という意味で使われているが、「(相手のために)祈る」という意味もあるので、最初はどちらなのかがわからない。〈あの子〉と〈あなた〉が〈私〉と〈かれ〉のどちらを指しているのかも、五行目まで進まないとはっきりしない。この最初の不安定感と〈年老いた魔女の/呪いの言葉〉という言葉の強さが、〈あの子/あなたに気を遣いすぎて身体をこわすわよ〉というぼんやり読んでいれば見過ごしてしまいそうな言葉の持つ意味を読者の脳に刻みつけてくる。
二連目からはその言葉に至るまでの経緯が九ページ近くに渡って語られる。しかも、この二連目は三連目からの伊豆のエピソードが五ページほど続いたあとの発言であり、その五ページ先で〈話のタネだ/ほんとうに行くとは思わなかった〉という言葉を添えた形で繰り返される。つまり、二重に時系列のずれがあるわけだ。
驚いたことに一泊の伊豆旅行のあと、大手町から九段下まで東西線に乗って千鳥ヶ淵に花見に行ったのである。この千鳥ヶ淵行きがすごい〈ひとごみ〉でいかに疲れることだったかが四ページほど語られたところで、〈あなたに気を遣いすぎて〉の種明かしがある。〈だいじょうぶ/声かけたのだ/彼に/人ごみに出かけることなどほとんどないのに/ただごとではない/おしくらまんじゅうに/つかれてはいないかと/つかれているこころが/言わせた/だいじょうぶだよと/言ったのだろうか/彼は/そのあとのことだ//あの子/あなたに気を遣いすぎて身体をこわすわよ〉。〈彼〉が〈行列もひとごみも苦手〉なことはそれまでに二度も書かれている。周到だ。そして、この九ページの間に読者の記憶に残っているのは、〈ユウキ〉がいかに〈母〉のために気を遣ってきたかである。にもかかわらず、〈はは、は〉〈そうと気づきもせずに〉〈わるい予言のように〉(詩ではこの三行はまったく逆の順序で並んでいる)、その言葉を口にしてしまったのである。〈私〉の〈はは〉に対する怒りが並大抵のものではないことは、〈すべり込む呪いの言葉を洗い流そうと/夜半/ふたつの耳にシャワーをあてる〉という最後の三行がよく表している。
ここまでを俯瞰的に見ると、「訪ない、かれの」で示された〈母〉と〈彼〉の潜在的な競合関係が、「まじなふ、ははは」で顕在化したというように感じられる。〈母とユウキと三人/いっしょに暮らす〉(「訪い、かれの」)というのは、どちらか片方を選ぶことができない〈私〉に合わせてほかのふたりが動いてきたということだ。〈私〉との関係を維持したければ、〈母〉と〈ユウキ〉は潜在的競合関係をあえて無視して三人の暮らしを目指さなければならない。「訪ない、かれの」と「まじなふ、ははは」を通じて〈ユウキ〉はそれをしっかりと実行してきたが、〈母〉はすでに「訪ない、かれの」の時点で危うくなっており、「まじなふ、ははは」ではついにうっかり〈幼い姫の誕生を祝う席に遅れて現われた/年老いた魔女の/呪いの言葉〉を吐いてしまった。しかし、〈あの子/あなたに気を遣いすぎて身体をこわすわよ〉という言葉は、〈母〉の意図とは裏腹に、〈あの子〉=〈ユウキ〉、〈あなた〉=〈母〉だということを〈私〉に教えたのだ。そして〈母〉との共存はあり得ず、どちらを選ぶかを迷っている余裕はないことも(さらに、このあとの三篇を読めばわかるように、〈私〉は〈あの子〉とは〈ユウキ〉以上に〈私〉だと感じていたはずだ)。
《弐》の残る二作「はくり、ひとの」、「ばっこばっこ、ははは」と《參》の唯一の作品「ものぐるひ」は、同じ日の同じできごとを中心として成り立っている。「はくり、ひとの」は見開き二ページでこの詩集のなかでもっとも短く、「ばっこばっこ、ははは」は十四ページ、そして「ものぐるひ」は二十二ページでこの詩集のなかで群を抜いてもっとも長く、特異な作品でもある。こちらに書かれていることがあちらには書かれていないということがあるので、三作のなかの重なる箇所、重ならない箇所をつなぎ合わせて読まないとわからない部分がある。
たとえば、「はくり、ひとの」では〈いさかうことがあって〉としか書かれていないこと(そして、「ばっこばっこ、ははは」では触れられていないこと)は、「ものぐるひ」を読むと〈「テレビつけたるままならば彼のひと/いたう疲るるによって/み終へたまはば消さるるか/おのが部屋にてご覧じたまへ」〉という〈私〉の言葉に〈母〉が〈口あらがひを責〉めたことだということがわかる。そして、「はくり、ひとの」では〈びんせんというもの/しょくたく/かきおかれた文字があって」、「ばっこばっこ、ははは」では〈書き置き四行〉としか書かれていなかったものが、「ものぐるひ」では〈「さらば かたじけなう ゆるしてたべ 幸あれかし」〉と擬古文に書き直された形で出ている(「浜風文庫」に残っている改稿前の「ものぐるひ」(https://beachwind-lib.net/?p=25821)には〈さよならありがとうごめんねしあわせに〉という現代文の形が含まれている)。
しかし、もっと注目すべきは、「はくり、ひとの」で〈泣いてただただわびるつねの習いもとじこめ〉、「ものぐるひ」で〈あさましやな/口あらがひを責むれば/泣き泣き詫ぶる習ひのあの子が/御免ごめん許してたべと度重ぬるさまの/うるさうて かまびすしうて/おぼへず/あなかまつと聲荒らぐるほど/執念くて/かかるあの子が/詫び言せぬ/詫ぶることばをのみこむがごと/睨めつくる/おそろしや 怖やの〉と書かれていることだろう。どちらにも〈習い〉という言葉があり、その日には〈習い〉に反することをしたというのだから、その日まではそういう絶対服従が〈習い〉になっていたのである。《壱》からはそのような〈習い〉があることはとても想像がつかなかったので、読者としてはびっくりだ(そうと知ってみると、「河津、川べりの」の〈だったら/だったら〉の二行で始まる連や、「穴子、瀬戸内の」の〈旅のミッションその二〉あたりにその兆候があったのかとも思うが)。
よく読むと、「ばっこばっこ、ははは」にも、〈あんたにわるい/言われれば打ち消す/くりかえしだった〉という箇所がある。「〈あんたにわるい〉と〈言われれば〉自分の言い分を〈打ち消す〉〈習い〉だった」と解釈すればよいのだろう。ここには〈泣いてただただわびる〉とか〈泣き泣き詫ぶる〉という言葉が入っていない分衝撃度は低いが、同じ〈習い〉のことを言っていることがわかる。そして、そのような〈習い〉の原因または理由と思われるものは逆に「ばっこばっこ、ははは」にしか書かれていない。
そっぽむきたい
むいてもいいと
気づかなかった
ずっと
兄弟姉妹なく父なくなり
「仲よく」「大事に」と
言われた日から三十六年
あかるみにでてしまえばもう
つつみ隠すことは難しい
(以下略)
この詩集の本当のクライマックスはここだろう。〈「仲よく」「大事に」〉という言葉がマインドコントロールのように〈私〉を〈三十六年〉も縛ってきたのだ。しかし、〈そっぽむきたい/むいてもいいと/気づ〉いてしまった。〈あかるみにでてしまえばもう/つつみ隠すことは難しい〉とはずいぶん抑えた控え目な言い方だと思うが、〈気づ〉く前とあととでは革命が起きたぐらい、世界がひっくり返ったぐらいの違いがある。《壱》を書き始めたときには作者も想定していなかったことが起きて、それが詩集全体を支配している。
〈あんたにわるい〉の直前に〈ごっこ/ごっこだったのか/ずっと仲のいい親子に/見えたろう思われたろう/思っていた/うっかり/水をむければ応えるひとを/もてなすのが習いになっていた〉という八行があるが、〈もてなす〉というのは《壱》のもとになった旅のことだろう(後記にも、旅の提案について〈水を向けると母も応じた〉とある)。実際、《壱》を書き出したときにはそんな意識はなかったから《壱》を書けたわけだが、ここでは〈うっかり〉という言葉で《壱》を全否定している。しかし、《壱》の旅の記録があれだけしっかり書かれていなければ、ここの〈うっかり〉の重さは読者には伝わらないだろう。そういう意味で、《壱》はえらく長い前置きだが必要不可欠なのだ(前置きなどと書いてしまったが、拙文の前半で縷々書いてきたように、《壱》だけでも優れた詩集として成立し得るものの、この〈気づ〉きを知るとそれすらも前置きに見えてしまうという意味である)。
では、どこで〈あかるみにでて〉〈気づ〉いてしまったのか。それを示すために書かれたのが《弐》の最初の二作、特に「まじなふ、ははは」だろう。対立が誰の目にも顕在化したのは、〈母〉の家出が起きたときだが、〈私〉が〈気づ〉いたのは〈呪いの言葉〉のことを聞いたときである。それは実際にその〈呪いの言葉〉が発せられたときからまもなくのことだろう。花見は三月末か四月初めのことだと思われる。家出は〈五月〉と明示されている(「ばっこばっこ、ははは」)。一か月と少しぐらいの短い間だが、〈私〉の〈気づ〉きと〈母〉の家出にはタイムラグがある。上の引用で(以下略)とした〈べつべつのひとひとりずつと申し立て/剥がしてきたうえでなお/うかがっていた/もっとそっと/なだらかに切り分けるナイフを/もたなかった〉という六行にその短いタイムラグのことが書かれている。
〈べつべつのひとひとりずつと申し立て〉の部分は、〈私〉が〈母〉に対立する形になっても自分を貫くようになったということだろう。「ばっこばっこ、ははは」のなかで〈叔父〉の〈「ここに来るしかないってわかっとるやろ」〉という言葉に対し、〈なぜ/なぜわかるとおもう/ひとひとりのことを/わかるなどとなぜ〉と憤っているのも、それとつながっている。その〈叔父〉は〈「仲よく」「大事に」〉と言ったひとりなのかもしれない。
〈うかがっていた〉というのは、〈泣いてただただわび〉たりしない態度を示すチャンスを〈うかがっていた〉ということだろう。そして、〈もっとそっと/なだらかに切り分けるナイフを/もたなかった〉というところに切迫感がある。〈あさましやな/口あらがひを責むれば/泣き泣き詫ぶる習ひのあの子が/(中略)/詫び言せぬ/詫ぶることばをのみこむがごと/睨めつくる〉という〈ナイフ〉は、なるほど〈そっと/なだらか〉だとは言い難い。
この部分は、「訪ない、かれの」の後半部分を思い出させるところでもある。〈そっぽむきたい〉の直前に〈朝こじれて夜帰ると/席をたった食卓が/そのまま/冷めきって〉という四行があるが、これは先ほど〈母〉が不安定化、自壊していく様子として引用した箇所の最後の行〈食卓が席をたった朝のままの日もあり〉と同じことを言っている。その引用箇所は連を変えずに〈ユウキとはじめての旅〉のことも描いている。〈京都で大喧嘩/泣いたり怒鳴ったり駆けだしたり黙ったりまくしたてたり/つづいて高野山四天王寺/笑い転げたりハグしあったり〉というのだが、まさに支配関係のない独立した(〈べつべつの〉)人と人の交わりではないだろうか。〈ひとひとりのこと〉が〈わか〉らないからこそ〈大喧嘩〉もするのだ。
あとは家出の結末だ。「はくり、ひとの」は家出のシーンで終わっているので、そこには触れていない。それに対し、「ばっこばっこ、ははは」は〈それでも//三人で暮らそうと/春先の旅も一緒だった/彼が駆けつけ/待った/しらっと/夕方だった/帰ってきた/母のくちから/別に暮らす話/ふるえる声/もの言えぬわたしに代わり/「それがいいです」と/きっぱり/彼/スープのさめない距離と/叔父叔母に言われ/うなずいて帰ったけれど/こわばった顔に/あきらめたらしかった〉、「ものぐるひ」は〈なれど//うからに説かれ/三日目/もどれば/もの申さぬあの子/カレと呼ばるるかの親切なりしをのこ在りて/おかあさんと呼ばれたり/まつしろなり/まつしろ/ドア押し開くる/また〉と描いている。
両方に描かれていることがあり、一方に描かれていてもう一方に描かれていないことがあるが、たぶんどちらにも描かれていないことがある。だから読者としてはよくわからなくてじれったいが、ほかならぬ「はくり、ひとの」で〈ことばにうつすと何かがもれおちる/うつしとられたものばかりに宿る事実はうそくさい〉と言っているのだから、この詩集の読者は、書かれていない部分があることを覚悟しなければならない(これはここだけでなく、《壱》から《參》までのすべてに当てはまることだ)。ただ、〈三人で暮ら〉すことはもちろん、〈スープのさめない距離〉で暮らすこともなくなったということははっきりとわかる。
【三】
《參》の「ものぐるひ」については、先ほど特異な作品だと言っただけのことはあって、まだ触れておきたいことがいくつも残っている。特異ということで誰でもすぐに感じるところは、全体が擬古文で書かれていることだ。もっと具体的に言えば、能の謡曲の形式にかなり近づけてある。
これだけでもかなり実験的な試みだが、実験的ならすばらしい、とてもいいというものでもない。なぜ能の謡曲という形式を借りたかが問題になる。その前に謡曲がどのようなものかを簡単に確認しておこう*1。
言うまでもなく能は古典的な演劇だが、主役であるシテ(シテに従うツレがいる場合もある)と脇役のワキ(ワキツレというものもいる場合がある、一部ワキのない曲もある。ワキはシテと丁々発止のやり取りをすることもあるが、たいていは観客の代表としてシテの話の聞き役になる)、進行役(狂言回し)のアイが舞台で所作をしたりセリフを言ったりする(アイのない曲もある)。そのほかに、笛、小鼓(こづつみ)、大鼓(おおづつみ)、太鼓(たいこ)の囃子方、観客から見て舞台の右側に座って合唱する地謡(場面の説明をするほか、シテの内心の思いや謡の続きを謡うこともある)、芝居を進めるための裏方を担う後見がいる。謡曲は舞台台本で、シテ、ワキ、アイ、地謡が関わってくるが、シテと地謡はシテ方の家、ワキはワキ方の家、アイは狂言方の家が代々務めてきたため、謡曲本にはそれぞれの家で必要なことしか書かれていなかった。これを初めて全部載せたのが九十年前に岩波文庫として出版された野上豊一郎編『謡曲選集』で(同書のはしがきが以上のようなことを説明している)、出版各社の古典文学全集的なものの謡曲集の巻もそのような作りになっているだろうと思われる(少なくとも、手元にある小学館『日本古典文学全集』の謡曲一、二の二巻はそうなっている)。「ものぐるひ」は、この形式にならい、インデントによってシテ、ワキ、地謡(シテの内心の思い)が見分けられるようになっている(【一】の冒頭で指摘した区別なしの形式とは異なるということである)。
「ものぐるひ」では、《弐》までの〈母〉が〈嫗どの〉としてシテの役割を果たしている。能にもいきなりシテが出てくる演目はあるが(あとで触れる「三井寺」もそうである)、普通は最初にワキが自己紹介(名ノリ)をしながら出てくる。「ものぐるひ」でも、最初に出てくるのはワキで、高松に旅行(〈Go To トラベル〉)でやってきた学生という設定になっているが、嫗が語ることはともかく、この学生と嫗のやり取りはもちろん、学生の存在自体もフィクションなのではないかと思う。
これはあくまでも私(この文章の筆者)の考えに過ぎないが、《弐》は〈私〉の一方的な主張ばかりだったので、読者としては〈母〉にも言い分があるはずだということがずっと気になっている。いや、作者としても、〈はは〉を罵倒しまくった「ばっこばっこ、ははは」で終わるのではちょっと後味が悪かったのではないかと「想像」する。しかし、「ばっこばっこ、ははは」で〈なぜ/なぜわかるとおもう/ひとひとりのことを/わかるなどとなぜ〉と〈叔父〉を非難した言葉はそのまま〈私〉にも跳ね返ってくる。〈私〉が〈母〉の立場を完全に代弁するということはあり得ない。
しかし、「ばっこばっこ、ははは」に〈ややあって返信また返信/わび言のち反論/また反論つきぬ反論/メールボックスにあふれる/母というひとの名と言葉〉と書かれていることから「想像」すると、作者の手元には〈母〉の言い分についての十分な資料がある。ただ、それ自体を衆目にさらすわけにはいかないだろう。何らかの工夫が必要になるはずだ。
幸い、能の謡曲は、日本の古典芸能にありがちなことだが、かなり様式化されている。シテのタイプによって「神男女狂鬼」(しんなんにょきょうき)という分類があり、以前は一日かけてその五種をその順番で五曲演じていた(五番立てという)。実は、「ものぐるひ」というタイトル自体、神男女狂鬼の狂(四番目物ともいう。ほかの四種に入らないものをすべて入れるので、雑物、雑能などとも呼ばれる)のなかのサブタイプ、物狂のことを表しており、これは行方不明になった愛する男や腹を痛めた子を探し求める狂女がシテを務めるという内容のもので、能の子を探す狂女の演目としては「三井寺」、「隅田川」、「百万」などがある。なお、能の「狂う」は精神疾患のことではなく、神がかりのようになって舞い謡うことである(だからそのときは「正気」ではなく、トランス状態になっている)。
以前にも触れたように、この詩集の大半の作品が最初に発表されたウェブサイトの「浜風文庫」には「ものぐるひ」の初稿(二〇二〇年十月三日付け)が掲載されているが、そちらでは〈媼〉が〈学生〉に言った言葉とワキの〈学生〉が言った言葉、心の声だけが擬古文で、〈媼〉の心の声または独り言は現代文になっている。大半がその〈媼〉の心の声または独り言なので、擬古文の部分は少ない。
それに対し、二〇二〇年十二月十日付けの完成稿(ふりがなを追加したことや小さな「っ」を大きな「つ」に変えたこと、最後の〈あと けらけら と申しける〉の一行を独立した一連として繰り返したことなどを除けば詩集に掲載されているものとほぼ同じもの、以下は詩集掲載版を参照する)は、すべてを擬古文にしている。擬古文かどうかで口にした言葉と心の声の区別をしていたものが全部擬古文になったためか、心の声の部分は丸括弧で囲まれるようになった(能なら地謡に謡ってもらうような部分だろう)。そして、改作前は学生がシテの話を聞くというワキの役割を放棄したため、〈媼〉が現代文で独り言を〈吠え〉る羽目になっていたが、改作後はワキらしく、少々間抜けに感じられるところもあるが話を聞くようになったので、現代文の独り言だったところがワキ(と観客、すなわち読者)に対する語りになっている。
両者を比べると、改作前の現代文による〈媼〉の語りは妙に生々しく感じられる。《弐》までの〈私〉の視点から語られたことと張り合うような混ざり合うような変な感じがする。しかし、言葉の調子も含めて能の型に嵌めることによって、その生々しさが消えたのだろうか。私(この文章の筆者)はうまく理屈にすることができないが、もっと感性的なレベルでこれしかない、はまっているという感想を持つのである。
以上を念頭に置いた上で内容を読んでいこう。拙文の【二】では、『《弐》の残る二作「はくり、ひとの」、「ばっこばっこ、ははは」と《參》の唯一の作品「ものぐるひ」は、同じ日の同じできごとを中心として成り立っている』と書いたが、正確に言うと「ものぐるひ」は《壱》と《弐》の総集編のようなもの(ただし、〈家族の来し方や日常〉の部分だけで、旅の部分は除く)になっている。もちろん、〈母〉の視点から語られているので、《壱》、《弐》とは違う部分がある。ここではもちろんそこを中心として見ていくことになる。
まず、当たり前と言えば当たり前だが、一人称が別の人になったので、家族の呼び方が変わっている。《壱》、《弐》での〈父〉は〈背の君〉または〈あのひと〉、〈私〉は〈あの子〉、〈母〉は〈みづから〉になる(〈叔父〉も〈弟〉だ)。この作品には〈メール〉、〈携帯〉、〈ソーシヤルデイスタンス〉といった新作ではない能には決して入ってこない語彙が多数入っているが、目立たないながら〈あのひと〉と〈あの子〉もそうだろう。このふたつの単語は、読むのに苦労する擬古文のなかでそれこそ生々しく記憶に残る。
全体は強いて分ければワキの学生がうどん屋に入る前と出てきたあとに分けられる。前半では心の声として〈あのひと〉の思い出を語っているが、後半では〈あのひとと/暮らしたる二十二年/うれしうてたのしうて/会社勤めせはしく/家にあらぬこと多きひとなれば/さみしうはさうらへども〉、〈せはしきあのひと つまの/いたって健やかなるがある折/あさましや床に伏し/さうしてやうやう共に居らるる時を得てさうらふ/うれしうて憂はしうて/二とせあまり/あのひとは ああ/はかなうなりて若きまま〉と〈あのひと〉にちょっと触れたあと(ここには新しいところはなく、《壱》の終わりの方の復習である)、もっぱら〈あの子〉の話になる。前半と後半冒頭は話を本題に導いていくための糸口であり、本題が後半にあることは明らかだ。ただ、二つの引用箇所の間に〈あの子/ひとり子の/あの子の居れば〉という三行があって、〈あの子〉が〈あのひと〉の代わりになっていたことが示唆されていることは目を引く。
次に目を引くのは、〈あの子〉が大学を卒業して就職したあとの〈ある日ひとりのをのこ参りて/むすめ御をふた親にまみえさせたしと申す/否むことはりとてなく/そののち/ひとり子なればとてみづからと三たりにて暮らせども/ふいに了んぬ〉という六行だ。今まで〈デモドリ〉という言葉が何度か使われていたが、「家を出て」はいなかったことに驚く。しかし、それ以上にぎょっとさせられるのは、〈あの子〉の離婚が〈ふいに了んぬ〉と自然現象のように描かれていることである。おそらく、そのときも「まじなふ、ははは」で描かれたようなことがその〈をのこ〉に起きていたのだろうと想像してしまう。そして、その連の締めくくりがまたも〈あのひと〉の身代わりとしての〈あの子〉を示唆する〈むすめなれど/しごとにんげん、とや/さながら背の君の代わりと/にがわらひ〉という四行になっている。
〈なれど/あの子が〉の二行の連からは《弐》の内容に踏み込んでいく。拙文の【二】で述べたように、ここは復習というよりも「はくり、ひとの」と「ばっこばっこ、ははは」に書かれていなかったこと(またはその時点ではまだ書けなかったことかもしれない)が初めて詳述されている。それについては繰り返さないが、ワキの学生が〈ここな嫗どの/しづまりたまへ/御身の背の君の物語をば聴かむと申したるに/あの子とや/御子のこととや/うたてやな/あさましう いとどことさめてさうらふ〉と文句を言っているのは好プレーであり、話が〈あのひと〉から〈あの子〉に逸れていっていることを読者に教えてくれる(これは、この詩集が旅を主題としているかのようなふりをしているけれども、本当は〈あの子〉が〈嫗どの〉から自立した経緯を描いた叙事詩集であることも示している)。
家出から三日目に戻ったが〈あの子〉の拒絶に遭って再度〈ドア〉を〈押し開くる〉ことになったというところで、再びワキのセリフが入る。改作前は〈袖すり合うとは申し条/ソシアルディスタンスな今日った/触るるはご法度/うちすてて参らずばなるまいて〉と言ってワキの役割を放棄してしまったところだが、改作後は〈袖すり合ふとはまつことこのこと/少し歩みたうなりたれば/歩みあゆみ承らうよ〉と言ってワキを務めきることを申し出る。謡曲の型があと少し頑張れと詩人の背中を押したような形だ。
それにしても〈少し歩みたうなりたれば〉とはずいぶん間抜けな物言いだなと思うが、〈歩〉むことから〈潮風みなはの洗ふ城とは/あれなるや/たまもてふ波うつ石垣/港ちかき海ぎはへと歩をすすめて参らうよ〉と高松城のことを話題にしているのはまたも好プレーだと言える(ちなみに〈たまも〉とは高松城跡の玉藻公園のことを指している)。冒頭の心の声の部分で〈潮の匂ひないたす此処は/あのひとに初めてあり会ひし町〉と懐かしさを示した高松に対して、歩き出してからの〈嫗どの〉は次第に気持ちが昂ってきて、〈おう おぼへぬ/いい 見も知らぬ/おお とほき遠きい町/うう 疎うとしき/知らぬ人ばかりの町〉と拒絶的な態度を示すが、その予告になっているのである(なお、各行冒頭の二字は、そのあとに続く言葉の冒頭の音の母音に対応している。〈見〉(み)は「い行」なのでその前が〈いい〉、〈疎〉(う)は「う行」なのでその前が〈うう〉となっている。もっとも、〈おぼへぬ〉の前が〈おう〉、〈とほき〉の前が〈おお〉になっている理由はよくわからない)。
少し先に進みすぎたが、ワキのセリフの直後に戻ろう。〈おうおう と/聲あぐるはいと易けれど/おしころし押し殺す底ひより/たぎりたちくるもののさうらひて/あの/あの子/あの子の名 を/こゑ に/こゑ に出ださず/聲 にせむ〉というところは難しい。嘆く声を押し殺しても、心の底から吹き出してくるものがあって、それが〈あの子の名〉だということなのだろうが、〈こゑ に出ださず/聲 にせむ〉というところの〈こゑ〉と〈聲〉の違いは何なのか。
実はこの詩のなかでは、〈あのひとの血縁〉の〈ナミコさん〉の名前は出てくるが、〈あの子〉の名前は出てこないのだ。実際に出てきた〈聲〉は〈えおう いい いい〉というものだが、先ほど引用した〈おう おぼへぬ/いい 見も知らぬ/おお とほき遠きい町/うう 疎うとしき〉と同じように解釈すると、〈あの子〉の名前である「めぐみ」の母音だけを抜き出した「えうい」を引き伸ばしたものだと思われる。〈なにかに似たれど なにやら覚束ぬものの/名のごと/したたるなりわたる/音に濡れ〉とはその声が遅れて耳に入ってくる様子だろう。
続いて〈びやうびやう/吹き鳴らしたるは/のどならむ こゑ ならむ〉というのだから、〈こゑ〉は発声前の意図のことだろう。名前そのものを言うつもりがないのだ。それに対し、〈この身の/なにかににたれど なにともおぼつかぬ/聲〉は発声後に響いた音のことだろう。ここからは〈こゑ〉を発した(子を生んだ)〈母〉(〈この身〉)の〈なにかににたれど なにともおぼつかぬ〉〈娘〉(〈聲〉)という関係が見えてくる。〈ひとひとり〉という現実に耐えられない〈母〉の姿を描こうとしたものだと思われる。
そして、先ほども引用した〈疎うとしき/知らぬ人ばかりの町〉で数少ない〈見知りたる/ひと〉である〈細うて優しき/折ふしこはき/ナミコちやん〉に連絡を取ろうとしたのか、〈書き込みひとつなき/暦をぞめく〉る。ここでワキの〈ナミコどのとやらむ/むすめ御にてさうらふや〉というセリフが入る。〈嫗どの〉が〈とうにおはさぬ/あのひとの血縁/ナミコさん〉と言った直後なので、今度こそこのワキは間抜けなやつだと思ってしまうところだが、〈嫗どの〉が〈あの子の名〉を「えうい」としか言っていないのに〈ナミコちやん〉の名を言っていることを読者に注意させるためのセリフだと考えるべきだろう。
そして久しぶりだと思われる電話が〈あの子のカレと申すをのこ〉からかかってくる。〈殆としう果つるものを/ほとほとしう果てぬにや〉はほとんどかからなくなった電話がかかってきたことを言っているのだろうが、〈果つる〉という言葉からは自らの死を意識しているのかという意味合いも強く響いてくる。そして〈ま〉があったものの〈あの子の こゑ 聲〉も聞く。
能の物狂は、探す人を見つけてふたりは幸せに暮らすという形で終わるのが普通である(「隅田川」の場合は子が死んでいることを知って嘆いているところに子の幻が現れるという形だが)。電話というなんとも現代的なものを介してだが、ここで能の型に沿うかのように親子の疑似再会が果たされるわけだ。
しかし、ここで疑問が湧いてくる。〈切つ先ふるふと思へば〉というのだから携帯電話だ。携帯以前の電話なら市外番号の異なるところに引っ越したら電話番号がすっかり変わってしまって電話もかけられなくなる。携帯電話も少し前ならキャリアが変わったら番号が変わっていたが、二〇〇六年にはMNPが導入されて変えなくて済むようになった。それなら、この〈嫗〉は〈あの子〉の声を聞きたければ自分で電話すればよいのではないかということだ。
思い出さなければならないのは、「ばっこばっこ、ははは」の最後の部分である。〈母〉は実際にメールも電話もしている。しかし、〈わたし〉はそれに疲れて〈着拒〉に及んで〈圏外〉に去っているのである。そういうわけで、電話をかけてもつながらないのだ。だから、〈あの子のカレと申すをのこ〉(この〈カレ〉というのも古典の謡曲には絶対出てこない語彙だ)から電話がかかってきたら、〈あらあ/おぼえずはねあがる/こゑ 聲/みづからがこゑともおぼえぬ/こゑ〉が出るぐらいのことなのである。
ここで〈こゑ 聲〉となっているのは、〈こゑ〉と〈聲〉が一致しているということだろう。そして、〈あの子〉の〈こゑ〉と〈聲〉も一致している。これは、〈えおう いい いい〉などという発声をしていないのだから当然のことだが、〈嫗〉がそこまで追い詰められていたということを想像すべきだろう。そして、〈みづからがこゑともおぼえぬ/こゑ〉が〈こゑ〉であって〈聲〉でないのは、うわべの声だけではなく心から喜んでいるということを表しているはずだ。
しかし、〈かあっとあつうなりたる〉あまり、〈嫗〉は失敗してしまう。〈たらちめなりみづからはみづからはあのこのたらちめなり/あの子の生まれしより長ういなあの子をはらみしより長う/いちにちたりともかくることなう長う/みづからはたらちめなりなればこそ/たれば たら ただこのたらちめは〉と〈あの子〉は自分と一体だとまくしたて、〈あの子〉が〈ひとひとり〉だということを否定してしまい、電話を切られてしまう。〈嫗〉は〈きれてありしやきりたるものや〉と言っているが、切られたことは明らかだ。読者としては、作者は〈嫗〉が〈ひとひとり〉という現実を突きつけられたが、どうしても受け入れられずにいるということを描こうとしたのだと解釈すべきだろう。
〈嫗〉は電話がかかってきたから、手紙でも届いていないかと〈郵便受け〉を見に行くが、そんなものは当然ない。〈たぎりたる/つむりのひえて〉とあるが、物狂能の型として、子と再会した母は物狂の状態から脱する。探し求めた子が死んでしまったことを知った「隅田川」の母親も探し求める理由がなくなったので物狂ではなくなる。この〈嫗〉も〈うれしき切れ端握りなほし〉〈うれしき思ひの絵文字選りて〉〈ナミコさあん〉にメールを書き始めるが、古典の物狂能のシテたちとは異なり、〈嫗〉には〈ゆくりなう/ぐうつとせきあぐるもの〉(思いがけず噴き出してくるもの)がある。そのため、〈メールの文字〉が〈重うにごりそめ〉、〈いかな了見にやあの子とや/カレとやらむ申せしひとも/きがしれぬきがしれぬいまごろでんわして寄越すきがしれぬ〉と書いて送ってしまう。
送ったのが深夜の非常識な時間なので(〈12さしたる/針ふるへ/糸とほさぬ時計の/針ふるへて〉。〈母〉が得意な洋裁の針に触れているところが面白い)返事は朝になるが、ナミコさんもよくつきあってくれるものだと読者は感心してしまうところだ。しかし、〈嫗〉からすると、ナミコさんは《壱》の時代までの〈あの子〉のように自分を理解してはくれないという思いなのだろう。〈ナミコさん〉初出時に〈細うて優しき/折ふしこはき〉、〈語りかくれどひたと見上げをる〉と形容してあったので、〈わらはぬをさなごのナミコさんのみつめをる〉が効いてくる。〈嫗〉は〈ナミコさん〉では満たされないのだ。
ここまでが〈嫗どの〉の回想で、能なら地謡がかなりの部分を歌ってシテが舞っていたところだろうが、次の〈こ、こはいかに嫗どの/そこな畳まれたる/携帯の鳴りをるやらむ/嫗どの をうなどの〉というワキの言葉で現実に引き戻される。ワキはすべての出番で好プレーを演じている。しかも、〈畳まれたる〉という言葉で〈嫗どの〉の携帯がこの時点での主流であるスマートフォンではなくガラケーだということまで教えてくれるのだ。
次の〈嫗どの〉の最後のセリフは絶唱とも言うべきところで、〈みづからを〉の五音のあとは七五調を貫いている。これも能にはよくある形で、感きわまったところのセリフは七五調になる。たとえば「隅田川」でも、行倒れの少年を弔うために土地の人々が行っている念仏の対象が自分の子のことだとわかったときのシテは、「今までは/さりとも逢はんを/頼みにこそ/知らぬ東(あづま)に/下(くだ)りたるに/今はこの世に/亡き跡(あと)の/しるしばかりを/見る事よ…」*2と謳う(字余りが少々あるが)。
ちょっと脱線するが、河合祥一郎氏によれば、シェイクスピアの『ロミオとジュリエット』などの初期作品には彼の詩人としての試みが劇作に大きく反映されているという。河合氏もそれを意識して『新訳ロミオとジュリエット』(角川文庫)では「表現の技巧には特に留意したつもり」だとして、たとえばソネット形式になっている一幕と二幕の間の歌(コロス)として〈はかなくも、古びた恋は、墓の中、/新たな愛があとを継ぐ。…〉という現代文による七五調の訳文を作られている*3。劇の一部の(あるいはそれを独立させた形の)七五調の詩の可能性には注目すべきではないだろうか。ついでに言っておくと、拙文で擬古文という言葉を使い文語という言葉を使っていないのは、中世語の語彙と文法で書かれていても登場人物が口にする言葉は口語であって決して文語ではないだろうと思うからである。
さて〈嫗どの〉の七五調の絶唱だが、こういうものの常として、私(この文の筆者)のような凡人の身にはなかなか難解だ。「自分を呼ぶ聲も風のなかで消えてしまうぐらい田舎びた潮の鳴る道をどちらに行ったらわからないような毎日だが、亡くなった夫を慕っているので、そのときが来るのを待ってあちらの世に渡ろう」というようなところなのだろうか。前半三行は「しらぬ」と「しらむ」の音の近さで繰り返し朝がやってくることを呪っている序詞のような気がする。そして最初の三行のなかでも「みづからを呼ばはる聲も風の間に/絶えむとばかり」までは「鄙びたる/潮鳴る道の左右しらぬ」を導くための序詞のように見える。そして、「しまなみ、そして川口の」冒頭の思念的な四行を思い出す「渡る」という言葉が使われている。
最後のワキのパートは、最初の三行一連がワキの言葉で、残り二連はワキの視点からの状況説明だ。ここでのワキも好プレーを演じていて、状況説明の冒頭で〈潮風にも消ぬ携帯の着信音〉と言って〈嫗どの〉の絶唱の序詞を否定している。〈炭いろの衣ふわとひるがへりて/突き出されたる枝先のごとき指より/今しなげうたれたるもののさうらひ〉は非常に技巧的に携帯電話を投げ捨てる様子を描いているが、〈携帯〉と名指ししていないので、私(この文章の筆者)は初めて読んだときには携帯を捨てたことに気づかなかった。何度か読むと、〈炭いろの衣〉(ワキがうどん屋を出てきたときの〈嫗どの〉の形容でも使われているが)から想像される(そして「まじなふ、ははは」の決定的な言葉を思い出させる)魔女のイメージと〈突き出されたる枝先のごとき指〉という描写もぴったり合っている。〈嫗どの〉の際限がない孤独感は「ばっこばっこ、ははは」の〈跋扈〉とはあまりにも対照的だが、作者にとって〈嫗どの〉はまだ〈魔女〉という存在なのだということを知るかどうかでこの作品の解釈は大きく変わるだろう。
この巻末の作品は、よく練られた巻頭の作品をはるかにしのぐほどの細心の注意のもとでとてつもないテクニックを駆使した大作であり、ずっしりとした存在感がある。ただ読んでいるだけなら適当に誤魔化してわかった気になってしまうところも、このような文章を書くことによって自分を追い込むと、適切なのかそうでないのかはっきりわからないものの、あれこれの意味(謡曲との類似点、相違点も)が見えてくる。このような作品はそうそう出現するものではないと思う。
*1. 私(この文章の筆者)がそこそこ親しんでいる古典芸能は歌舞伎だけであり、能、狂言、文楽などはどれも生で見たのは一回限りで正直なところよく知らない。しかし、歌舞伎は能、狂言、文楽を取り入れており、たとえば、能の「安宅」を歌舞伎化した「勧進帳」ではワキに相当する富樫左衛門が最初に出てきて自己紹介する。そういうところを見ているので、「ものぐるひ」がこれらの古典演劇をもとにしたものだということはすぐにわかった。それでも、歌舞伎でも狂言でもなく能らしいということがわかるまでは時間がかかった。ここで能の基礎知識として説明していることは、三省堂の『能楽ハンドブック』や小学館の『日本古典文学全集』三十三、三十四巻の謡曲集、各種ウェブサイト(特にthe能.com:https://the-noh.com/jp/と文化庁の文化デジタルライブラリー: https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/modules/learn/#c5。後者には「隅田川」の解説のページ: https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc14/sumidagawa/index.htmlがあり、物狂の能のパターンが説明されている。亡くなった子の幻と出会う場面を含む動画もある)などで一夜漬けで学んだことを垂れ流しているに過ぎないので、そのつもりで読んでいただきたい。
*2. 小山弘志、佐藤喜久雄、佐藤健一郎校注・訳 小学館『日本古典文学全集33 謡曲集一』pp.512-513。
*3. 河合祥一郎訳『新訳ロミオとジュリエット』(角川文庫)p.178、p.46)。なお、河合氏は筆者の高校の同期生だが、筆者は中高一貫校の高校に編入入学したため、同期生は百八十人ほどと少なめながら、そのうちのごく一部としか同じクラスになったことがなく、そうでなくても交友関係が隣の大学の同好会の名前を騙って駅前でどんちゃん騒ぎの飲み会をするようなメンバーに偏っていたので、同級になったことのない彼とは言葉を交わしたことがない(実は、同級生でも言葉を交わしたことのない相手がけっこういたと記憶する)。先方はこちらのことなどご存知ないだろう。一方、河合氏は高校時代から英語が抜群にできるということで、同学年の生徒でその名前を知らない者はいないという存在だった。
【四】
これを機会に今まで持っているだけで手が出なかった薦田さんの過去の詩集『苧環論』、『流離縁起』も読んでみた(詩人諸氏には申し訳ないが私のまわりにはそんな詩集が山ほどある。なお、『ティリ』は単純に持っていないので読んでいない)。特に印象に残ったのは、詩論として書かれたという『苧環論』の表題作「苧環論」だった*1。改めて詩集の姿形を見てみると、帯文に引用されているのも「苧環論」の一部であり、目次でもほかの作品と同等に(つまり、詩論として特別扱いされることなく)並んでいて、詩集タイトルにもなっている。詩集中の作品への言及もあるので確かに詩論といえば詩論なのだが、言葉の運び方がこれこそ詩だと思わせるものになっているのである。
たとえば、タイトルになっている苧環(おだまき)だが、最初は画家への贈り物として選んだ花として〈赤みの濃い紫のくすんだ色のや、水色から娼びた明るさを抜いたようなのや、黒に近い青紫の花びらがひっそりと聞いていて、すっきりと伸びた花茎の許を囲む葉の形も慎ましげなのが、うれしい〉という形で登場する。〈水色から娼びた明るさを抜いたようなの〉というような濃密な言葉はなかなか出てくるものではない。
それが次のページでは一転して文楽の『妹背山婦女庭訓』のなかの苧環の話になる。想い人の着物に糸を結んであとを追いかける男女が持つ糸車のことだ(花の方はこの道具に形が似ているので苧環という名前がついたらしい)。男(藤原鎌足の息子淡海)は糸のおかげで想い人の素性を知り(鎌足の宿敵である蘇我入鹿の妹)、女(豪族ではない市井の娘)は糸が切れて想い人(淡海)を見失うというあらすじを紹介した上で、〈私にとって苧環は、行方も知らずに導かれてゆく怖さ、心躍りの徴である。導かれてゆく先は、思いもよらない言葉の磁場である〉という美しい比喩で「詩論」の核心に入っていく。
これだけでも、若き日の薦田さんの比喩のセンスのよさと『そは、ははそはの』であらゆる形の比喩が詩の力を強めていることの根源がうかがえるが、「詩論」自体は〈私のつくる詩は、メッセージの伝達を志さない。また、物語の全景を描ききることもない。そこここに物語の断片を垣間見ることはあっても、それだけを手がかりに終点までゆくことはできないきまりごとになっている〉〈意味を解してしまう不自由な中枢を避けて、心の琴線にダイレクトに届く詩。/つい言葉の意味を追うことを忘れ、詞章の律動や音の心地よきに身をまかせ、たゆたってしまいたくなる詩。/私の書きたいのは、そんな詩である〉という方向に進んでいく。
この「詩論」をもっとも鮮やかに示しているのがスーラの比喩である。〈スーラが点描画においてとった方法は、従来のパレット上での色の融合ではなかった。より純粋な色を並べ置き、離れたところから見ると、溶け合って淡い澄んだ色調を楽しむことができるという仕掛け、視覚混合といわれるものであった/そこに用いられた色は互いに照り応えあい、反射して、澄んだ輝きを生み出した〉
ところが、この比喩はだんだん過激化していく。〈近くで見れば、タッチの安定した色の苗床である。そのどれもが、一枚の絵の構成部分という領分をこえて輝いて見えるので、画家がほんとうは、この色のひとつひとつを見せたかったのではないかと思えてくる。もっとも、この細部に生気がなければ、絵はたちまち艶のない、安ものの類に堕するにちがいない〉。
そして、それを言葉に〈応用〉するところに到達する。〈言葉を、その個々の意味において存分に立ち上がらせつつ、全体としての通意を断ち切る〉というのである。あれあれ、スーラは〈より純粋な色を並べ置き、離れたところから見ると、溶け合って淡い澄んだ色調を楽しむことができる〉ようにしたが、薦田さんは〈全体としての通意を断ち切〉ってしまうらしいぞ。
もっとも、詩は詩論を裏切るものだ。音による純粋詩を目指すかのような「詩論」とは裏腹に、『苧環論』に収録されている「詩」は言葉のさまざまな意味が交錯する空間になっているように感じる。私がたまたま知っている歌舞伎の用語が散りばめられている「なよたけすべらな爪沿い遣らずの傘さす保名の道ゆき夜もすがら棧敷をかけだす襟足その意気のとおさに折から獣心よびさます」やたまたま土地勘があって時代がわかる「本郷二丁目壱岐坂上潮が鳴る」では特にそれを感じた。すべての作品で音に対する作者の鋭い感性ははっきりと感じるが、「詩論」が主張するほど意味を消し去ろうとしているわけではないのではないか。。
ただ、「苧環論」以外の作品は、〈大層な主張があって、それがために言葉を動員するわけではない〉という点では共通している。それに対し、「苧環論」には〈主張〉があり、その〈主張〉を明確にするために、あるいは著者にとって納得のいく形で押し出すために、言葉を制御して使っているという違いがある。そのため、「詩」では封印されていた〈主張〉を展開するための言葉のテクニックが駆使されている。薦田さんはそのような技術を備えながら、「詩」ではその力を封印していたのではないだろうか。「詩論」として書かれた「苧環論」に「詩」として書かれた作品で見られない詩の要素を感じ、これは「詩」だと思ったのはそのためだろう。
『苧環論』について「詩」ではなく「詩論」から話を進めたのは邪道だが、『流離縁起』についても「ことの次第」という後記から入ることにしたい。〈対の詩集〉として構想していた『ティリ』(一九九五年)と同時期に書かれた作品を十年もあとの二〇〇六年に出すため〈書き手の個性よりも、書いた時代の匂いのほうが強く浮きあがるのではないか、と懼れた〉が、〈時代のにおいなどいささかもそなえていない、明らかに私という書き手の、略しがたい軌跡なのであった〉とある。
実際、『流離縁起』には『苧環論』以上に〈時代のにおい〉がない。〈本郷二丁目壱岐坂上〉のような実在する地名は一切入っておらず、読者は作品として描かれる未知の世界を所与のものとして受け取らなければ先に進めない。全体的な印象批評に過ぎないが、『苧環論』の詩篇には拡散していく開放性を感じるが、『流離縁起』の各詩篇には凝縮していく閉鎖性を感じる。その分、言葉の密度は高くなっており、筋をたどりやすくなっている。『流離縁起』の方が『苧環論』よりも初読で読みやすいのではないかと思う(私の場合はそうだった)。
「ことの次第」で先ほど引用した部分の次は、段落を変えて〈むろん、身の内からあふれた言葉ばかりではなく、離れて暮らしていた明治生まれの祖母の声音や佇まいなども織り込んでいる。すでに演劇作品へと形をかえて観客の耳目に届けた一節もある〉と続いている。〈むろん〉というところで、〈身の内からあふれた言葉ばかり〉では足りないということらしいと安心する。そして、〈祖母の声音や佇まい〉というのは巻末に四編ある「石積み」の連作のことだろうと想像する。「ことの次第」を読む前に全編をひと通り読んだが、「石積み(Ⅰ)で「じゃったの」という語尾や「わし」という主語に接して、外界と触れ合ったという感じがした。でも、〈演劇作品へと形をかえて観客の耳目に届けた一節〉はどこだったかわからなかった。
「肉鞠」という作品では〈生魚〉が嫌いな〈痩せた母〉という懐かしい人が登場する。また、「海駅」という作品の〈東の都市に向けての急がねばならない道のりを、人々の好んでする鉄路ばかりで行くことに倦んで、ふいに、この駅でなら叶う海路への乗り換えを、果たさなければと思い立ったのだ〉という一節では「しまなみ、そして川口の」の〈父〉と〈母〉を思い出した。順序が逆だが、不思議な既視感だった。
このように見てくると、この三冊が同じ人によって書かれたことはよくわかった。耳のよさ、古典文学/芸能、演劇の下地がどの作品にも共通して感じられる。もちろん、三冊それぞれに異なる色合いがあるし、【四】では私がわかる範囲でそれを明らかにしたつもりだ。まだ触れていないことで特に指摘しておきたいのは、『流離縁起』の後記が書かれてから時間のたった作品を集めている「のに」という文脈ではあるものの、〈時代のにおい〉がないことをよしとしているのに対して、『そは、ははそはの』は時代と場所の固有性をはっきりと描いていることだ。時代の移り変わりのスピードが上がり、文学が永遠を目指すことは難しくなっていることから、私は変化の過程の一瞬を後世に伝えることの方が有意義なのではないかと思っている。そういう意味で、『そは、ははそはの』は『流離縁起』が向かっていた方向から反転してよい方向に向かっていると思う。
三冊を比較したとき、入りやすさという点ではおそらく異論なく『そは、ははそはの』が一番ということになるだろうが、奥も深い。「本郷二丁目壱岐坂上潮が鳴る」や「石積み」連作などの例外を除けば、『苧環論』や『流離縁起』は単声と感じる作品が多いが、『そは、ははそはの』はほぼ全篇複声だと思う。入りやすさゆえに作者の文学的後退を感じるならそれは大きな誤りだろう。
この文章は書くために三か月近くかかってしまったが、特に【三】では毎日新しい発見があって作品に堪能させられた。しかも、【二】、【三】で詳述したように、《壱》と《弐》、《參》の間には後戻りできないような断絶があると思われる(つまり、もう《壱》を書いたときのようには作者は〈母〉を描けない)。そのような断絶(あえて自己否定と言いたいが)を抱えた作品は、ひとりの作者の生涯のなかでもそうそう巡り会えるものではないだろう。
歌舞伎を見ていると、いわゆる古典では眠くなることが多い。新作ではそれほど眠くならない。たぶん、古い芝居の時間は現代人の生活リズムよりもかなりゆっくり流れていてその遅さについていけなくなるのだと思う。速さについていけないのではなく、遅さについていけなくて眠くなってしまうのだ。遅いということは一つひとつの描写の密度が濃いということである。ひとつの感情に行き着くまでのプロセスが複雑なのだ。当代の市川團十郎白猿などは、せっかちな現代の観客のために、たとえば『義経千本桜』のような古典を早回しで見せる演目を作っているが、何度か両方を見ると、やはり原作の濃密さがよいと思う(それでも眠くなるが)。『そは、ははそはの』には古典歌舞伎のような濃密さがある。しかも、最大のテーマは〈ひとひとり〉という近現代の思想だ。多くの方にその濃密な味を堪能していただきたい。
*1. 薦田愛「朝顔だったか」(「浜風文庫」https://beachwind-lib.net/?p=35913)。