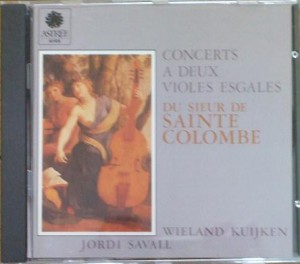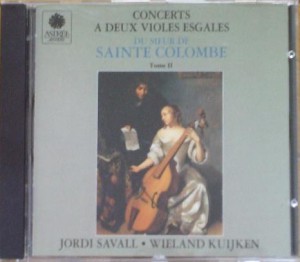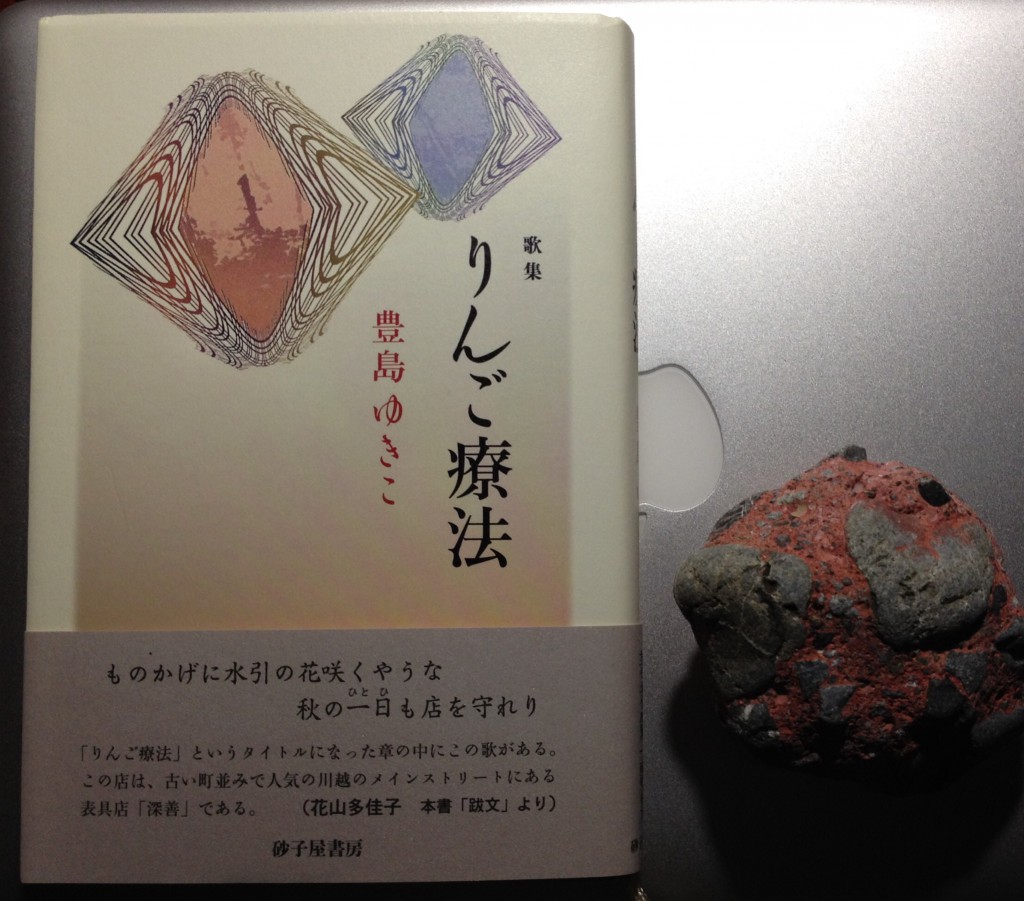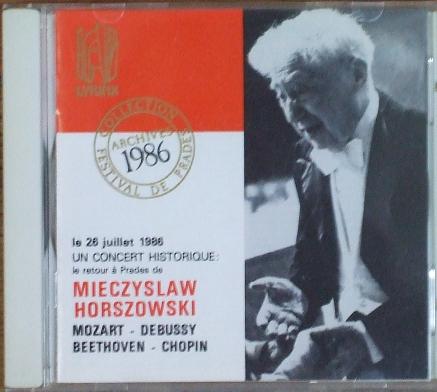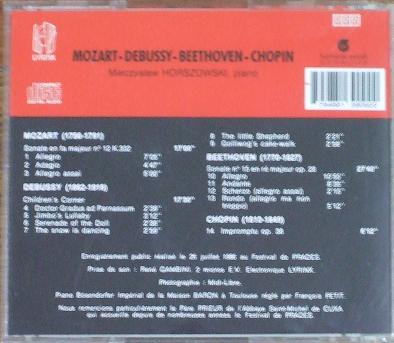木村和史
雪どけのころに北海道に渡り、初雪が降るころまで温泉分譲地の一画でひとりで家をつくるという生活を開始してまもなく、周辺に動物たちが多いことに気づいた。
分譲地にはすでに20数軒の家が建っていて、定住している人は半分くらい。あとは本州から避暑などでやって来る人や、別荘として利用している近隣の町の人たちで、しかもほとんどの敷地が数百坪前後の広さがあるので、もともとが北海道生まれとはいえ東京生活の方がずっと長いわたしの目に、人が少なくて緑と動物が多いと映るのは当然かも知れない。
まだ売れていない区画もたくさんあって、分譲会社が草刈りに入ったあと以外は雑草が伸び放題になっているし、わたしの敷地の目の前には小さな林もある。大型の動物は無理かも知れないが、小型の動物たちが居住する空間はいっぱいありそうだ。
一年目はテントで寝泊まりしていたので、とくに外の気配に敏感だった。リタイアした人たちが多いせいか、近隣の人びとの夜は早い。家の灯りが小さくしぼんでしまったあと、暗闇のどこかからなにか分からない物音がときどき聞こえてくる。一瞬緊張はするものの、どこかになにかがいるような気配の正体をつきとめるのは難しい。闇とはそういうものだとすぐに諦めて、東京生活のときよりずっと早い眠りにわたしも落ちていく。
朝3時を過ぎると、前の林で小鳥たちがにぎやかにさえずり始める。何種類もの鳴き声が重なっているので、聴くというより浴びる感じだ。後を追うように太陽が昇ってテントが炙られると、わたしもゆっくり眠ってなどいられない。夜更かしをすることもないので早起きは苦にならないが、それにしても追い立てられるようにテントを這い出すことになる。
小鳥たちに負けず、夜が早い近隣の人たちの朝も早い。まだ暗いうちからヘッドランプをつけて犬を散歩させている女性がいるし、夏には、6時半頃になるともう草刈り機の音が聞こえてくる。ほぼ半年間雪に閉ざされ、地面も凍っていて、外の仕事がほとんどできないのだから、残りの半年と貴重な昼の時間を目一杯活用しようという気持はよくわかる。というより、ここではそれが自然で、理にかなった日常なのだろう。
ここら辺で大型の動物を見かけることは滅多にないが、立派な角を持った大きな鹿が、近所の庭に彫像のように立っていてびっくりさせられたことがある。町道の反対側の、池のある雑木林のあたりにはタンチョウ鶴の夫婦が棲んでいて、時期になると子供を連れて歩いている。山の麓の友人のところでは、庭の切り株に新しい熊の爪痕があるのを発見して以来、夜になって庭に出るのは慎重になったそうだが、さいわいなことに、この近くに出没したという話はまだ聞かない。
目につくのはやはり、小鳥たちが圧倒的に多い。二年目の夏には、セキレイが材木の山の隙間に巣をつくって五羽の雛を孵したし、四年目あたりから物置小屋の軒先で、雀が年中子育てをするようになった。寒い季節になると、餌箱にゴジュウカラやコガラなどが、次から次へとやってくる。一人暮らしをしている隣りのおじさんのログの壁にキツツキが止まって、コンコン突ついていることもある。
いつの夏だったか、この世のものとも思われない、か細くて美しい鳴き声がどこからか聴こえてきたことがあった。賑やか過ぎるほどの、いつもの小鳥たちの鳴き声とは全然違う。仕事の手をとめて耳を澄まし、声のする方にそっと歩いて行くと鳴き声は止んでしまい、植木の根元を歩いている一羽の小鳥と一瞬目を合わせたけれども、その鳥が声の主だったのかどうか、結局分からずじまいだった。いつかまたあの美しい声を聴いてみたいと思っているのだが、その後一度も巡り会えていない。
夏の夜になると、前の林で一羽の鳥がひと晩中、よく通る声で、光をまき散らすように鳴き続ける。その鳥が一羽で舞台に立って、夏の夜を演出しているようなものだ。遠くから、それにこたえてもうひとつの鳴き声が聞こえてくるときもある。何年も経ってふと気がついたのだが、その鳥には縄張りがあって、その一画にはおそらく牡の、その鳥が一羽しかいないということなのだろう。
小型の動物では、エゾリスがたまに姿を見せる。来るときは毎日ほぼ同じ時間に、敷地の隅の植木に吊してある小鳥用の餌箱に押し入って、ひまわりの種を食べ散らかして去って行く。それがどうしてか、ぱたっと来なくなることがある。近所の人も同じようなことを言っていたから、あちこち順番に巡り歩いているのかも知れない。隣のおじさんが露天風呂に浸かっていたら、突然、子リスが6匹、頭の回りを駆け回ってびっくりさせられたことがあったという。そんなところでも巣作りをしているようだ。
テント生活に入って間もないころ、林の暗闇の向こうから、もの悲しい笛のような鳴き声が、遠くなったり近くなったりしながら、あっちからもこっちからも聞こえきたことがあった。テント生活は、得体のしれない物音にいつも包まれているようなものだが、さすがに大がかりな得体の知れなさだったので、翌日、隣のおじさんに訊いてみると、群れを離れた若い牡の鹿たちだという。もの悲しいどころではなく、威勢良くどこかへ繰り出す途中だったのかも知れない。二十歳過ぎまで北海道にいたのだから、鹿の鳴き声など、どこかで聴いていて不思議じゃないと思うのだが、記憶に残っていない。車であちこち走り回るような時代じゃなかったせいもあるだろう。晩年のこれから、あらためて故郷の北海道を学ぶことになりそうだ。
わたしはまだ目撃したことがないが、小さな犬を連れて一日に何回も散歩している女性が、三本足の大きな狐がここら辺を縄張りにしていると教えてくれた。朝早い時間に遭遇することがあるという。
10月下旬に本格的な霜が降りて、6畳の寝泊まり小屋がようやくできあがり、テントの寝床を移動して、屋根の下で布団にくるまれる喜びをかみしめていたとき、朝起きると外に脱いでおいたサンダルが見あたらない。あたりを探してみると、霜で真っ白に濡れた隣地の草むらに、ずたずたに食いちぎられているのが見つかった。そのとき、三本足の狐のことを真っ先に思い浮かべた。わたしがこの地に住みつこうとしていることに苛立ったか、わたしを脅して立ち退かそうとしたか、とにかく何かのメッセージのように思えた。サンダルと戯れただけではなさそうな気がする。野生のミンクが鶏を襲ったりもしているようなので、三本足の狐のせいにするのはまったくの濡れ衣かも知れない。しかし犯人が誰であれ、メッセージはわたしの心に残った。以前は一面にリンドウの花が咲いていたという緑豊かな草地を、盛り土で覆ってしまったのだから、侵入者としてのわたしの方がむしろ罪が重い。次から次へとトラックがやってきて、草地が土の山で埋められていくのを眺めながら、たしかに躊躇いを感じないではなかった。本格的な霜の季節の寒さと、寝泊まり小屋をなんとか形にした喜びで、狐に対するわたしの罪悪感はすぐに打ち消されてしまったけれども。
近所の家々を眺めていると、あそこには日常があって、わたしのところには日常がないと感じることがある。必要に迫られた幾つかのことを追いかけているうちにその日が終わり、変わりやすい天気や、朝晩の気温の変化などと向き合う日々を重ねているうちに、いつのまにか季節が移っていく。家の形というのは、日常生活がそこにある証明みたいなものかも知れない。テントの薄い生地一枚だと日常生活を囲いきれず、漏れてしまうのだろうか。わたしのテント暮らしはどちらかというと、分譲地の住人たちの家よりも、木の上の小鳥のねぐらや、枯れ草の中のネズミの寝床により近かったような気がする。雨になりそうな気配を感じると、大慌てで道具を片付けシートの覆いをかける。片付け終わったとたんに雨が降り出すという芸当もできるようになり、誰かに向かって自慢したくなるような、つまらない満足感を味わうこともあった。
テント暮らしは一年で卒業したものの、7年目になる現在も諸般の事情により、まだ母屋の建たない不便な小屋暮らしを続けている。そのあいだに最初の意気込みが徐々に変化して、分譲地の中の家々に伍するような、そこそこまっとうな家を一目散に目指しているとはいえない感じになっている。家づくりが遅々として進まないあいだに、暮らしの方が先に育ってしまったようなのだ。
それにしても、家づくりを開始した一年目は特別に風が強かった。わたしのところは風の通り道になっているらしく、常設した大型のテントがばたばたと煽られて、いまにも飛ばされそうになる。しかも、強風の日が何日も続く。張り綱が切れるか、支柱が折れるか、テントごと飛ばされるか不安で仕方がない。
それで急遽、風よけのための囲いをつくることにした。もったいないと思ったが、寝泊まり小屋のために仕入れた貴重な角材を掘っ立て柱に流用して、そこに野地板を胸の高さほどに打ち付ける。テントのペグの位置に合わせて柱を立てたので、囲いの形はいびつだし、野地板もあとで剥がして使えるように、端を切りそろえないでなるべく長いまま使った。突きつけに張った板は乾くと隙間だらけになるけれども、風が弱まってくれればそれでよかった。秋に寝泊まり小屋ができあがったら、どうせ撤去される運命なのだから。
ところが、この囲いがまるで役に立たない。相変わらずテントは煽られ、ぎしぎしと支柱がきしむ。なんとかしたいが、ちゃんとしたものに作り直すほどの建造物ではないし、かといって壊してしまうのもなんだかもったいない。
結局、テントを撤去して、かわりに自動カンナ盤を囲いの中に持ち込み、作業空間として利用することにした。風の強い日に盛り土の上で自動カンナ盤を使うと、鉋屑が隣地まで飛ばされていって、掃除をするのが大変だった。雑草だらけの空き地とはいえ、知らんぷりをするわけにもいかない。カンナ屑が囲いの中で止まってくれると、片付けるのが楽になる。そんなわけで寝泊まりは、囲いの外に張り直した、風に強い小さなテントの中ですることになった。
このときにいったん机に戻って、年間計画をじっくり練り直すべきだったかも知れない。新しく何かを作ることと、作ったものを壊して無にすることは、まったく性質の違う作業になる。精神の健康のためには、どうせ壊すのだから、などと考えてはいけなかったようだ。前だけを向いて、前にだけ進む。
立ち止まって想を練るのは、じつは、頭の調子がよくないわたしにはどうも苦手だ。40歳のときにトラックに撥ねられて以来、不自由になっている心身の問題が幾つかある。不完全な想のまま体を動かして形をつくり、その形を眺めて次の不十分な想を描き、また体を動かすというのが、いつのまにかわたしの方法になっていた。できないことはできない。できない人にはできない。わたしの中でこのことはずっと葛藤であり続けているのだけれども、同時に、徒に悲観する必要のない、むしろそちらの方向に前向きになっていい可能性にも見えているようだ。
珍しく風のない、穏やかに晴れた日だった。囲いの中でコンビニの弁当を食べていると、カラスが飛んできて、掘っ立て柱の上に止まった。すぐ目と鼻の先だ。何メートルもない。当然、弁当が狙いだろうと思って、唐揚げをひとつ箸でつまんで地面に投げてあげた。カラスに意地悪すると仕返しされるという話が頭をよぎった。追い払うのがちょっと怖かったのかも知れない。まぢかで見ると、黒光りした羽根と、太くてがっしりした嘴がなかなかの迫力だ。
すぐにでも唐揚げを咥えて、飛んで行ってしまうだろうと思ったのだが、カラスは動かない。悠然としていて、うっすら笑みを浮かべているようにさえ見える。おそらく、鋭い眼光くらいは走らせただろう。でも、唐揚げに気持を動かされた気配は、わたしには少しも見てとれなかった。
カラスと根気よく気持のやりとりをする余裕が、このときのわたしにはなかったようだ。朝早くから暗くなるまでの力仕事に体がまだ慣れていなかったし、朝晩の寒さともいちいち対峙する感じだ。近所の人が半袖姿でふらっとやってきても、わたしはジャンパーを着込んでいる。東京で痛めた手指の関節がしくしくするので、バケツに温泉のお湯をためてときどき手を温める。手術した膝に、脚立の上り下りがこたえる。意気込みで紛れているとはいえ、この先のことも不安がないとはいえない。変な話かも知れないが、これから建てようとしている家が徐々に形になって通りすがりの人たちの目に触れることを想像すると、なんだか気持が臆してしまう。舞台の上で家を建てているような恥ずかしさを感じるのだった。
カラスを無視して黙々と弁当を食べ続けていると、羽根を打つ音がして、見ると、カラスが飛び立とうとしている。来たときと同じように突然、どこかへ飛んで行ってしまった。唐揚げに興味がなかったはずはない。わたしの目の前では手を出しづらかったのだろう。おそらく、あとでこっそり戻って食べるつもりに違いない。そう思ったけれども、仕事の邪魔になるので、弁当の容器と一緒に唐揚げも捨ててしまった。戻ってきたときにカラスはきっとわたしに騙されたと思うだろうな、気が変わりやすい奴だと思うだろうな、などと考えながら。
カラスと至近距離で向き合ったのは、それが最初で最後だった。もしかしたら、カラスの真の狙いは弁当ではなくて、わたしという新参者を観察することにあったのかも知れない。餌が目当てなら、離れた場所から様子を窺って、わたしが現場を離れた隙にかすめて行くとか、もっと巧妙に立ち回る方法があったような気がする。わたしが危険な存在か、害の無い存在か、仲間たちを代表して下調べに来たということも考えられる。隣りのおじさんの話では、近所のカラスは4羽で、みな兄弟なのだそうだ。
しかしここ来てまず真っ先に目に入ったのは、空をばりばりと雷のような音をたてて落下してくる鳥だった。子供のころ、故郷の空で同じ鳥を見たことがあった。50年も経って、あの鳥にまた巡り会えるなんて思ってもみなかった。家の裏の広大なキャベツ畑に、モンシロチョウの群れが舞い、雲雀が畑と青空のあいだを昇ったり降りたりしている時代だった。夕焼け空をカラスの大群が裏山に帰って行き、軒先のあちこちにオニグモの大きな巣がかかっていた。あらゆる光景が、少年のわたしの目に新鮮に映っていた。なかでもその鳥は、生まれて10年足らずの少年のわたしを特別に驚かせるものだった。
どこか知らない遠くからやってきて、短い夏のあいだ、けたたましい羽音をたてて高い空を飛び回り、秋になるといつのまにかどこかへ行ってしまう。わたしの記憶では、その鳥は一羽で、本物の雷のようにばりばりと音をたてて、空を裂くように落下してくるのだった。
ここでは、あの鳥が何羽もいて、昔に比べると小柄になったように見える。空を引き裂く音も昔の印象よりはずっと穏やかだ。でも間違いなくあの鳥だった。ここにまだ、わたしの少年時代が消えずに残っている。懐かしい感じがした。同時に、あらためてわたしの少年時代を失おうとしているような、せつない気持もこみあげた。
故郷の町にいたのは18歳のときまでだが、その鳥の記憶はなぜか少年時代に限られている。環境の変化かなにかで、故郷からその鳥がいなくなったか、高校に進んで内面に沈潜してしまったわたしが、滅多に空を見上げなくなってしまったか、とにかくなんという名前の鳥なのか知ることもないまま、高校を卒業すると同時にわたしは故郷を離れたのだった。
調べてみると、その鳥の名はオオジシギというらしい。通称カミナリシギとあるから間違いないだろう。春に、はるばるオーストラリアから飛んできて、恋人を見つけ、子育てをして、夏が終わるころにまたオーストラリアまで8000キロの旅をして帰っていくという。一日中空を飛び回ることなど、なんでもないのかも知れない。
北海道の夏は、じりじりと炙られるようだ。実際の気温以上に暑く感じるのは、空気がきれいなせいではないかと思う。おそらく紫外線を遮る塵の層が薄いのだろう。太陽に炙られ、カミナリシギのけたたましを羽音を頭から浴びながら、土運びなどの仕事をしていると、暑さが何倍にも感じられる。夜中に空を飛び回るカミナリシギの羽音で目を覚ますこともある。夏のあいだ、一日のうちのどの時間にも、空にカミナリシギがいる。カミナリシギが滞在しているあいだ、その羽音と鳴き声から逃れることは難しい。電信柱に止まってひと休みしているように見えるときも、ずうちくずうちく金属的な鳴き声だけは止むことがない。草むらに降りているのを見かけることがあるのは、図鑑の説明によると、その長い嘴でミミズなどを食べているようだ。
三年目、雨が降り続いて気温の低い夏になった。さすがのカミナリシギも元気がなくて、鳴き声も弱々しく、電柱の上の姿も凍えているようで痛々しく見えた。
その翌年、カミナリシギの姿を近くでほとんど見かけなかった。前の夏の寒さで伴侶を見つけられなかったか、子育てに失敗したか、オーストラリアまで帰れなかったか、とにかくなにか尋常でない事態が生じたのだと思う。
この地では、何年も大丈夫だった木が突然枯れたりすることがよくある。わたしのところでも、ホームセンターで買ったプルーンの木と、隣りのおじさんにもらった銀ドロの木が、植えて数年後に枯れてしまった。飢えた野ねずみに根を囓じられたり、ハスカップやプラムの芽を鹿に食べられて全滅したという話も聞く。植物も動物も、厳しい寒さとぎりぎりのところで戦っている。あんなにタフに見えるカミナリシギも、毎年同じように生きられるわけではないのだろう。
季節の変化とともに目を楽しませてくれるいろいろな動物たちも、のどかで平和な暮らしをしているとは言えないようだ。巣立った5羽の雛たちが、小屋の屋根をぱたぱた走り回って飛ぶ練習をしていたセキレイも、無事に子供を育てられたのはこれまでに二度だけで、あとは、なにものかに巣を壊されたり、親の羽が散らばっていたり、卵だけが巣のなかに残されていたり、順調でないときの方が多い。卵を抱くのに疲れたらしいセキレイが材木の上に出てきて、片方の羽根と片方の脚を交互に伸ばして骨休みをしている姿を目にすると、思わずカラスが近くにいないか見回してしまう。雀の巣も、うっかり安易な場所に作ると、雛が大きくなった頃を狙っているとしか思えないカラスに一斉に襲撃される。
動物たちを眺めながら暮らしていると、一年は長いと感じる。テント生活から始まって小屋生活にまで辿り着いたものの、母屋がなかなか建たない暮らしを続けているあいだに、一年ごと全力で生き抜いている動物たちの姿が少しずつ見えてきた。わたしも、順調な生活にばかり照準を合わせようとしないで、日々変化する自分にもっと注意深く目を向けて生きていく必要があるようだ。