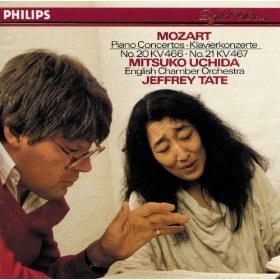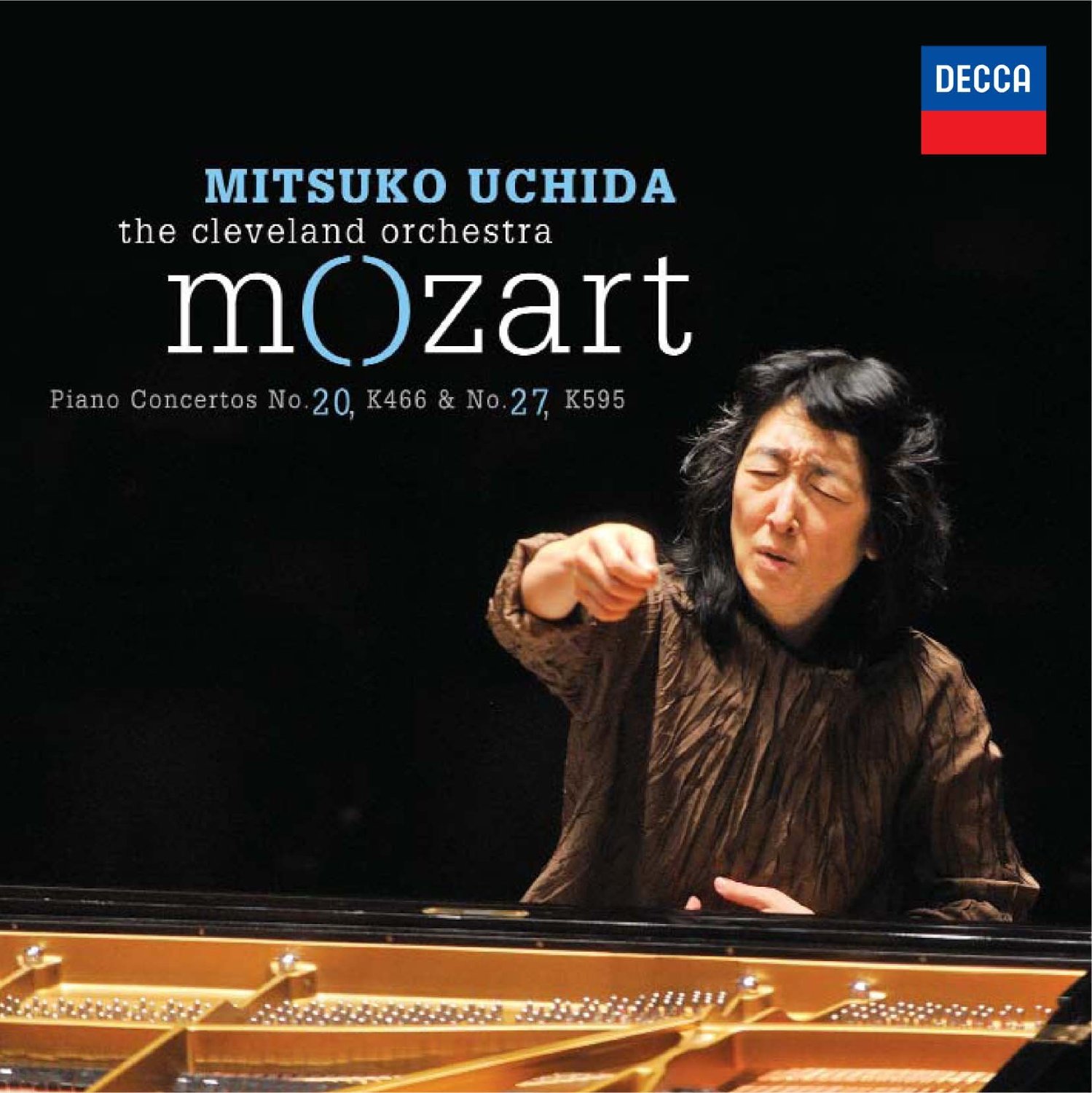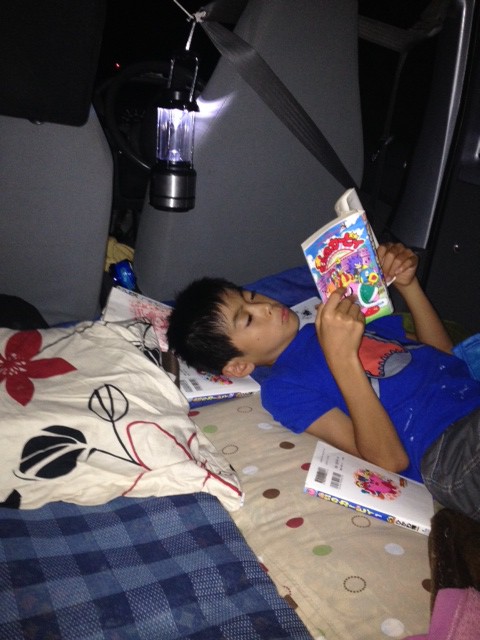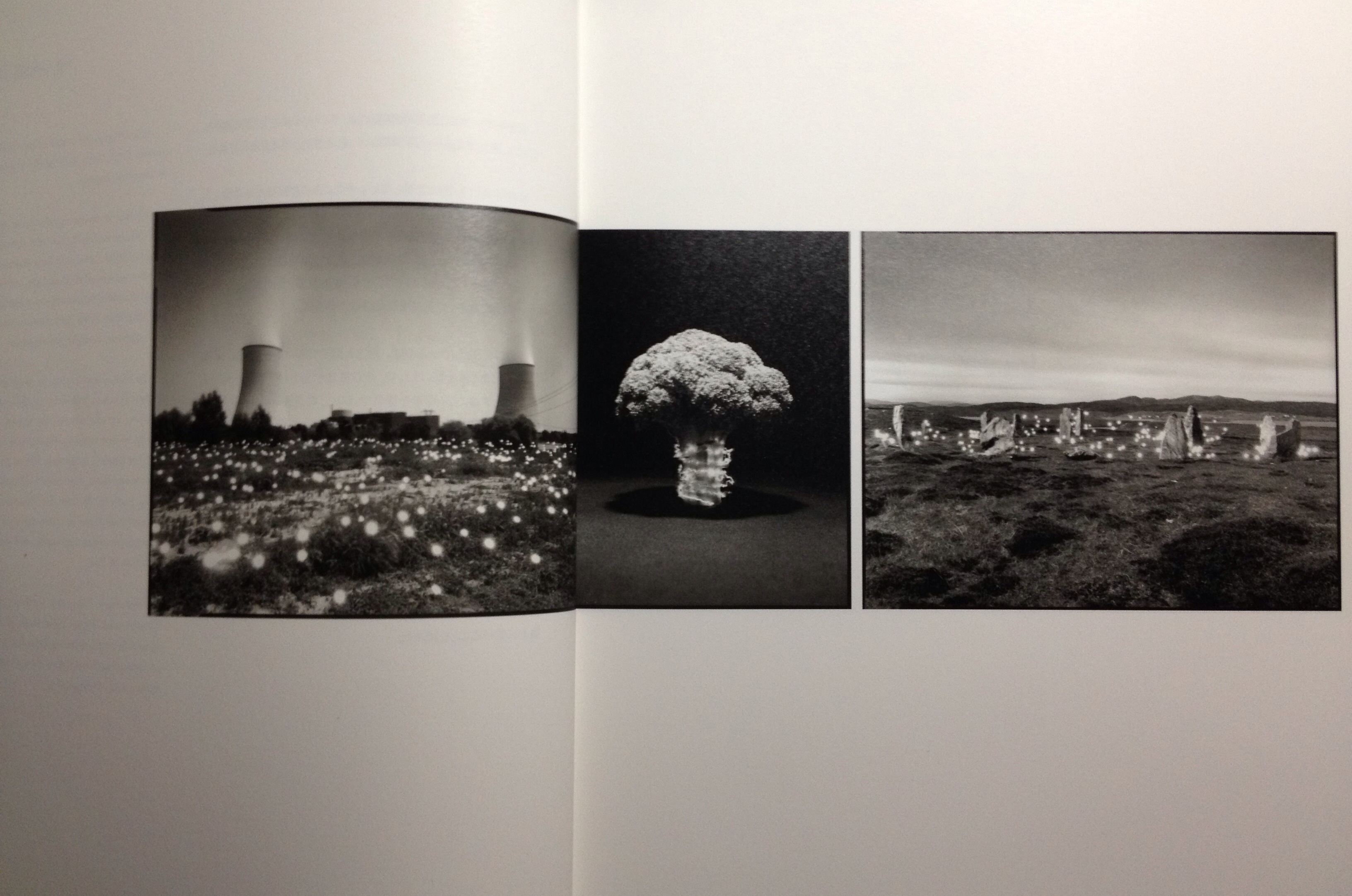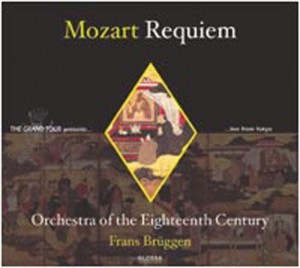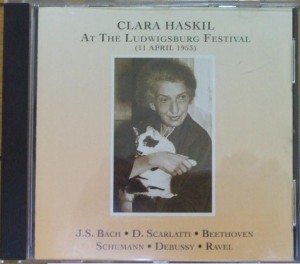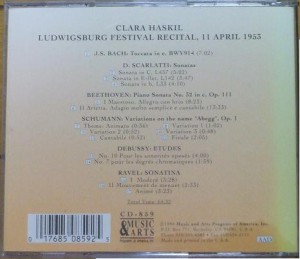根石吉久

サツマイモ予定地
ブラウザに公開される「ページ」というのが、フェイスブック上に作れるらしいと分かり、一つ作っているうちに二つできてしまったのが二年ほど前のことだった。片方を、語学論と称してきたものを掲載するのに使うつもりだったが、井上陽水の my house のURLなどを貼り付けて遊んで、放置してしまった。もう片方は、使い途が思いつかなかったので、そっちもそのままにしてしまった。
今年、畑に出たのは二月の終わり頃だっただろうか。アイフォンで写真を撮って、畑からフェイスブックに送ってみた。アイフォンでは文章が書きにくいので、写真だけ送っておき、夜、英語の仕事が終わってから、ビールを飲みながら短い文章を書くことが多かった。ごく短いコメントは、畑でアイフォンで書くこともしたし、畑から帰る途中、コンビニの駐車場に車を駐め、コーヒーを飲みながら書くこともあった。
畑でサツマイモを作り、去年作った石釜で焼き芋を焼き、焼き芋屋になることを予定しているとフェイスブックに書いたら、山下徹さんが、今年の秋、焼き芋を買いに行くつもりだと書き込んでくださった。神戸から長野まで、焼き芋を買いに来てくださるというのである。山下さんが、私の焼き芋屋の最初のお客様になるのだろう。
何年か前、サツマイモを作り焼き芋を焼いたことはある。その時は、ドラムカンを改造した窯で作ったが、焼き芋はうまくできた。
そのとき芋を作った畑と今年は畑が違う。今年、サツマイモを植える予定のところは、ずっと草を生やして放置しておいたところであり、草の根が土の中にびっしりと広がっている。耕さずに、ノコギリ鎌で草の根を切るだけで、サツマイモの苗を植えるつもりでいたが、少しは鍬を入れないと駄目だろうか。あのままでは、草の根に縛られたようになり、芋がふくらむ場所がないのではないか。
前に遊んだ時とは、窯も違うし、畑も違う。畑が違うからできる芋も違うはずだ。焼き具合も違うはずだ。どうなるだろうか。
その後、山下さんはフェイスブックの違う写真にコメントして下さり、秋、奥様も同行する予定だと書かれた。ううむ。お二人で来られて、しかも、うまく芋ができてなかったら、芋を買ってきて焼いて、ごめんなさいと言うしかないなと思ったが、問題はそれだけではない。山下さんは、奥様に農業指導をして欲しいと書かれていたのだ。
考え込んでしまった。
考え込むと言っても、どうせ私のことだから、30秒ほど考え込むことをしただけなのだが、その後、畑にいて、喉に魚の骨がひっかかったようなこころの状態になっていた。気になって何度も思い出すのである。農業指導かあ、と思うのである。
俺はいったい何をしてきたのか、と思うのである。
実に様々なことをしてきた。一貫していたのは、農薬・化学肥料を使わないということだけで、その他に一貫していたことは思いつかない。土手草を使ったり、キノコ栽培後の廃菌床を使ったり、30センチもスコップで掘って廃菌床を敷き詰めてみたり、土手草を畝の上に敷き詰めてみたり、最近では、畑の通路の草を刈り、天気がよければ一日か二日、天日で乾かして草の干物を作り、それを5センチ、10センチ程度に浅く埋めて土とまぶしたり、とにかくいろいろやってきた。
その時々で、手応えがあると人に話したりもした。こうやるとこうなるということを話して、人様がそのやり方を採用してくれ、試してみてくれることもあった。そのことで、その人に迷惑をかけたかもしれない。
例えば、川口由一の方法を試したときだが、「草は刈ってその場に置く」ということを試したのだった。川口はその方法は「誰にでもできる」と言うのだが、とんでもないことだった。確かに「刈ってその場に置く」というだけのことなら、「誰にでもできる」。刈ればいいのだし、その場に置けばいいのだから、ぎっくり腰をやっているとか、体が動かせないとかでなければ、私にもできる。しかし、このやり方は、いつも注意深く畑を見ていなければならない。草によっては、新しく出てきた芽が、刈って置いたものを持ち上げてしまって、枯れ草の下がスカスカになったりする。草が土に触れていなければ、雨が降ってやんでも、すぐに乾いてしまう。そうなれば、草はなかなか土になっていかない。その場合には、伸びてきた新しい芽をもう一度刈るようなことをして草を弱らせ、刈られて枯れた草が土に接しているか、土にごく近いところにあるように直さなければならない。手間がかかる。
「刈ってその場に置く」という行為自体は「誰にでもできる」が、絶えず畑を見ていて、細かく手を入れていくことは誰にでもできるわけではない。私の場合は、英語の練習用の教材を新しく作り始めたり、去年のように庭に石釜を作り始めたりしてしまうと、畑に行くことは激減する。それが、そのままこの方法の失敗につながっていった。一言で言えば、専業で「草は刈ってその場に置く」のでなければ、まずほとんど失敗する。
部分的なことを人に話しても、うまくいくとは限らない。
しかし、部分的なことだけ聞いて、それを試してみてくれた人はいて、その人の元でも、私の失敗と同じことが起こった。つまり、ただ単に畑が草ぼうぼうになったということである。草を刈って、その場に置いて、その場で草を育てているだけになったのである。作業全体の中には、どれだけ畑に時間が使えるかということも含まれている。川口はそのことには触れず、「誰にでもできる」と言っている。だから、「とんでもない」なのである。
川口の方法の後、ネットで知ったのは炭素循環農法と言われているやつである。炭素循環農法でキノコの廃菌床を使う場合は、菌床に糸状菌がまだ生きているうちに畑の土の浅いところに混ぜる。
山にある腐葉土などをひっくり返してみると、枯れた小枝などが湿り、白い糸のような菌が枝に沿って伸びているのが見えることがある。この白い糸のようなものが糸状菌なのだが、キノコ栽培後の廃菌床の糸状菌を生きたまま土に混ぜ込むのは難しい。
キノコの栽培工場と打ち合わせをして、廃菌床が出る日に一挙に畑に混ぜなければ、「生きたまま」の糸状菌を使うことはできない。野積みにすれば、糸状菌は発酵熱で死んでしまうのだ。それに、キノコの栽培工場から出たばかりの廃菌床を、その日のうちに土に混ぜ込むには、私の方で浅耕できる中型以上の耕耘機を持っていなければできないが、私は持っていない。少しだけ試してみて、廃菌床を使うことはあきらめた。
炭素循環農法のもう一つの資材は、畑やその周りに生える草である。川口由一の「刈ってその場に置く」でも、草は使ってきたので、草を干物にして土に浅く埋める方法でやってみることにした。
なぜかわからないが、川口の「刈ってその場に置く」だと、ドバミミズが殖える。雨上がりなどに、土の中から出て這っていたミミズが、急に太陽に照らされ、土の下に逃げ遅れて死んでいるのを見ることがある。場合によっては20センチもあるような大型のミミズである。この辺ではドバミミズと呼んでいる。鯉釣りの餌に使える。
単にミミズと呼んでいるのは短いやつだ。シマミミズも縞のないやつもひっくるめてミミズと言っている。大きくても5センチ程度、鮒釣りなどに使うのは、3,4センチ程度のもので、堆肥の裾などに棲んでいる。最近では堆肥の山を見なくなったので、ミミズもあまり見なくなった。
ミミズは、有機物がよくこなれていない土、土を掘れば土が腐敗に傾いていて、土が臭いようなところにいる。
炭素循環農法では、「ミミズのいるような土はよくない土だ」と言っている。ここで言う「ミミズ」が、この辺で単にミミズと言っている短いミミズなら、それはその通りなのだが、ドバミミズのいる畑の土は臭わない。ドバミミズは、有機物がこなれて、浄化され、清浄になった土にいる。
有機物は積み上げると腐敗しやすい。だから堆肥の裾にはミミズがいるのだ。これが、炭素循環農法がけなしている「よくない土」だ。それはその通りだが、炭素循環農法は、ドバミミズのいる土のことがわかっていない。ブラジル生まれの農法のせいなのかどうかはわからない。
草などを浅く散らし、絶えず土に直射日光が当たらないようにする場合は、草と土の接するところで、腐敗の過程が生じないまま、草は土に変わっていく。発酵熱も出ない。これが、川口由一の方法がうまくいった場合に起こることだ。これだと、ミミズはいなくなり、ドバミミズが急激に増える。釣りの餌に欲しいときは、畝の草を刈る。ドバミミズは草が刈られる音が嫌いなのか、草の根の震動が土を震わせるのが嫌いなのか、土から出てきて人の目に見えるところを這う。やたら体をくねらせているので、あわてているのがわかる。ちょっと草を刈れば、簡単にいくつも拾えるくらいに出てくる。こういうふうになった土はいい土だ。変な臭いはまったくしないし、林の中にいるときのようなにおいがかすかにする。野菜も育ちさえすればうまい。
だから川口由一の方法はいいのである。いいのであるが、手間が馬鹿にならないのである。手間まで含めて、「誰にでもできる」と言っているのではないのである。くどいようだが。
川口の方法を試しているとき、女房をどやしつけたことがあった。女房が通路の草を根こそぎ抜いたから、どやしつけたのだ。「草は刈ってその場に置く」ということを試しているときだったし、それを試しているのだと女房に伝えてあったにもかかわらず、草を根こそぎにしたからどやしつけたのである。それをやられたのでは、実験ができない。
うちの女房は大変強情で、伝えるべきことを伝えてあっても、それを無視して、勝手に自分のやりたいようにやる。別に百姓仕事に限ったことではない。相手が考えていることを「汲む」ということをしないのだ。あるいは、表面的な論理しか「汲む」ことができないのだ。「草は刈ってその場に置く」はきわめて表面的な論理だが、その時は、それさえ汲まなかった。無視した。だからどやしつけた。
どやしつけたあたりから、女房は畑を手伝うことはしなくなった。今では、私が一人でやっている。
炭素循環農法は、草を「置く」のではなく、「混ぜる」。これは別に独自性を主張できるほどのことではない。農薬や化学肥料が普及するまでは、どこででもやっていたことだ。独自性を主張できるとすれば、草を刈って少し放置し、干物にすることと、その干物を土の浅いところに埋めるのだと言い、「浅いところ」を強調したことだ。
「干物」という言い方は、私が勝手に言っているのであり、炭素循環農法では「秋のもの」と言っている。
春や夏に刈った草も、日干しにして枯れてきたものは「秋のもの」だと言っている。炭素循環農法を広めるためにネットのユーチューブによく出てくる人は、最近の日本人は、「秋のもの」という言い方で言っていることが伝わらないとぼやいている。枯れ葉や枯れ草の「枯れた状態」のことを「秋のもの」と言っているのだが、そんなふうに情緒的に言う必要はない。春に刈って乾かしたものは「春のもの」だし、夏に刈って乾かしたものは「夏のもの」だ。どっちも「干物」だと言えばいいことだ。
今やっているのは、炭素循環農法から得たヒントにもとづいている。しかし、去年の半年ほど、つまり春から秋まで、石釜を作っていたので、畑に通えなかった。そのせいか、野菜がまずい。サラダで食べられるはずの葉物野菜が渋みが強すぎてまずい。これじゃあ駄目でしょ、と思った。
川口由一の方法とまったく両立しないものは、今年の3月半ば頃から着手したポリエチレンの黒マルチの使用である。ビニールやポリエチレンを使った農法を、長年にわたってしゃらくさいものとして眺めていたので、ポリエチレンのマルチをするのは、私としては、完全な敗北である。これが完全な敗北であることは、別の原稿に書いた。
黒マルチは炭素循環農法とは両立する。ユーチューブで講釈する人は、草を「秋のもの」にして、土の浅いところに埋めるということだけしゃべっているのだと思っていたが、マルチをすれば「もっといい」と言っているのをたまたま聞いた。
ちょっと待てよ。マルチは、土と空気を遮断する。そのことで棲みつく微生物はまるで違ってくるはずではないのか。「もっといい」程度の違いで済むのか。嫌気条件を作って、「もっといい」などというのなら、これまでどうして草の干物を土の浅いところに埋めると言ってきたのだ。土の浅いところとは、好気性の微生物が活動する場所ということではないのか。そういうことも気になったが、炭素循環農法はポリエチレンやビニールを使うことは気にしないのだなと思った。
近所にゴミの溶融炉が建設予定だと聞き、自分で持っていた印刷機でビラを刷り、バイクで一軒ずつ村や町の家の郵便受けにビラを配って歩いたことがある。塾に英語を習いに来る生徒が激減した。
ビラにプラスチックを燃やすなということを書いたこともあり、プラスチックやビニールやポリエチレンの「使用後の行き先」「使用後の処理法」が気になるようになった。炭素循環農法は、そんなことは気にしない。
私は、破れたポリエチレンのマルチは、新しいポリエチレンの袋に入れ、畑の通路に浅く埋めようと考えている。草が生えにくくする用途になら長く使える。今のところ、それ以外の使い途は思いつかない。土で汚れたポリエチレンを行政に渡そうが、農協に渡そうが、どうせ焼却するか溶融するかどっちかだと思っているから、行政にも農協にも渡す気はない。
どうにも気になるのが、今年の野菜がまずいということだ。去年一年、畑に通う日が少なかっただけで、こんなにまずくなるのかというくらいにまずい。畑に毎日のように出られなくても、たまには草の干物を土に入れていた。しかし、入れっぱなしで、一月後くらいに土と混ぜ、有機物と土がよく接触するようにする作業はさぼった。渋みはそのせいではないかと推測している。土はなまものだとか、土は生き物だという言い方は、近代科学からは違うと言われるだろう。近代科学以後では、土は肥料分を含む細かい鉱物に過ぎないのだ。しかし、その言い方は科学的に正確であるだけだ。
川口の方法でやるとドバミミズが急激に増えるというようなまったく別の信号を受け取っている場合には、土は生き物だという言い方は非常に正確な言い方だと思う。
黒マルチの他に今年始めたことは、えひめaiというものを使うことである。
以前、EMがはやったことがあるが、微生物や酵素のブレンドを作ることでは、えひめaiもEMも似たような考えにもとづいている。
EMは「有用微生物」の英語の頭文字だが、要するに自然界にいる微生物の中から優等生を集めブレンドしたものである。えひめaiとブレンド具合がどんなふうに違うのかはわからない。というのは、EMは製法が閉じられていて、EM菌というものを消費者が買わなければいけないようになっているからだ。製法が非公開で、その利権を世界救世教が買ったというような噂を聞いた。
えひめaiは、製法が公開されている。
えひめaiで使うのは、イースト菌、納豆、ヨーグルト、砂糖である。これらを一定の割合で混ぜ、35度の熱で24時間、急激に繁殖させる。イーストや枯草菌や乳酸菌が砂糖を餌に繁殖し、酵素やアルコール(微生物の糞)を作り出し、酵素やアルコールが、土中の微生物のうち有機物を発酵させる性質のものを活性化させるのだろうと考えている。
えひめaiの作り方は、ネットで「えひめai」を検索すれば出てくる。えひめaiの元になっているのは、スーパーで買えるような「微生物の優等生」だが、優等生は自然界にただ置かれると弱いものだ。微生物のまま土に混ぜても、おそらく自然界の微生物の餌になるだけだろう。だから、35度の熱で24時間繁殖させるようなプロセスは人工的に行わなければならない。
えひめaiを作ることは、発酵菌を繁殖させ、腐敗菌を抑えるような性質の酵素を作ることだろうと推測している。
黒マルチの下に、ジョウゴで月に一度くらい注入してみようと思っているが、今年の野菜の味の悪さはどうなるだろうか。良くなってくれ。今年の野菜はうまくない。つまり、まずい。
農薬や化学肥料を使わないことの他に、もうひとつ一貫していたことがあると気づいた。土が良くなるのか、悪くなるのかにはいつも興味があったが、収穫できるかどうかにはほとんど興味がなかったということが一貫していた。だから、土や草をいじっているだけで、なんにも穫れないことがあっても、それはそれほど気にならなかった。
百姓をするのは、野菜を「穫る」ことが目的だろう、と言われてもピンと来ない。「穫る」ことにやぶさかではないが、そんなに興味がないのである。それよりも、畝の草を刈るとドバミミズがどんどん這いだしてくるとか、草の干物を埋めようとして、土を浅くどかすとき、以前に埋めた草のせいで土がほっこり軟らかくなっているとか、土をどかすのに力が要らなくなっているということの方がずっと面白かったのだ。台所から出る生ごみを畑に持って行き、以前に生ごみと土を混ぜておいた山を割って、新しくて臭い生ごみをおしあけ、鍬で混ぜる。その時、えひめaiの数百倍液の水をかけてやると、生ごみのいやな臭いが消える。そういうことも面白かった。完全に腐敗の方向をたどり始めている有機物を、発酵の方向へ瞬時に転換させていることが、人間の嗅覚でもわかるのだ。
私は、広い意味でなら、発酵マニアの一人なのかもしれない。
発酵マニアの遊びであり、百姓仕事でも農業でもない。そういうふうに書いてみると、なんか、自分で、納得できる。自分がそういう者なので、山下さんの奥様に「農業講座」(徹さんの言葉だったと思う)はできないのだということがわかる。それを明らかにすることができれば、喉に骨がひっかかったようなこころの状態は、直るのではないか。
なにしろ、収穫を邪魔扱いしないまでも、目的とはしていないので、家族からは馬鹿にされっぱなしである。収穫するというだけのことなら、私よりも女房の方が上手なくらいだ。だから、女房は私を堂々と馬鹿にする。土佐のハチキンにつける薬はない。
こうしたらこうなったと言うことは、手間が許すかぎりなるべく公開していくつもりだが、同じようにやってみてわかったことは、やってみた方が公開して欲しい。私も参考にしたい。
自分が何をして来たのかということが、少しはっきりした。書いてみないと、はっきりしてこないものというものはあるものだ。
■フェイスブック「素読舎」