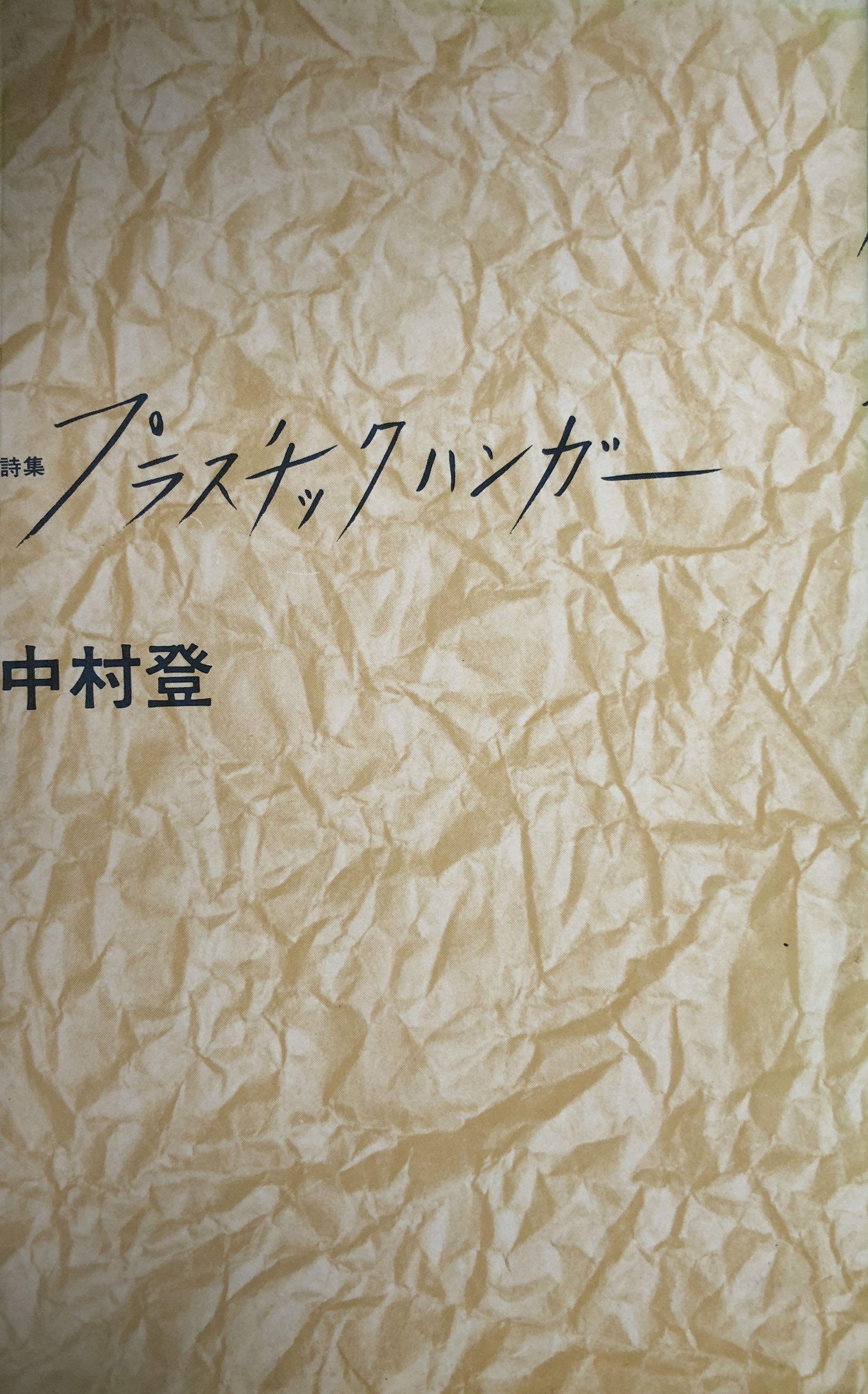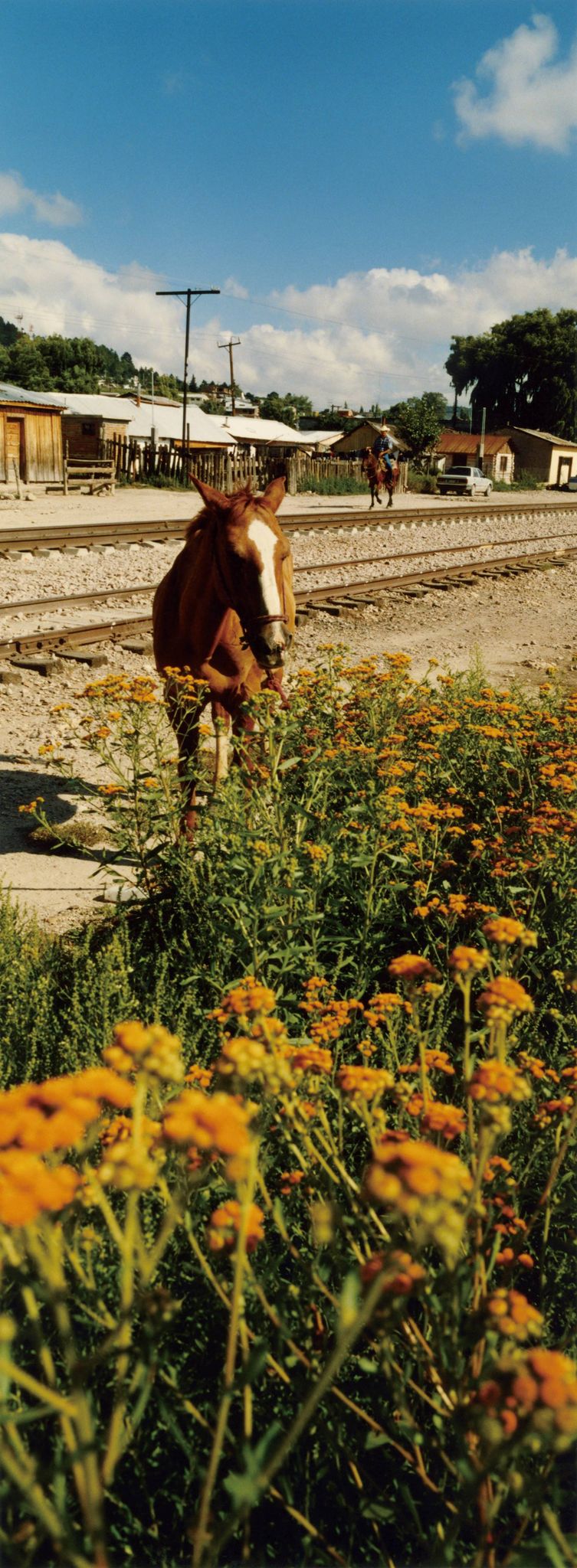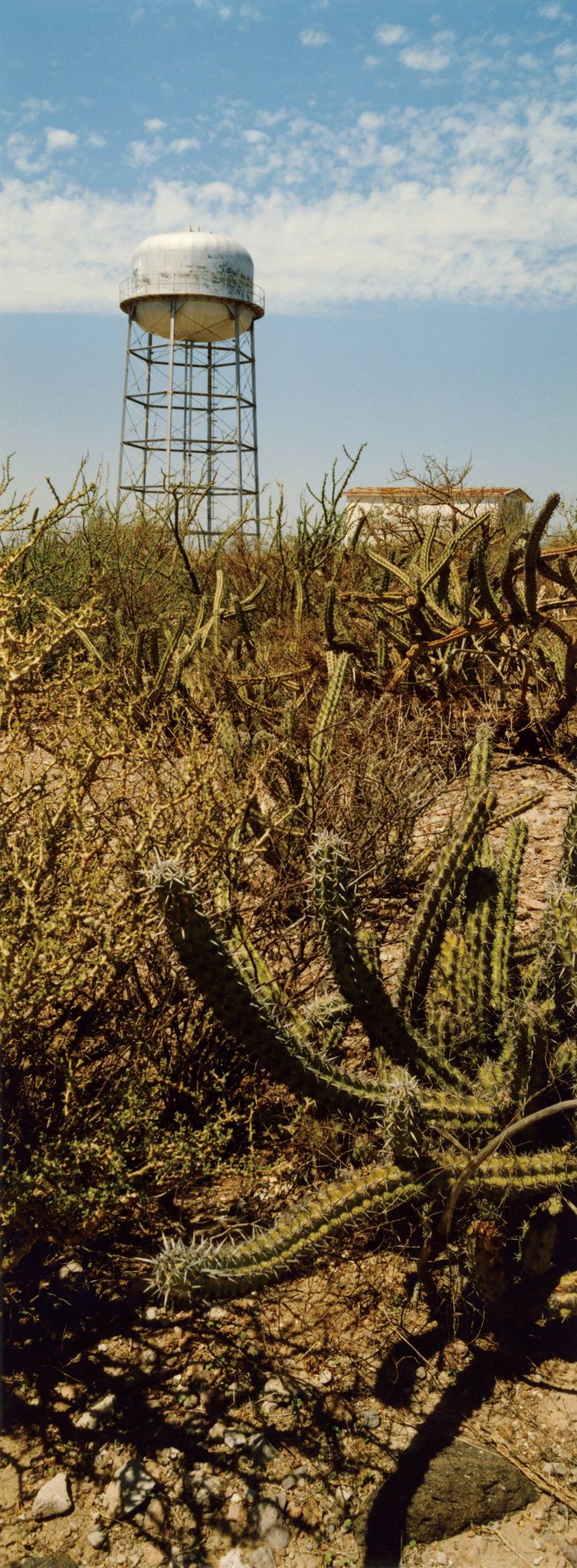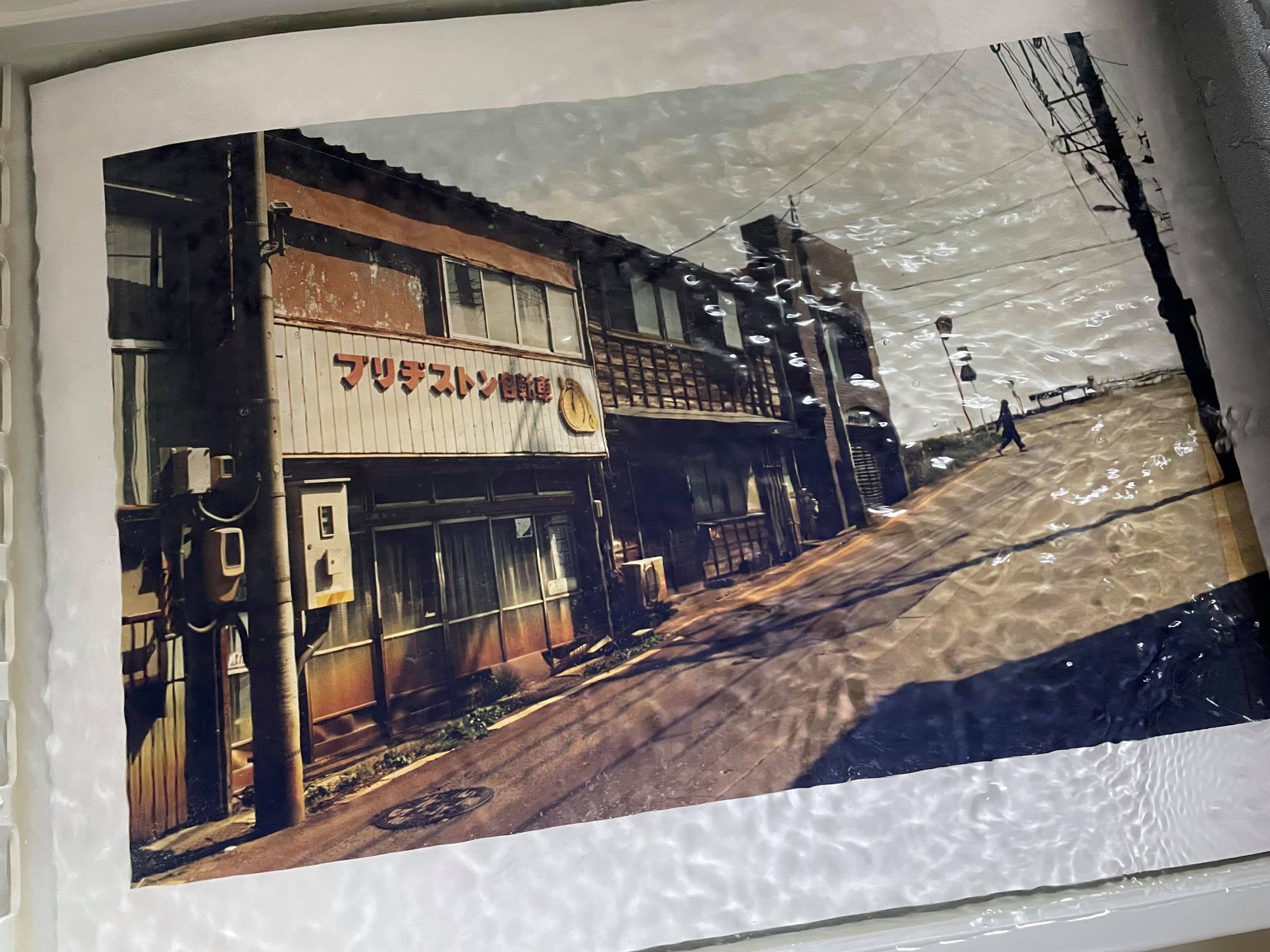今井義行
プロローグ
詩は、それまでの、或いは現在の、作者の体験から生まれてくるものだと思うけれど、そして、それは概ね作者の読書体験であることが多いように思うけれど。わたしも或る程度は読書体験はしてきたものの、わたしは読書がどうにも苦手なので、その内容は殆ど忘れてしまった。
それでは、わたしが何から影響を受けてきたのかというと小学生から現在に至るまでの、洋楽鑑賞だと思う。ただし、わたしは洋楽鑑賞マニアではないので、有名なミュージシャンについてしか語ることはできない。それでも、「書けば、形になる。」と信じてエッセイとして、書き残しておくことにした。(登場するミュージシャンの名前は順不同。また、わたしの記憶に基づいた記述であるため、間違いがあるかもしれない。)
● ローリング・ストーンズについて。
言わずと知れたビートルズと並ぶイギリス出身のバンド。だけれど、ブルース・ベースの曲が、あまりにもキャッチーでないため高校生まで、その良さが殆ど分からなかった。
ところがなぜか大学生になってから、そのグニャグニャしたグルーヴに、すっかり飲み込まれてしまった。
アルバムは1960年代末からの「レット・イット・ブリード」から1976年の「女たち」までは名盤続きで、1枚に絞り込むなどできない。
ちなみに有名な「スタート・ミー・アップ」を含む1980年の「刺青の男」は、過去に録音した曲の寄せ集めであるため、かなり大味で名盤とは言えない。
ところで、ギタリストにミック・テイラーが在籍していた時代が、ローリング・ストーンズの最盛期だったことはよく言われることだ。ミック・テイラーが脱退した後、誰が後任になるかについてジェフ・ベックという噂が出た。ジェフ・ベックを見かける度に「吐きそうになる」と言っていたキース・リチャーズの発言からして、さすがにそれはないだろうと思ってはいたが、まあ無事に後任ギタリストは人柄も穏やかだと言われるロン・ウッドに収まった。ロン・ウッドならバンド内の不和も和らげられるだろうから最適だと思った。
ところでバンドの最年長のチャーリー・ワッツは常々「ローリング・ストーンズは会社のようなもの。わたしはローリング・ストーンズの社員なんだよ。」と言っていた。そのチャーリー・ワッツがミック・ジャガーを激しく殴りつけたことがあるという。ミック・ジャガーがチャーリー・ワッツに向かって「俺のドラマー。」と言ったからだ。チャーリー・ワッツはミック・ジャガーの傲慢に向かって「2度とわたしのことを、俺のドラマーなんて呼ぶな。呼んだらタダじゃおかない!」と叫んだのだ。
もう10年に1度くらいしかオリジナル・アルバムをリリースしなくなってしまったローリング・ストーンズだけれど、現在ニュー・アルバムを制作中だと聞く。ローリング・ストーンズは、どこまで転がり続けるのだろう?わたしは、ローリング・ストーンズは解散などせずに、自然消滅していくような気がしている・・・。
● マイケル・ジャクソンについて。
マイケル・ジャクソンは、ソロ・アーティストして、群を抜いて大成功を治めたミュージシャンであると思う。わたしは、マイケル・ジャクソンが、本当に好きである。
1970年代後半に、「オズの魔法使い」が原作で、黒人キャストだけで制作された「ウィズ」というミュージカル映画があり、音楽監督はクインシー・ジョーンズだった。主役のドロシー役は、ちょっと歳の行き過ぎたダイアナ・ロスで、そして、かかし役がその頃10代後半だったマイケル・ジャクソンだった。
映画は、ブリキマンやライオンやかかしたちが踊りながら去っていく場面で終わるのだが、マイケル・ジャクソンが演じるかかしのダンスだけが突出していて驚かされたものだ。
多くの人たちが、クインシー・ジョーンズがマイケル・ジャクソンを見出したと思っているようだが、実際はその逆で、ソロ・アーティストとして低迷していたマイケル・ジャクソンが、クインシー・ジョーンズに「僕の音楽プロデューサーになってくれないか?」と持ちかけたのが、事の始まりだ。そこには、マイケル・ジャクソンの目利きぶりが、早くも、顕著によく現れている。
その後は、誰もが知っての通り、クインシー・ジョーンズがプロデュースした「オフ・ザ・ウォール」「スリラー」「バッド」という大ヒット・アルバムが続くが、わたしは、そのどれもが嫌いである。殊に世界で5000万枚を売り上げ、今でも売れ続けているという「スリラー」は、とても嫌いだ。
「スリラー」が大ヒットした1984年当時は、MTVが台頭してきた時代であり、視覚的に誰もがマイケル・ジャクソンを観られるようになっていた。マイケル・ジャクソンのパフォーマンスが神がかっていた事もあるが、また黒人アーティストとして初めて白人アーティストのエドワード・ヴァン・ヘイレンやポール・マッカートニーを起用した事もあるが、とにかく歌詞が幼稚過ぎた。それが5000万枚ものセールスを挙げたというのは、子どもから高齢者までが楽しめる音造りと内容だったからではないだろうか?
わたしがマイケル・ジャクソンを本当に天才だと思ったのは、マイケル・ジャクソンがクインシー・ジョーンズの手を離れて制作した「デンジャラス」からである。このアルバムでは、もの凄くお金をかけて錚々たるサウンド・クリエイターを掻き集めて制作された作品である事は明白だったが、そして並のミュージシャンだったならば、彼らの操り人形となってしまうところだが、マイケル・ジャクソンの場合は例外的にそのような事は超越していた。このアルバムでは、錚々たるサウンド・クリエイターと天才マイケル・ジャクソンとがぶつかり合う奇跡的な作品となっていた。
そして「デンジャラス・ツアー」の出来がまた素晴らし過ぎるものだった。人類にでき得る最高のものを創出したと言える。
ところで、マイケル・ジャクソンは、見れば明白だと言うのに、何故「自分は、整形などしてはいない」と否定し続けたのだろうか?人間誰しも老化していくというのにそれに徹底的に抗ったという事なのだろうか?天才のする行為は本当に不可解という他ないが、マイケル・ジャクソンの顔が段々と崩れていくのには揶揄されても仕方のないようなところもあった。
マイケル・ジャクソンが50歳を迎えたとき、マイケル・ジャクソンはロンドンのアリーナでコンサートをすると記者会見をして、「THIS IS IT!!(やるぞ!!)」と大きな意欲を見せた。ところが、その後、マイケル・ジャクソンは急逝してしまい、ロンドンでのアリーナ・コンサートは、無くなってしまった・・・マイケル・ジャクソンのこの死には諸説あるようだけれども、わたしは「暗殺」だと思っている。マイケル・ジャクソンを生かしておいてはならないという巨大な謎の勢力が、確かに存在していたに違いないと思うのだ。
●クイーンについて。
クイーンは、フレディ・マーキュリーのエイズによる45歳という若き死を以って神格化されたバンドだという評価が固まっているようだが、本当にそうなのだろうか?クイーンは確かに巧いバンドなのだが、リアル・タイムで中学生の頃からクイーンのアルバムを聴き続けていた者には、どうにも違和感がある。
クイーンの人気は日本から火がついたもので、クイーンのメンバーも大の日本びいきであり、またメンバーのルックスも良かったので、とにかく女子中学生の間で爆発的にアイドルとして人気が出た。当時のアイドル・ロック・バンドを中心に発行されていたミュージック・ライフの人気ランクでは常にクイーンの各メンバーが首位を独走していたのを覚えている。それ故、男子のロック・ファンからは、クイーンを聴いている奴らは情けないという事になってしまいわたしと妹は、密かにクイーンを聴いていた・・・
クイーンのアルバムでは、あまりにも有名な「ボヘミアン・ラプソディ」を含むサード・アルバム「オペラ座の夜」が最高傑作と言われているようだが、それにはあまり異論はないのだけれど「オペラ座の夜」は多彩な種類の音楽から成り立っているためロック・アルバムとしての最高傑作を挙げるとすれば、ヒット曲「キラー・クイーン」を含む、セカンド・アルバムの「シアー・ハート・アタック」ではないかと思う。このアルバムでは、ブライアン・メイのギター、ロジャー・テイラーのドラムス、ジョン・ディーコンのベース、フレディ・マーキュリーのヴォーカル、その全てが絡み合って、見事なロック・アルバムになっていると思う。
フレディ・マーキュリーの45歳でのエイズによる早逝は、「早すぎる才能の死を悼む。」という論調、或るいは「可哀そう。」という論調も含まれていたと思うが、わたしは、前者の論調には同意するものの「可哀そう」という見方には、大変な違和感を覚えてしまう。
わたしは、フレディ・マーキュリーの人生の選択肢には、2つあったように思われる。1つ目は「ファンのためにも、ヴォーカリストとして末永く歌い続ける。」という事、もう1つは「性的嗜好として個人的な男色家としての人生を愉しみ切る。」という事。フレディ・マーキュリーは後者を選択したという事だ。セーフ・セックスなど一切心がけず、あくまでナマでの性行為に没頭し、エイズに感染したという事は、アナル・セックスを好み、精液を直腸に注ぎ込まれる事に至福の喜びを感じたという事で、そのセックスには微塵の後悔などなかっただろう。わたしは、この事についてはフレディ・マーキュリーに拍手を送りたい気もちだ。
わたしが社会人になった1986年は、アメリカからエイズが上陸した年で、「せっかくこれからセックスを愉しもうと思っていたのに、すっかり水を差されてしまった。」という落胆でいっぱいだった。この事は、つまり自分で自分の命を守ろうとする事であり、数十年経って、今やコロナ禍で世界は大騒ぎ。わたしには、表現活動を続けていきたいという願いがあるにしても、マスク着用、手指のアルコール消毒、手洗い、うがいの励行・・・というように、未だ自分の命を守るために、ちまちまと努力しているわけである。必要な事なのかもしれないが、何だか情けない人生を送ってきてしまったような気も何処かに持っているような気もする・・・
フレディ・マーキュリーは、ヴォーカリストとしても素晴らしかったと思うけれど、自分の人生を例え短命でもきっちり謳歌したという点で、尊敬に値すると、わたしは思うのだ。
● カーペンターズについて。
わたしが小学校4年生のときに、自分のお小遣いで初めて買った洋楽のレコードが、カーペンターズの「シング」だった。本当は「イエスタデイ・ワンス・モア」のシングルが欲しかったのだけれど、売り切れだった。1973年当時の日本は、空前のカーペンターズ・ブームで湧いていて、武道館での来日公演のチケットの申し込みはビートルズを超えたと大きな話題になっていた事をよく覚えている。もちろん本国アメリカでもヨーロッパ各国でもカーペンターズは大人気だった。
カーペンターズは、作曲家バート・バカラックの流れを汲むアーティストで、1969年のデビュー以来、プロデューサー兼アレンジャーの兄リチャード・カーペンターとヴォーカルの妹のカレン・カーペンターと共にハーモニーの美しいカーペンターズ・サウンドを造形していき、セカンド・アルバムに収録されていた「遥かなる影」のビルボード・チャート1位をきっかけに、アルバムのリリースを重ねていくごとにそのサウンドは洗練されていき、多忙なツアーの合間に制作されたとはとても思えないアルバム「ナウ・アンド・ゼン」でそのサウンドと人気は頂点を極めた。何よりアルト・ヴォイスが大変に魅力的で英語の教材にもなったというカレン・カーペンターのヴォーカルの魅力がカーペンターズ・サウンドの中核を成していたのは確かだが、リチャード・カーペンターのカレン・カーペンターのヴォーカリストとしての才能を活かし切るプロデューサー兼アレンジャーの仕事振りも実に的確なものだった。あまりにも有名な「イエスタデイ・ワンス・モア」が弱冠20歳のカレン・カーペンターの歌唱力で発表された事には今でも驚きを禁じを無い。
リチャード・カーペンターは常々カーペンターズ・サウンドとは「タイムリー・アンド・タイムレスにある」のだと語っていたのだが、その意味は、後にファンが知る事となった・・・
ポップ・グループが避ける事のできない人気の少しづつの凋落も、アルバム「ナウ・アンド・ゼン」の発表後、3年振りにリリースされた「ホライゾン」あたりから明確になっていった。このアルバムからは明るい曲調の「プリーズ・ミスター・ポストマン」がシングル・カットされ、見事にビルボード・チャートの1位に輝き、そのポップ・サウンドとしての出来栄えは実に素晴らしかったものの、それまでのカーペンターズの魅力が、片思いの女性の心情を切々と歌い上げる事の魅力が中核を成していたにも関わらず「プリーズ・ミスター・ポストマン」は万人狙いとも言えるファミリー・レストラン的なヒット曲として成功してしまったため、その後が続かなくなり、人気の凋落が始まってしまった。そして、若すぎるカレン・カーペンターの拒食症による1983年の32歳での若すぎる死は、カーペンターズ・サウンドの終わりを告げるには、あまりにも凄惨過ぎた。
後に日本で制作されたテレビ・ドラマ「未成年」では、カーペンターズの「青春の輝き」という曲が主題歌として用いられ、テレビ局には「カーペンターズのニュー・アルバムはいつ発売されるですか?」「カーペンターズの来日公演は、いつ行われるのですか?」という問合せが殺到して、カーペンターズのベスト・アルバムは瞬く間にオリコン・チャートを駆け上がり、200万枚もの売り上げを記録して、社会現象にまでなってしまった。アメリカのビルボード・チャートではこの曲は25位でとどまっていてヒット曲にはならなかったのだが、この曲の日本での成功により、「青春の輝き」は、日本では「イエスタデイ・ワンス・モア」を超えるものとなった。
ここに、リチャード・カーペンターが公言していた、カーペンターズ・サウンドとは「タイムリー・アンド・タイムレスにある」という言葉が証明される事となった。未だに、少なくとも日本に於いては、カーペンターズの代表曲は「青春の輝き」であるとされ、いつまでも聴き継がれている。
● ビー・ジーズについて。
ビー・ジーズは1970年に日本で公開され、大ヒットとなった映画「小さな恋のメロディ」で用いられた「メロディ・フェア」や「若葉のころ」によって、白人ポップ・グループとして認識されていると思うのだが、その本質は白人ソウル・グループとしての才能にあると思う。やはり「小さな恋のメロディ」で用いられた「トゥ・ラヴ・サムバディ」という曲は、元々飛行機事故で亡くなってしまったオーティス・レディングに向けて制作されたものだったと言う。
その後、人気の浮き沈みを乗り越えながら、やはり大ヒットした映画「サタディ・ナイト・フィーバー」の音楽を全面的に担当して、ファルセット・ボイスを駆使した独特のヴォーカル・スタイルで世界的にディスコ・ミュージックのブームを巻き起こす事となったわけだが、このときの音楽プロデューサーがアレサ・フランクリンの名盤「スピリット・イン・ザ・ダーク」を手掛けたアリフ・マーディンであった事は重要な事だ。
ビー・ジーズが1970後半にヒット曲を立て続けに発表した頃、そのファルセット・ヴォイスには賛否両論あったようだが、わたしはその後に登場する事となる若き日のプリンスの最初期のアルバムに見られたファルセット・ヴォイスにその影響が顕著に現れていると考えている。
また、ビー・ジーズは黒人アーティストへの楽曲提供も盛んに行なっており、ダイアナ・ロスに提供された曲も、ディオンヌ・ワーウィックに提供された曲も、軒並み大ヒットを記録していた。
わたしは、ビー・ジーズの横浜アリーナに於ける来日公演を聴きに行ったが、初期のヒット曲からディスコ・ミュージック時代までの曲が立て続けに披露され、その1連の流れが全く違和感を感じさせなかった事に、やはりビー・ジーズは、白人ソウル・グループなのだという思いを確信した事を覚えている。
その後、ディスコ・サウンド・ブームの終焉とともに、また3人のメンバーの内、2人のメンバーが亡くなってしまった事により、ビー・ジーズは自然消滅した形になっているようだが、ビー・ジーズが世に送り出した楽曲の数々は、記録として残っているばかりではなく、人々の記憶に残るものとなっているように思う。
●ボブ・ディランについて。
ボブ・ディランがノーベル文学賞を受賞した事は、まだ記憶に新しいところだが、ボブ・ディラン自身は受賞式には出席せず、代わりにパティ・スミスが受賞式に出席して、見事にボブ・ディランの「激しい雨が降る」を歌い上げ、人々に感銘を与えた事は記録に残る事だと思う。ボブ・ディランもパティ・スミスも、ボブ・ディランのノーベル文学賞受賞には、ノーベル賞の話題作りだと気づいていたと思うのだが、パティ・スミスの受賞式への出席は、ボブ・ディランへのリスペクトそのものだったと言える。その頃、当のボブ・ディランは、劣化した声で「ネバーエンディング・ツアー」なるものを続けていたようで、アメリカの何処にいるのかもわからず、連絡がつかなかったようで、老境に達しながら「何をやっているんだ。」という具合で、気まぐれというか、何処か可愛らしいというか(笑)、実にしょうもない男ではある・・・
ボブ・ディランは、フォーク・ソングの先駆け、ウディ・ガスリーの影響を受けて、プロテスト・ソング「風に吹かれて」や「時代は変わる」などを発表して、フォークソング・ファンに熱狂的に迎えられたが、その後、歌の巧いモダン・フォーク・グループ、ピーター・ポール・アンド・マリーにより、それらの曲のメロディ・ラインがとても美しい事が認知され、ヒット曲にもなった。
1960年代半ば、ボブ・ディランがアコースティック・ギターからエレキ・ギターに持ち変えて活動を始めたとき、かねてからのフォークソング・ファンからは激しい罵声を浴びる事となったのだが、そんなときにリリースされた「ライク・ア・ローリング・ストーン」という6分近い曲は、全米で広く受け止められ、ボブ・ディランにとって、初のビルボード・チャートの1位を記録する事になったのだった。
フォークソング・シンガーがアコースティック・ギターからエレキ・ギターに持ち変え、フォークソング・ファンから罵声を浴びるという現象は日本にも飛び火して、岡林信康や吉田拓郎がそのような体験をしたわけだが、吉田拓郎の「結婚しようよ」が大ヒットしてしまった事により、「ライク・ア・ローリング・ストーン」が受け容れられたように日本のフォーク・シンガーたちも一般に受け容れられる事になったのだった。
1978年にボブ・ディランが初の来日公演を行なったとき、演奏スタイルを次々に変えてしまうボブ・ディランは、派手なラスベガス・ショーのスタイルで演奏して、聴衆を戸惑わせた。そのとき聴衆の1人としてボブ・ディランの演奏に接した美空ひばりからは「岡林信康の方が遥かに良い」と言われる事ともなったのだった。その発言には、美空ひばりが岡林信康から2曲の作品を提供されていた事も関係していたといういきさつもあるのではないかとも思われる。
ボブ・ディランの活動の全盛期はビートルズをも嫉妬させたという、1960年代末のアルバム「ブロンド・オン・ブロンド」から1975年のアルバム「欲望」までとされ、殊に「血の轍」は最高傑作とされているようで、わたしはその事に何の異論はないけれども、わたしにとっての愛聴盤は地味なカントリー・アルバム「ナッシュビル・スカイライン」で、1曲目のカントリー界の大御所ジョニー・キャッシュとの掛け合いによる曲も何の遜色もなく、見事なものとなっている。
デビューから現在に至るまで、ボブ・ディランのフォロワーは後を絶たないが、当のボブ・ディランは「ネバーエンディング・ツアー」で、今頃、アメリカの何処にいるのだろうか・・・?
●デヴィッド・ボウイについて。
2016年に(もう、そんなに経つのか)デヴィッド・ボウイが亡くなって、レディ・ガガが先頭に立って、追悼集会を行なったり、遺作となったアルバム「ブラック・スター」がビルボード・チャートの1位になったりしたときも、わたしはデヴィッド・ボウイの長年のファンだったにも関わらず、あまり大きくは心が動かなかった。
10年ほどアルバムのリリースがなかったので、どうしたのか、と思ってはいたけれども「地球に落ちてきた男」とまで言われていたデヴィッド・ボウイでさえ、癌で69歳で亡くなってしまうのだな・・・とは漠然と思った。
リリースされたアルバムは殆ど買い揃え、デヴィッド・ボウイの生涯を辿ってきたわたしは、デヴィッド・ボウイから多くの事を学んできたように思う。
知っている人は多いと思うが、1972年に、「ジキー・スター・ダスト」というキャラクターを自らに与えてイギリスのグラム・ロックを牽引したデヴィッド・ボウイ。顔に独創的なメイクを施し、山本寛斎デザインの衣装に身を包み、そのパフォーマンスは多くのオーディエンスを虜にした。何よりもとにかく「1番初めに挑戦してみる。」というアーティストとしての姿勢に魅了された。
デヴィッド・ボウイは、そのような派手なパフォーマンスをしながらも、インタビューでは次のように答えている。「わたしは、ボブ・ディランのようなアーティストを目指している。あくまでアルバム・アーティストとして在り続けて、時々シングルのヒット曲を出すような・・・。」
実際デヴィッド・ボウイは、「アラディン・セイン」「ダイアモンドの犬」などとキャラクターを変え続けて、アルバムの名盤を本国イギリスを中心にリリースし、精力的にツアーを展開しながら、時々シングルのヒット曲を出すという姿勢を貫いた。
そんなデヴィッド・ボウイではあったが、尖鋭的なアルバムを発表したのは、アルバムの制作場所をベルリンに移したり、アメリカに移したり、また本国イギリスに移したりしながらアルバムを発表した1979年のアルバム「スケアリー・モンスターズ」までに限られている。
その後、デヴィッド・ボウイは1983年制作の大島渚が監督した映画「戦場のメリークリスマス」に出演して、坂本龍一や北野武と共演したが、坂本龍一が映画音楽作曲家としてアカデミー賞を受賞したり、北野武が芸人から映画監督にも活動の場を広げていった事を考えると、デヴィッド・ボウイの俳優としての活動は凡庸であったと言わざるを得ない。
デヴィッド・ボウイは、再び活動の拠点をアメリカに移し、ヒット・アルバムの仕事人とまで言われたナイル・ロジャースのプロデュースのもと、「レッツ・ダンス」というダンス・アルバムをリリースして、そのアルバムはアメリカを中心に大ヒットしたが、その事は、アメリカでは、ダンサブルなアルバムでしか成功しないという事を証明してしまい、その後のアルバムはその2番煎じとなっていってしまい、尖鋭的であったデヴィッド・ボウイのサウンド造りの活動は、他のアーティストのダンサブルな音造りの後追いの形となってしまい、その事はおそらくデヴィッド・ボウイの死まで続いていったと思われる。
1度手を染めてしまったもので1度成功を得てしまうと、もう後戻りはできないという事をわたしは学んだ。
だからこそ、わたしは2016年にデヴィッド・ボウイが亡くなって、レディ・ガガが先頭に立って、追悼集会を行なったり、遺作となったアルバム「ブラック・スター」がビルボード・チャートの1位になったりしたときも、わたしはデヴィッド・ボウイの長年のファンだったにも関わらず、あまり大きくは心が動かなかったのである。
● ビートルズについて。
20世紀に最もその名を世界中に知らしめた、偉大なるロック・バンド、ビートルズの活躍振りに、異論を唱える人はまずいないだろう。リリースされたシングルは全て大ヒット、リリースされたアルバムは全て大ヒット。解散してから50年以上も経つというのに、デジタル・リマスターされた過去のアルバムその全てが今だにビルボード・チャートの上位を占めてしまう事などに於いても、このようなバンドはビートルズをおいて他に例がない。
また、10年に満たないその活動期間に於いて、リリースされるアルバムごとに、リスナーを毎回驚かすような進化が顕著だったという事も本当に大きな要素であるだろう。
そんなビートルズではあるのだけれども、わたしは、ビートルズに対しては、好きでも嫌いでもない。名曲の数々を世に送り出したビートルズに対して、わたしがそのような感情を抱く1つの理由は、単純にそれらの曲に対してのわたしの趣味嗜好によるところが大きいと思う。
とはいえ例外的に、「イエスタデイ」「ペーパー・バック・ライター」「ア・デイ・イン・ザ・ライフ」「レット・イット・ビー」などは、あるのだけれども・・・
名曲の数々を世に送り出したビートルズに対して、わたしが好きでも嫌いでもないという感情を抱くもう1つの理由は、ビートルズが、そのキャリアに於いて、途中でライヴ活動を辞めてしまい、スタジオ・ワークにすっかり移行していってしまったという点にある。その環境の中で数々の傑作アルバムが制作されていったという事は分かるのだが、ビートルズが何故そのような選択をしていったかの理由については、彼らのファンではないわたしには分からない。
ローリング・ストーンズの大ファンであるわたしにとって、ローリング・ストーンズを好きなその最大の理由の1つは、ローリング・ストーンズがライヴ活動を重要視して、ロックの持つ昂揚感やスリリングさを非常に体現していた事にある。その点に於いて、わたしは、ビートルズに対して、何だか物足りさを感じてしまうのだ。
ビートルズがリリースしたアルバムの中でも、20世紀ポピュラー・ミュージックの金字塔と称される「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」については、各楽曲の質の高さ、各楽曲が緻密に制作されていった事などについて、十分に理解できるのだけれども、とにかく聴いていて、閉塞感が半端でなく、何だか窒息してしまいそうな感覚に、わたしは見舞われてしまうのだ。
このアルバムに影響されて、ローリング・ストーンズが「サタニック・マジェスティーズ」というアルバムを制作して、その出来栄えはなかなか良かったにも関わらず、「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」の出来栄えには遠く及ばなかった事、ビーチ・ボーイズの天才ブライアン・ウィルソンがスタジオに籠もって「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」のようなアルバムを制作しようとしたあまり、精神疾患に罹患してしまった事などを考えると、いかに「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」というアルバムが秀でたものである事は分かるのだけれども・・・
また、ビートルズのおびただしい名曲の数々が、ポール・マッカートニーとジョン・レノンの競合によって、緊張感高く制作された事も、非常にビートルズの稀な成功にとって関わっている事だろう。
ビートルズが解散してからのポール・マッカートニーとジョン・レノンのソロ活動にについても見るべきところは多くあるけれども、ビートルズ時代の稀な成功には遠く及ばない。
またビートルズ解散の理由について、オノ・ヨーコがビートルズの活動に割って入ったという事もしばしば指摘されるところだが、ビートルズのファンにとっては、オノ・ヨーコの存在は本当に邪魔で仕方なかった事も想像にかたくないのだが、わたしには、オノ・ヨーコは前衛アーティストとして見るべきところがとても多い人物だと感じられる。
いずれにしても、ビートルズが20世紀に最もその名を世界中に知らしめた、偉大なるロック・バンドである事には変わりはないと、わたしは思っている。
*********************
書けば、形になる。書かなければ、思っているだけで終わってしまう。そのような気もちで、わたしは、このエッセイを書いた。