広瀬 勉
#photograph #photographer #concrete block wall

この街では時間がかかる
玄関扉を解錠されて 敷居をまたぐこと
夏至の晴れた午後に
アルテバウの入り口のブザーを鳴らす
戦争を超えて生き残った古いアパート
の 入り口
あなたの自筆で書かれた苗字 その横のボタンを押す
そう この国で呼び鈴は summer(ズンマー)
夏とともに 濁音で始まる言葉にふさわしい音をたて
重い木の扉が開いた
思い出す
あの瞬間
わたしは街の本当の内側に入ったのだ
人に撫でられた形にすり減っていた
階段の木製の手摺
すこし傾きのある階段を三階まで上って
二つ目のボタンを押す
開かれた扉の向こう側で あなたは
新聞紙を握って立っていた
濡れた新聞紙は 窓をきれいにする
ほら 君が来るのを見ることもできたし
アルテバウの暖房は薪ストーブ
冬は部屋が暖まるまで白い息を吐きながら、分厚いコートを着たまま薪を投げ続けるんだよ そう、数十分ずっと
(知っている あなたを知ったのは冬だから ちくちくする分厚い毛のコートはまるで軍用毛布のよう)
天井まで三メートル 床は石に似た冷たい大きなタイル
きっとこの家のどこに触れても冬は氷だ
氷の部屋が透明な水蒸気になるまで あなたはストーブに薪をくべ続ける
だからあなたをカイと呼ぶ
コーナーの隅には小さな蜘蛛がいた
台所の食器棚の上にもトイレの片隅にも
小さな蜘蛛たちはいつも変わらず密かに糸を吐き続けているのだ
空から焼夷弾が落ちてくる時にも街がコンクリートの壁で真っ二つに分かれても
本棚から一冊本を抜き取ると
フナムシのような銀色の虫が隙間から出て来た
ぴんぴんはねる銀色の魚の胴体に
二本の触覚と小さな複数の手足がついた虫
お前は きっと漢字で名付けられた「紙魚」だ
わたしが日本で見たことのない
紙の魚
ヒゲのある黒い虫に似たアルファベット
ひしめく新聞紙を握りしめ
窓際のカイがこの国の言葉で私を呼ぶ
ごらん 下を見なければまるで森のようじゃないか
三階から首を出して外を見ると
菩提樹の伸びた枝枝が網目のように繁茂する
この国の言葉に誘われ
小さな蜘蛛とぴちぴち跳ねる紙魚と共に
この窓から出て
樹々の梢を渡り歩いて
あの日から
わたしは街の本当の内側に入ったのだ
いつまでも暮れない夏至の空まで上って
ごらん まるで森だ

鬼は人間をバクバク食べるのが好き。
人間の悲鳴もちょいとしたスパイスだ。
ある時変な人間を食べてしまった。
そいつは食べてくれてありがとうといい、
そいつを噛み砕いている時、
うふふ、うふふと喜んでいた。
何十年何百年と年月は過ぎていったが、
鬼はあの人間の喜ぶ声が忘れられなくて、
ある日あの人間に変わってしまい、
食べてくれる鬼を探し続けることとなった。
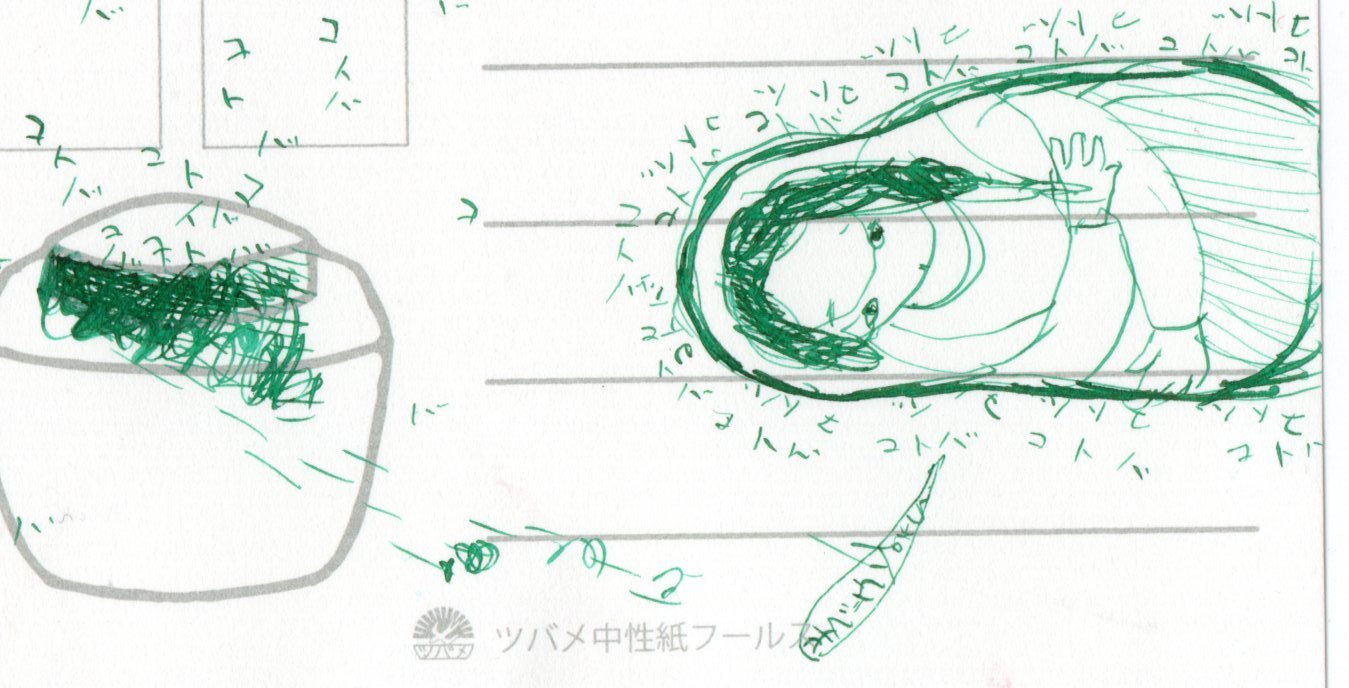
言葉を探すのはつらい
考えてる時、頭の中に言葉はない
感覚の湖の中にドブんと沈み込み
そこでキラキラしたものを探してる
言葉で現実に戻そうとしたって
言葉は嘘つきだから
キライ

私が猫だったら、
いつも可愛い可愛いと言ってくれるのかな。
うっかりあなたの大切なものを壊しても
仕方ないか、猫だもの。と言って許してくれる。
私が猫だったら、
いつも側に来て優しく撫でてくれるのかな。
そしていつかあなたより先に死んでいっても
あなたには私との美しい思い出しか残らないのだ。