さとう三千魚
2018年9月1日に新宿文化センターで行われた工藤冬里のピアノリサイタル行ったのだが、リサイタルの後に工藤冬里から詩集「棺」をいただいた。
わたしの詩集「貨幣について」をお送りしていたからそのお返しかとも思われた。
工藤冬里の詩集が出版されていることは知らなかった。
奥付を見ると、2012年発行、十六夜書房、初版第三刷となっている。
工藤冬里のファンたちから随分とたくさん購入された詩集なのであろう。
わたしは工藤冬里の音楽は詩であると思っているから、
詩集を出さなくても彼は十分に詩人であると思うのだが、
工藤冬里の「棺」という詩集はこの世にあり、リサイタルから帰って、読みはじめてみたのだ。
わたしはすでに工藤冬里の「徘徊老人 その他」などの音楽を聴いてしまっている。
工藤冬里がソロで行っている音楽や、工藤礼子さんと行っている音楽、マヘル・シャラル・ハシュ・バズの皆さんと行っている音楽、などなどを聴いてしまっている。
わたしはそこに詩を見ている。
最低の人の声を聴いている。
工藤冬里の「棺」という詩集はどのような声を持つのだろうかと思いながら、
詩集「棺」を読み始めてみたのだった。
「棺」は遺体を入れて葬るための箱であろう。
この詩集の奥付の前頁の空白の中に一行「二◯一一年一月〜五月」と記されていて、
この詩集の詩は、東日本大震災を前後して書かれたものであることが解る。
はじめに「遺書 I」「遺書 II」という詩がある。
全文を引用してみよう。
・・・・・
遺書 I
墓を暴き
骨を洗うな
おれの灰は公衆トイレに流してくれ
どこでもいい
水洗便所に流してくれ
王たちの墓に入れるな
遺書 II
死と引き換えにやっと読まれるような
生きている者の
落度だけで
縫われていく
きみのマフラー
生きられる時間は短いので
病の悲惨さを確認するだけで終わってしまうね
総ゆるポジティブな思考は
だから嘘だ
王国の
散見される
手術前の雪の
落葉のようなバスの遅延
・・・・・
工藤冬里の詩は絶句の後の言葉でできている。
おそらくはこの世で「手術前の雪の落葉のようなバスの遅延」を体験している。
そして、東日本大震災の後の絶句も体験している。
詩に向かう時、わたしたちはあまり語るべき言葉を持たない。
詩は言葉が途切れるところからはじまる行為だとわたしは思っている。
言葉が途切れ絶句するところとは自我から非我に至る場所ということなのだろう。
そこでは、あまり語るべき言葉がないのだ。
語るべき言葉はないが全てが詩だというような場所なのだろう。
詩の言葉はコミュニケーションの手段ではない。
詩の言葉はコミュニケーションから逸脱することができる言葉だろう。
広告屋さんの言葉や政治家さんの言葉とも異なる。
彼らは言葉に効果と結果を期待する。
商品の売り上げを上げること、選挙に勝つこと、など、効果と結果を必要とする。
これまでに随分とたくさん、そんな言葉たちを見てきた。
社会とはそのような言葉で溢れかえっているところだった。
ご苦労さまなことです。
詩の言葉は「作品」でさえないかもしれない。
詩の言葉は絶句の後で自身の肉体に刻む刺青だろう。
それは作品をやめてまで届こうとする最底の人の声だろう。
工藤冬里の詩こそ最低の人の声だろう。
「der Rahmen」という詩の冒頭を引用してみよう。
・・・・・
既に滅ぼされている枠だけが座っている
既に滅ぼされている枠だけが座っている
既に滅ぼされている枠だけが家に帰る
既に滅ぼされている枠だけが座っている
既に滅ぼされている枠だけがアルジャジーラのtweetを追う
既に滅ぼされている枠だけが座っている
既に滅ぼされている枠だけがyoutubeを眺める
既に滅ぼされている枠だけが座っている
既に滅ぼされている枠だけが服を着て座っている
既に滅ぼされている枠だけが座っている
或いは帰らない
或いは帰る家がない
既に滅ぼされている枠だけが座っている
既に滅ぼされている枠だけが座っている
既に滅ぼされている枠だけが座っている
場所の問題ではない
墓所の問題なのだ
既に滅ぼされている枠だけが座っている
既に滅ぼされている枠だけが座っている
既に滅ぼされている枠だけが座っている
・・・・・
あの震災の後に残ったのは「枠」だけだったのだろう。
家族写真の額縁の枠であったり津波で流された家屋の基礎部分であったり、やわらかいものを包む枠組みだったろう。
やわらかいものの多くは流されてしまった。
その事実がここでは語られているようだ。
「弁当箱」という詩がある。
ここにもやわらかいものへの言及がある。
・・・・・
場所がなくなっても妙法がある訳ではない
本当はここで言葉が出るかどうかの実験だったのだ
(いまこの灰色の群集に別れを告げて山に登ったら自然はどう映るだろうか)
最後の歌というものはやはりあるのだ
とうとう歌えなかった背骨の陣営の歌
・
いつも 二つの場所があると思っていた
いまはどこにもない
ひとりで暮らしていかないと
ひとりで暮らしていくには
詩は浮き上がった剰余なのか
詩は池に浮き上がった剰余なのか
ここからは 本当に 弁当箱の
ようなものを失くすのか
・・・・・
詩はとうとう死者たちの背骨の陣営の歌を歌えなかったのだ。
詩は、池の底から浮き上がる死体の泡のようなものなのだろうか、
ここから人びとの本当にあたたかい弁当箱のようなものは失われるのだろうか?
工藤冬里は人びとが失ってしまうやわらかいものを掴まえて抱きよせようとしているように思える。
それを人びとは誰でも持っているのに失ってしまう。
歌はそのような別れの後に歌われるエレジーだろう。
最後に「そういう風にして」という詩を全文、引用してみます。
・・・・・
そういう風にして
そういう風にして今年に入って、ある曜日にある場所である地層から遺書の
ような言葉を出すことを続けてきた。震災の後、東京でもそれが出来る状況
になり、東京から帰って来てからは最早場所は日常全体に敷衍できると思い
始めた。書くことには手続きが必要だ。詩とは言葉を出す場所を決めること
だ。そういう風にして、再びノスタルジーの契機さえ捉えることが出来るよ
うになる。そういう風にして、今日のわたしが昨日のわたしになる。未来は
ないにしても。
・・・・・
「詩とは言葉を出す場所を決めることだ。そういう風にして、再びノスタルジーの契機さえ捉えることが出来るようになる。そういう風にして、今日のわたしが昨日のわたしになる。」と言われている。
工藤冬里の歌は、そういう風にして、歌われるだろう。

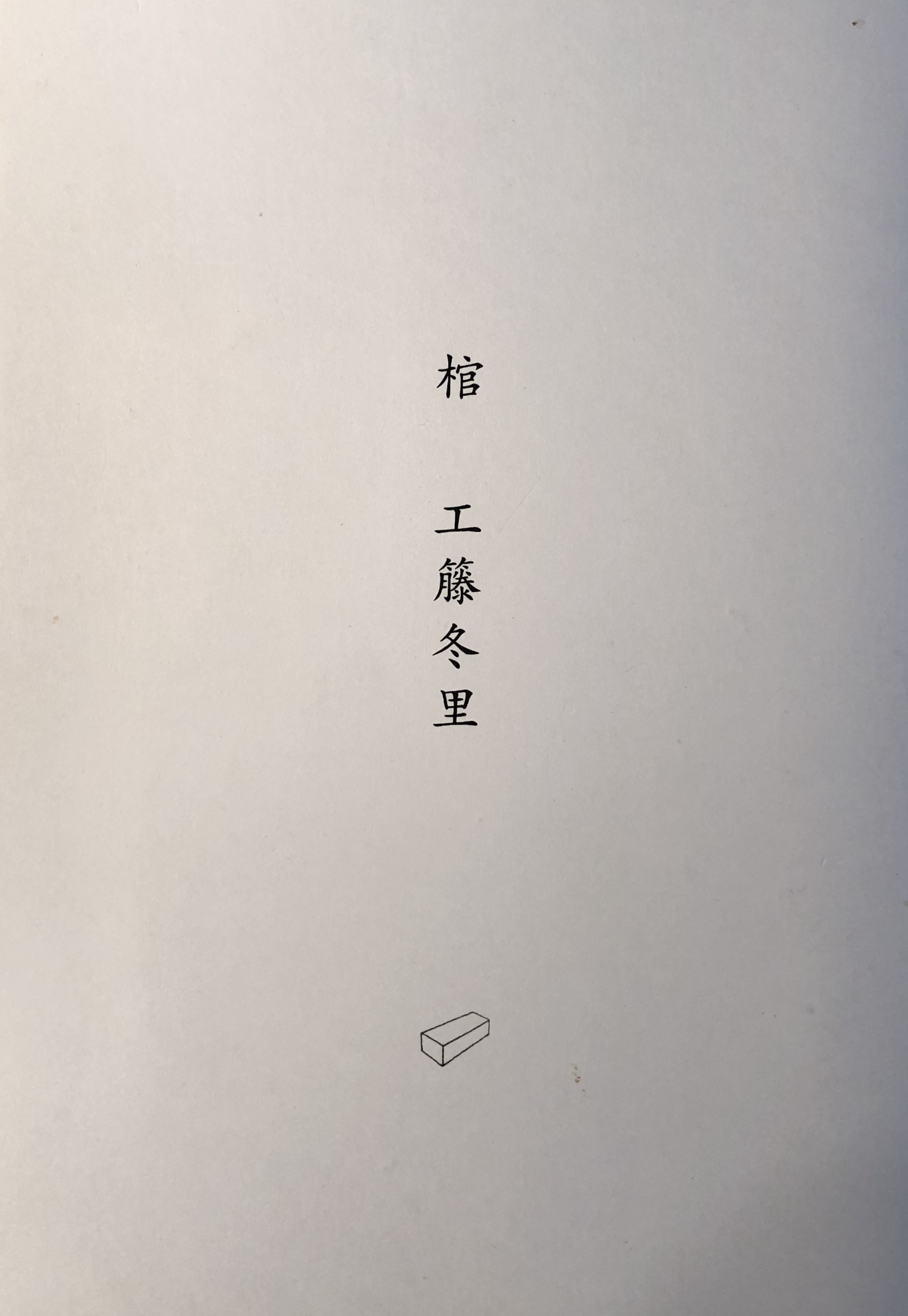


いいです
ありがとう。
いま、東名高速バスで、
ひかりの馬に向かっています。
!!!!!
いいです