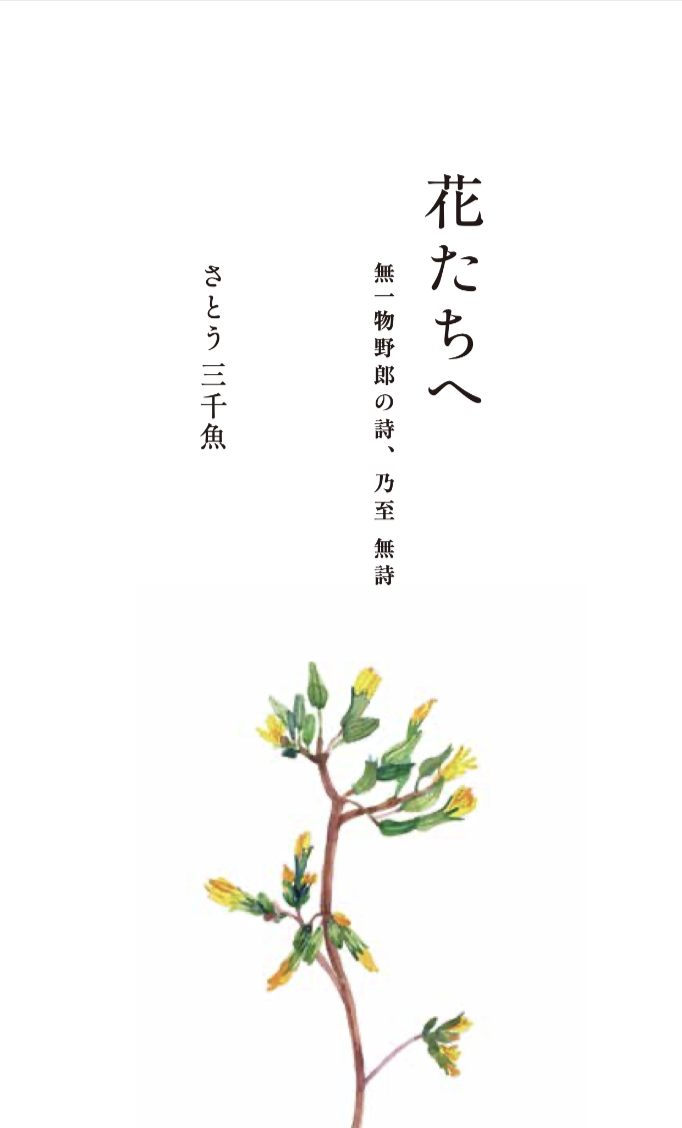佐々木 眞
2022年の5月28日の土曜日、作者の地元である静岡市の北街道にある本屋さん「水曜文庫」というところで、この詩集はスタートした。
「みらい」というタイトルである。
みらい
あしたの
ことも
みらいの
ことも
わからないけど
ここに
わたし
いて
あなたがいて
薔薇が
咲くのを待っている
ピンクの薔薇
咲くのを
「あとがき」を読むと、この頃作者は、なぜか自分の詩が行き詰ったように感じていたようだ。作者の言葉を借りると「オワコンのように感じられて」いたようだ。
そんな苦境を救ってくれたのが「水曜文庫」のご主人だった、と作者は感謝しているが、本当に危機を突破したのは作者自身だろう。
なぜなら、この詩集に掲載された詩は、全部が全部即興詩であり、しかもこの即興詩人は「水曜文庫さんのお店の小さなテーブルをお借りして、小さなプリンターとスマホを置いて、お客さまからお好きな花と詩のタイトルを伺い、その方たちに花の詩を書いた」のだから。
従来の詩作とは、全く次元の異なる画期的な詩作方法を、一気に誕生させのだから。
仏蘭西の詩人ポール・ヴァレリーなら「これは一つの方法的制覇だ!」と、叫ぶかもしれない。
普通の詩人の普通のやり方は、無人の書斎でパソコンや原稿用紙に向かって沈思黙考、呻吟しながら書き下ろすのだろうが、それはあくまでも自分の大脳前頭葉の内部で完結させる古典的な書法である。
「詩のボクシング」の最終ラウンドでは、その場で即興詩を立ち上げて優劣を競うが、創作方法自体は前者と同様である。
さいきんの短歌の世界では、読者のリクエストに応じて、一般ではなくその人個人のためのパーソナルな短歌をつくる手法が話題になっているが、これとて即時の即興歌の創作ではない。
まさしく「花」というカテゴリーと、「題目」という思案の方向性を眼前の第三者の「骰子一擲」に委ね、次の瞬間に未知の時空に羽ばたいて新しい言葉を模索する「詩的投企」の試みに他ならないのである。
これで詩人は、息を吹き返した、のであろう。新たに生まれ変わった詩人が、以後さまざまな土地を巡礼し、さまざまな人々との一期一会の邂逅を果たしながら、私の住んでいる鎌倉の地に姿を現したのは、忘れもしない2024年の8月4日の暑い日曜日だった。
日記を繰ると、「午後1時30分、鎌倉駅にさとう三千魚氏を迎え、共に大塔宮を経て瑞泉寺へ行き、歌人、そして山崎方代の研究家としても知られる住職の大下一真氏と面会す。さとう氏は近著『方代に捧げる歌』を住職に進呈。そのお返しに小生まで『方代研究』誌を何冊も頂戴す。夜は一真住職の助言で、方代ゆかりの居酒屋「田楽屋」にて真夏の田楽料理に舌鼓を打ち、夜8時頃駅頭で別れる」
とあるが、実はこの日の昼は小生、夜は東京から偶々訪れた見知らぬ客人を相手にして、『花たちへ』の2つの即興詩が出来たのだった。
後者は本書を手に取って読んで頂くとして、その日他に訪問客が誰も居ないので、やむを得ず私を相手に、あっという間に作者がその場でスマホで打ち、ミニプリンターで印刷してくれた、1篇の即興詩を、最後にご紹介しておこう。
2024年夏
木槿の
花が
咲いていた
鎌倉の
瑞泉寺の
夏の
庭の
白い花の
咲いていた
ムクは
眠った
ムクは庭の土に
眠った
ムクは
無垢
木槿の木の下に眠る