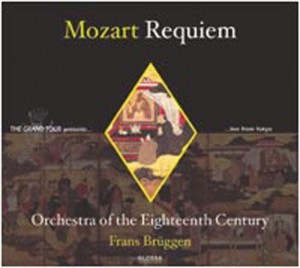加藤 閑
休日の朝は、たいてい最初にどのCDをかけようかと、棚を物色することからはじまる。バッハを選ぶことが多いのだが、きょうは久しぶりにサバールをかけた。ひところよく聴いたサント・コロンブの「2台のヴィオールのための合奏曲集」。ジョルディ・サバールがヴィーラント・クイケンとふたりで演奏している。サント・コロンブは17世紀フランスの作曲家だが、伝記的事実はほとんどわかっていない。ヴィオールの独奏曲と二重奏曲がかなりの数残っているだけだ。録音もそれほど多くはないのだろう。わたしはこの二人の演奏でしか聴いたことがない。(もちろんカタログには何点か他の演奏家の録音がある)
ディスクは2枚あって、1枚は1976年の録音、もう1枚のTomeⅡは1992年の録音である。実に16年の開きがある。前者と後者とでは、二人の演奏家のクレジットの順が入れ替わっている。すなわち、1枚目はヴィーラント・クイケンが上になっているが、2枚目はジョルディ・サバールが上になっている。1970年代といえば、古楽演奏が世界的に注目され始めた時期で、ヴィーラントは二人の弟シギスヴァルト・クイケン(ヴァイオリン)とバルトルト・クイケン(フルート)とともにクイケン兄弟として、グスタフ・レオンハルト、フランス・ブリュッヘン、アンナー・ビスルマらとともにその中心にいた。年齢も3歳ほどサバールより上になる。しかし、2枚目の出た1992年には、サバールはエスぺリオンⅩⅩを率いる新しい古楽演奏の旗手として注目されていた。だからCDの表記もサバールが上になっているのだろう。
当時、プレーヤーに乗せるのは圧倒的にTomeⅡの方が多かった。それを当時は2枚のディスクに収められた曲の違いだろうと思っていた。自分の好みに合った曲想のものが2枚目の方に多く収められているのだろうと。だが、きょうほんとうにしばらくぶりに2枚を続けて聴いてみると、曲の違い以上に演奏の質が異なっていることに気がついた。音楽を表現する音色に艶があって伸びやかだし、演奏の構成がずっと深みのあるものになっている。
わたしは音楽に対する感覚が優れているわけでもないし、ディスクを聴いて二人の演奏を聴き分けられるほどの明敏な耳を持っているわけでもない。だからこれはまったくわたしの想像にすぎないのだけれど、この音楽の深まりは、多くをサバールの演奏家としての成長に負っているような気がする。ヴィーラントもすぐれた演奏家だとは思うし、演奏にも後進の指導にも誠実さを感じさせる。しかし、みずからエスぺリオンⅩⅩという演奏団体を組織して、15世紀の音楽からベートーヴェンまで演奏しようというサバールのような才気には乏しいのではないか。
しかしながら、実を言うとわたしはエスぺリオンⅩⅩをほとんど聴いていない。デュ・コロワのファンタジー集とベートーヴェンの「英雄」くらいだろうか。ベートーヴェンは非常に明るい演奏で面白いと思ったが、記憶にはあまり残らなかった。個人的には、この人はヴィオールの演奏家という印象が強い。さきほど触れた、サント・コロンブの2枚のディスクの間の成長も、ヴィオール演奏家として1978年から83年にわたって録音された、トン・コープマンらと組んだマラン・マレのヴィオール曲集の演奏によるところが大きいのではないかと思う。これは5枚のCDになっていてサバールの代表作になっている。
ただ聴く分には作曲家として成熟しているマレの作品の方が面白い。けれどサント・コロンブ、特に第2集の方は美しい悲しみに満ちている。人は人生のどんな時間も取り返すことはできないということを告げるような悲しみに。
ディスクの価値の判断は、他の演奏にはないものを聴けるという点にある。その意味でいつまでも持っていたいと思うCDと言える。