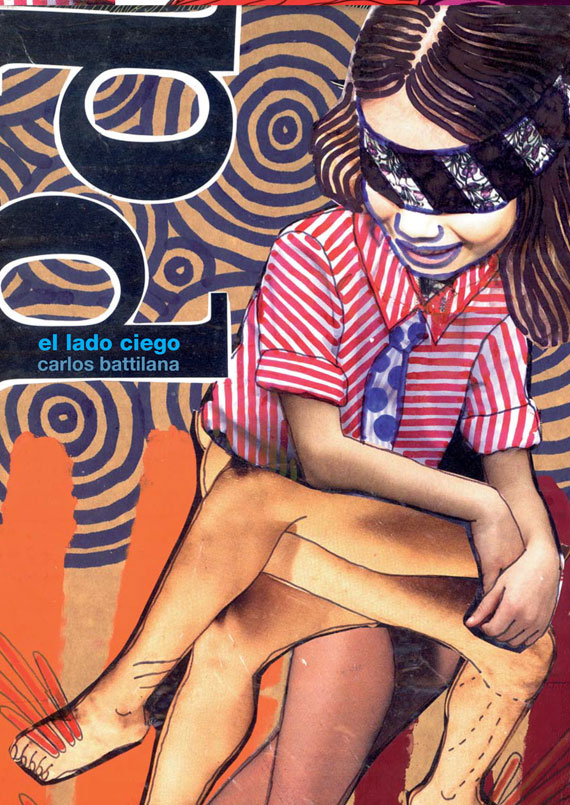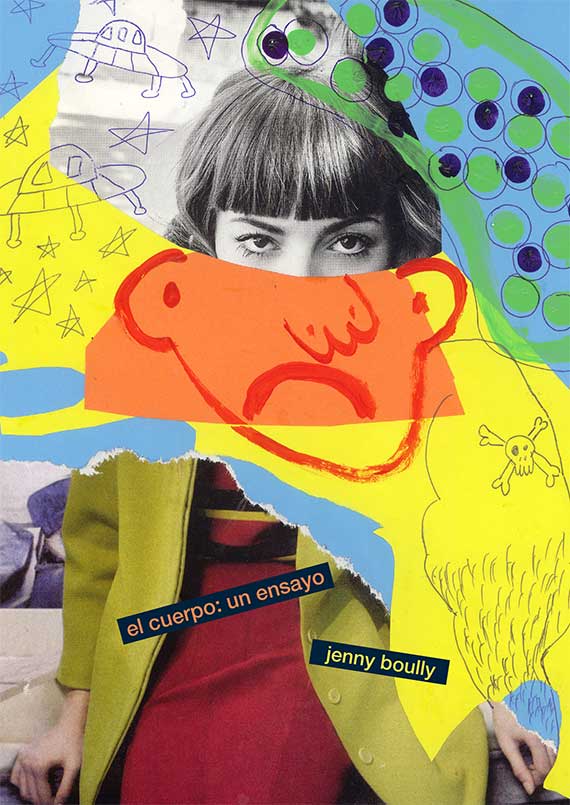村岡由梨
1. 娘A
楽しそうに話す学生たちの声。
キュッキュッと忙しく歩く上履きの音。
「学校」という色々な音が渦巻く空間の中心で、
ひとり孤独感を募らせた、娘。
特に誰かに悪口を言われたわけでも、
意地悪をされたわけでもない。
鳴らないスマホ。
周囲の友達の、悪意の無い無関心。
自分という存在が持つ意味がわからなくなって、
娘はやがて、呼吸の仕方がわからなくなった。
そして、学校へ行けなくなった。
もちろん、それだけが理由なのでは無いのだろう。
理解のある面倒見の良い先生。優しい友達。
誰も悪くない。だから辛い。
「高校3年 大学4年 仕事を始めたら40年」
「今、選択を間違えたら、この先大変なことになりますからね」
オンラインの特別ガイダンスで声を張り上げる先生たち。
それを虚ろな目で見る娘。
思わず抱き寄せると、
体が静かに震えていた。
将来のことなんてわからない。
考えたくもない。それなのに
カチカチと無情に時間を刻む時計。
カチカチとカッターナイフの刃を出す音。
切れ味の悪い刃で、娘の白い皮膚が裂かれるのを見て
悲鳴をあげる。
「自殺したい」
親が子供にそう言われる苦しさを思い知りました。
そう言って診察室でうなだれる私。
「今はたくさん甘えさせてやりなさい。」
先生はそう言った。
娘が「ママさん、ママさん」と言って無邪気に抱っこをせがんでくる。その無防備な二つの胸の膨らみに、抱くのを躊躇う私がいる。これまで母親のような役割も果たしてきた夫に娘が抱っこされるのを見て、戸惑う私がいる。父娘が抱き合うのを見て、男女の性愛を思い浮かべてしまうのだ。うなされ苦しむ娘の声を聞いて私は、女である私と母親である私との間を右往左往する。これは育て直しなのだ。甘え直しなのだ。ぎこちなく娘を抱き寄せて、背中をさする。「ママさんって、いい匂いがするね」しばらくして抱いている手をゆっくりとほどいて、娘を寝かせて、手を握る。娘がどこか遠くを見つめて言った。
「ママさん…ママさんは近いのに遠いね」
「そう?」
「うん。近いのに、遠い。」
「そっか…」
そんなことないよ、とか
遠くなんてないよ、とか
そんな風に娘の孤独を受け止められる母親に、
これから私は、
なり得るのだろうか。
2. 娘B
夜遅くに塾が終わって、
突然の雨で全身びしょ濡れで帰ってきた疲労困憊の娘が
怒り任せに、こう言った。
「何でこういう時に限って迎えに来ないの」
「死ね、毒親」
「死ね、毒親」
かわいいとか愛しいとか、かけがえのないとか
そういった熱を帯びたような感情が、
すっと冷めていくような気がした。
こんなことくらいで感情が冷めていく、
自分の心の脆さが、こわかった。
「冗談だった」と言ってくれた娘。けれど、「私の知らないところでも、私のことを毒親だと嘯いているのではないだろうか。」自分の子供のことを邪推する。他人から悪い母親だと言われるのがこわい。いつかひどい言葉で傷つけられるんじゃないかと警戒する私がいる。自分自分自分吐き気がするような自己愛に耽溺する私。それを軽蔑する娘たち。自分自分自分自分自分自分自分自分いくら人から作品を認められたって、二人の娘の心に響かなければ意味がない意味がないもうどうすればいいのかわからない。自分という存在に意味を持たせようと必死だったけど、意味がない もう意味がない 自分の都合のいいように娘たちを解釈しようとする私 後ろめたさ いい母親ぶっていること 全て見透かされている
3.
ある日、私たち家族は、窮屈なベッドで眠っていて…
身動き出来ないほど、窮屈だった。
その時、まるでフラッシュバッグのように私は
2017年に訪れたアウシュビッツ(オシフィエンチム)で見た光景を思い出したのだった。
ぞっとするほど冷たい手で心臓を握りつぶされて
引きちぎられたような衝撃だった。
気がつくと、私はアウシュビッツの収容棟にいた。
モノクロではなく、鮮やかなカラーの光景だった。
私は、褪せた水色と白のストライプの囚人服を充てがわれ、
たくさんの囚人たちと同様、「名前を奪われて」、
一緒に収容棟へ入れられた。
寒い寒い夜だった。
古びて煤けた粗末な二段ベッドで痩せた体を押しつけ合い、
互いの体温を分け合いながら、
身を切るような寒さをしのいでいた。
生きのびるために
生きのびるために、自分以外の誰かの体温が必要だった。
ある日、一人の看守が一人の囚人を表にひきずっていった。
間も無くその囚人は頭を撃ち抜かれて死んでしまった。
地面に広がる赤い鮮血。周りにいる人たちの無関心。
夢から覚めて、
その血の赤さを思い出して
これまで「詩」という名の暴力で
娘たちの「名前」を奪ってきたのではないかと思う私がいた。
ただでさえ生きづらさを抱える娘たちを
自分勝手に振り回して、
私は今まで一体何を思って書き続けてきたのだろう。
過去の何もかもを消してしまいたい。
でも消したくない。
娘たちが許してくれてもくれなくても、
無条件に人を愛せる人間になりたいから。
娘たちになら、頭を撃ち抜かれて死んでも構わない。
けれど
生きのびるために
私たちは「名前」を取り戻さなければならないのだ。
生きのびるために
人は、自分以外の誰かの存在の温かさが必要なのだ。
生きのびるために
生きのびるために。