広瀬 勉
#photograph #photographer #concrete block wall

Una nación poderosa e innumerable ha invadido mi país
Los demás son superiores a ustedes
石原さんが都知事の頃、西東京で営業の仕事をしていましたがどうやら向いてなくて、どうやって生活したらいいのかまったく分かりませんでした。そういう時期に、都営にただで住まわせてもらってました。ありがとうございました。
私は最近まで都知事はずっと美濃部さんだと思ってましたからこういうふうにも言えると思います。東京は存在しない。いや、日本も存在しない。あるのは鈴木、スズキというような発音だけだ、だから東京ではなくて鈴木都だし五輪参加も鈴木国でいい。東京だと奥の細道が拡がり、鈴木はそれを狭めるのだ。
川の両岸には鈴木が生えている。2キロ歩かないうちに鈴木川河口くらい深くなる。鈴木の葉は若返りの茶にするので小判にも彫られた。鈴木弁を咄す人は代わりに煎餅を焼いた。鈴木には金山がなかったからである。
なにか潰れたと思ったら外では笑い袋のような鳴き声
Nadie tiene amor más grande que quien da su vida por sus amigos
沢庵カレーていいんじゃないの?ウコンだから
桜三里の心(しん)は手打ち麺で頑張っていて、二流でも三流でも六流でもない。が、一流ではない。
それはこの地方の鶏ガラの敗戦後の扱いに於ける先入主から来ている。この地方で唯一一流と言えたのは春光亭のみであった。
それは春光亭がヌーヴェル・キュイジーヌとしての和食史の文脈に位置付けられ、しかもフィールドとしての純ラーメン店群の只中で営業し得ていたからであった。
シロノトリコなどがいくら頑張っても、春光亭頓挫以降の愛媛のラーメン史は存在しない、とさえ言えるのだ。
その迷走を体現しているのがりょう花東温実験店であると言えよう。
それは甘苦い松山三井の呪縛と闘う日本酒業界にも言えることだ。
それらの退廃は、バップの超克に疲れたフュージョンや新建材の建売住宅群のように風土となって久しい。
どこに真の味覚が、音楽があるだろうか?それは各自が自分で創り出す以外にないのである。
そのような中にあって、真に大阪的とも言えるダイドードリンコが開発した「当社デミタスブラック史上最高峰のコク」と謳われるプレミアムデミタスは一流であり、山崎が書きに書いて最期に到達する掌編、のようなものがあるとすれば将にそのような味わいがある。
倉敷がビスケットを創るとこのようなものになるのか。
味覚面の情報を削ぎ落とすことによってのみ可能な、形と量に関わるデザインである。

Corramos con aguante la carrera que está puesta delante de nosotros
どんどん歳とって死んでゆくので
新台入替に並ぶ
皆200万くらい捨てていた
皿ヶ嶺から冷気が降りてきて
屏風の虎も飛び出る
鈍い金属の頬が
換気の必要に気付く頃には、頸骨は絵本のように磨耗して
きちんと飲まないと溺れてしまう
今は腰くらい
火挟の要らない森で
N極S極を探す
una vida tranquila y calmada
ヤマハとターナーがアーティスト支援の立場で一緒なら絵の具とデジタル音は同じ素材である。それは冷蔵庫や空気清浄機と結婚するようなものである。そうではなく、太陽を黒焼きにしなければならない。


雪まるけ
抽象を目指していない具象は仏教的には業が深いというか過去を弄れてない。だから未来がない。組み直しの遠近法は建築家に与えられた特権だ。それが泥に沈もうともまずは描いてみることだ。
今図書館車に積んでいるのは晩年のこの三冊です。

https://twitter.com/library_nara/status/1489165204982095875?s=20&t=4lV1kauClFMnN8xifpsccA
今図書館車に積んでいるのは2017年の「芝公園六角堂跡」のみです。2019年の「瓦礫の死角」「掌篇歳時記 秋冬」は本館にあります。
https://twitter.com/kyodo_official/status/1489815762315677700?s=20&t=4lV1kauClFMnN8xifpsccA
「死ぬまで生きる 伊藤ひろみ」と書いたメモを持って来てくれましたが、それは「いつか死ぬ、それまで生きる わたしのお経 伊藤比呂美」でしょう。ズバリそうでしょう。
テキ屋にはつらい春だ
カイロの残りを風池に当てて低温火傷のような立春
立春大吉
映像美などというものが何の役にも立たない原の柩の列に倫理の雪
口を開けずに喋る両生類たちにゴムの継目
ぶら下がりぶら下がるカットソーは二種類の糸を織り交ぜたワールドリィの抜け殻
巣鴨も今は疎だろう弛んだ赤の勝敗
最初から覚える気のない動物の諦め切った發音
参道に出店は許されずテキ屋にはつらい春だ
カイロの残りを風池に当てて低温火傷のような立春
聖なる者は母を敬う鬼は線対象の過去と未来に立ち尽くす
Unifica mi corazón
#poetry #rock musician
「ひとつの文体とは、
自分自身の言語[自国語]において吃るようになることである。
これは難しい。
なぜなら、そのように吃ることの必然性がなければならないからだ。
自らの発話において吃るのではなく、言語活動それ自身で吃るのである。
自分自身の言語において外国人のようであること。逃走線を描くこと。
私に最も強い印象を与える事例は、カフカ、ベケット、ゲラシム・ルカ、ゴダール
である。」
(『対話』、11)
ジル・ドゥルーズ+クレール・パルネ『対話』
「書くことは正確な人間を作る」
という
小学校で
先生が強調した
フランシス・ベーコンのことばを
信じたわけでもないが
たぶん
ぼくは
ゼロから
にほんごを学ぼうとして
つとめて
ことばを記すようにしてみている
ぼくは
にほんごを知らないのだ
なんだか
よくわからない
しかるに
まわりのひとたちは
にほんごなんて
わかっているのが当たり前だというように
にほんごをじぶんたちは所有しているかのように
ぺらぺら
にほんごをしゃべっているし
さくさく
にほんごを書いている
こどもの頃から
それに
すごい違和感があった
にほんごは
なめくじのように
いつも
どこかどろどろしているし
ひとも来ない汚れた小さな神社の柱に
むかしに貼られたままの紙の
そらおそろしい字のように
きもちわるい
ぼくは
すこしでもどろどろしないように
きもちわるくならないように
にほんごに慣れよう
にほんごの裏の思いのようなものを見抜こう
と思って
にほんごを記してみている
そういえば
フランシス・ベーコンは
じつは
「読書は充実した人間を作る
会話は気がきく人間を作る
書くことは正確な人間を作る」
と書いたのだそうで
だったら
読書だけでいいかな
と
いまのぼくは思ったりする
本当は
充実vs気がきくvs正確
をこそ
ベーコンは問題にしたのだったかも
しれない
だいたい
小学校の先生が
ベーコンのことばを引用したのも
ノートのとりかたを
教えるときの
かっこ付けだったかもしれない
読書のすすめのときなら
「読書は充実した人間を作る」
のほうを
きっと
引用しただろう
学校の先生というものは
いつも
ご都合主義な
ものなのだから

死んだらいいのに
言っちゃいけないことだから
思っちゃいけないことだから
バチが当たったらいやだし
でもこう思うこともある
死んだらいいのに
ナイフを持って
深夜を一人歩いて
泣くための悲しい話を探して
死んだらいいのに
他人を自分を
目に見える全てを憎んで
死んだらいいのに
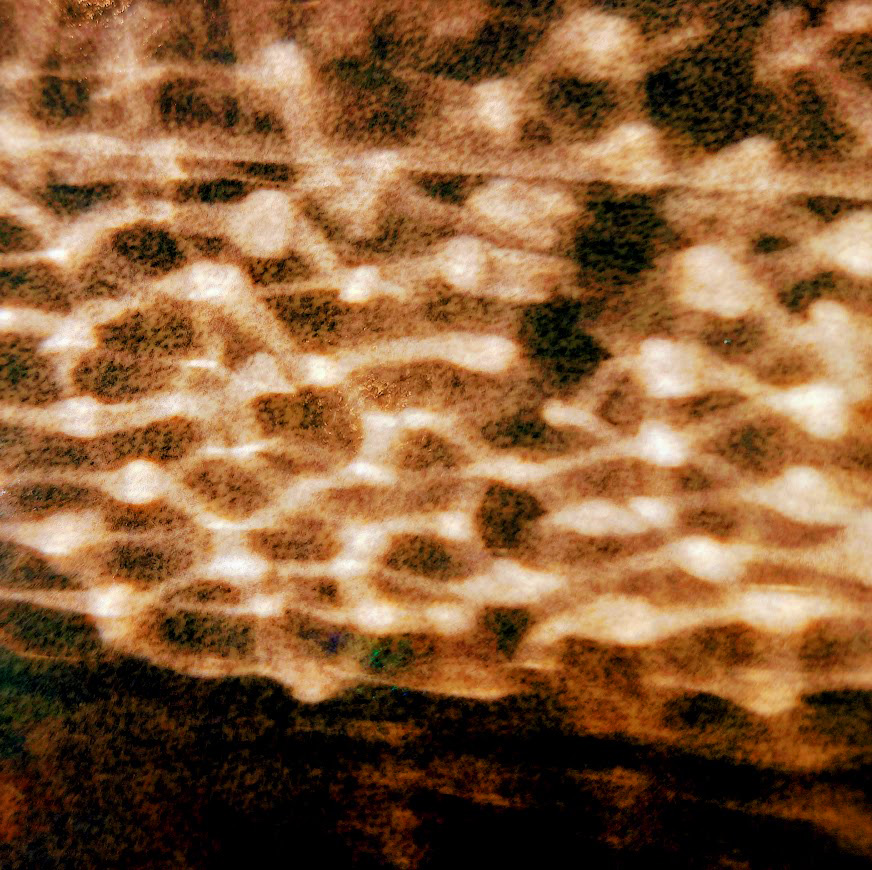
遠い地で不思議な大地を撮り続け、
長い旅から帰ると、
故郷の空気は美しく私を出迎えた
見えてないだけだった
謎が生まれたところに答えも同時に存在するのだった

1本の電線は会えない母の存在の証
電話での会話は時々意味が通じない
遠くにいる後ろめたさが背中を覆う
まだ大丈夫 まだ大丈夫
でもいつか大丈夫じゃなくなる
背中を映すことのない今日が
明日に変わるのが怖い
大阪北辺午後四時ちかいスーパーで
かごを手にひとめぐり
あれ小松菜もほうれん草
ニラも並んでいない
あるにはあっても手が出ない
見切り品もない
なんて時
間引き菜だの小かぶの葉つきだの
あれば重宝なのに
それも見当たらないと本当に往生する
だからね
緑のものがみえると
手がのびる
そう
緑みっしりひと色の
げんこつもしくはブーケ
ブロッコリー
黒ずんだのやら少し黄色くひらいたのやら
積み重ねられた緑の確かさを
抱き取ってしまう
ああ でも
それだけ焦がれた緑だのに
いざつれて帰り
かたまりの半分をゆでてマヨネーズで食べると
鉢にふたつ三つ残る
あとの半分はゆっくり
野菜室の隅でしおれていく
どうしよう ああこれならと
ささみを削ぎ切り湯がいたのとナンプラーで和えてみても
んん
美味しいにはおいしいけれど
しみじみしない
しっくりこない
「なんだか、ブロッコリーっていうものは
どう食べたらいいのかよくわからないね」
と、つれあいユウキも微妙な顔
そうか やっぱりか
私もだよ
それなら買わなきゃいいのに
緑の引力なのかな
「いつか畑をやりたいな」
とユウキ
ふたりとも食いしん坊なうえに野菜が好きだし
貸し農園でも探してみる?
私は探すだけだよなどと話すうち
瓢簞いや
ひょんなことから
東へ西へ
畑のできる住まいやぁいと呼ばわり呼ばわり
たずねあるくようになり
春が夏になり
あったのだった
大阪北辺の住まい近くをとおる国道の先の先
丹波という土地に
その秋ふたりで
引っ越した
直売所も近くにあって便利
ユウキ
畑をがんばってね
東京の友達とも大阪の知り合いとも
SNSでつながっている
と思うと心づよい
入谷でご近所だった
ヨガ講師で柴犬ママのマミコさんの
料理の写真が美味しそう
きくと最近
志麻さんのレシピ本でつくっているという (*1)
カリスマ家政婦として人気のひとだと
知った
その家の冷蔵庫にある材料で
おお、と唸る料理をつくるアイデアと腕のひと
おお、と図書館でレシピ本を借りてくる
付箋ふせんそしてカラーコピー
どうしてレシピはカラーじゃないと
つくる気がおきないのかな
モノクロコピーだと
仕舞ったままになるんだ
つくれるかもしれないメニューと
食べたことがあるもの
十あまりをコピー
なかになんきんやらブロッコリーやら
野菜をソテーするものもあった
今晩これをつくろうと
レシピをコピーしたりデータを保存したりするとは限らない
これ食べたいたぶん好き
できるかもしれない身体によさそう
そうやって溜まったコピーや切り抜きが
クリアフォルダーからあふれんばかり
束から引っ張り出しては
冷蔵庫の中を思い出し
時々開けてたしかめながら
これかな
これなんかどうかな、いや
ゆうべ鶏だったから
今日は豚か魚で何か、と並べてみる
一枚いちまいは端が折れ
破れかけを再コピーしたものもある
ユウキやきもき
ある日
「よかったらこれ使ってみて
もっとこんなふうにということがあったら
つくり直すよ」と
渡されたバインダー
大まかな食材別に分ければいいように
インデックスまで
二穴パンチで孔あけ
並べ直せば探すのに手間取らないよって
ほんとだね でも
メインが豚肉か鶏むねか
という分け方で綴じても、さ
ピーマンを軸に探したい時
見つけにくいよね
それに
A4サイズばかりじゃなくて
切り抜きやスーパーのラックから選んだカードとか
大小ばらばら
「コピーし直して揃えればいいんだよ」って
そのとおりだけれど
せっかくのバインダーも使えないまま
あふれかけた紙束のクリアフォルダーを持ち越して
こんにちに到る
面目ない
難儀なるかなわたくし
難儀なるかな
流行り病への対策が叫ばれつづけ
四人五人が集うこと
ねっしんに語りあうことももってのほかと
もとめられ
仲間との勉強会さえオンラインになった
そんな日の画面を閉じた午後五時すぎ
ユウキ、急いで何かつくるからね
ランチはつくってくれて洗い物まで
いつもはつくってもらった人が洗うのに
おかげで勉強会に間に合ったから
終わったあとは私が、と
気は急くものの手が遅い
ユウキの好きなホッケの干物おおきいのを焼いて
味噌汁は温めればいいから
そうだブロッコリー、あの
直売所で出くわした
スティックセニョール(*2)
袋づめのがそっくりあるからあれを
すっ と切り落とす
ひと枝
枝というより茎
包丁で
すっ すてぃっく
スティックセニョール、セニョリータ!
ブロッコリーの脇芽を集めましたという袋入りを買ったことがあったから
てっきりこれもそうだと思ったよ
げんこつもしくは緑のブーケは切ると粒つぶが散らばるし洗いにくい
細い茎を束のように詰めてあるのは扱いやすくてうれしい
すっと細く
すっと伸びた
く、き、茎ブロッコリーと呼んでいたら
いまひとつ広がらなくて
しげしげ眺めたのだろうか種の会社のひとが (*3)
すっと背が高いしね そう
セニョール、なんて感じかな
スティックみたいで、いやあと半ひねり
ステッキ持った紳士とか
さ
すっ すてぃっく
スティックセニョールって
名づけてみたん
かな
などと独り言つ間もなく
すっと細い すっと長いのを
ざざっとざるに入れ
ざざあっと水換えてもう一度
さらに浄水かけて
ばさっと振る 床にもすこし降る
浅いフライパンにオリーブオイル熱し
にんにくのマッシュつとっ
ややあって
緑のス、スティックセニョールどさどさっ
並べて火を強く そして蓋
グリルにホッケも入れて点火
じじいっ わっ 蓋をとれば
ああちょっと焦げてきてなんだか
ほっこり香る
ね
ス スティック
スティックセニョール 茎のみどりの
焦げるにおいってこんななんだな
岩塩ひとふた振り黒胡椒四、五振り
ハーブソルトもふた振り
ああ あれはどうかな
冷蔵庫からぽん酢つつっ じ じゃあっ
あっ ながれこんでくる
鼻腔の上奥へ
酸っぱからいこれ
「おっ、なんかいいにおい。なんだろ」とユウキ
へへ、なんだとおもう?
「え、うまそうだね
ビールがあいそうだ」
あっ あれっ
あのときカラーコピーした
志麻さんのレシピの中身はわすれて探しもしなかったけれど
こまって急いて
ええい
なんとなくやってみたら
「うん美味しいよこれ」
そうか、こんなのでもいいのかな
紙のレシピのファイリングじゃなくて
眼や頭のどこかに紛れていた残像が
知らずしらず美味しいほうへ誘ってくれたのかな
フライパンの焦げをおとすのでユウキに手間取らせてしまったけれど
「あれは美味しいよね」と定番になり
ス スッ
スティックセニョールを畑でふた株
つくってもらうこととなり
かぶや豚肉と炒めてもシチューに入れてもいいよねと
(つまるところ重宝なブロッコリーということだけれど)
次つぎのびる茎をもいできてもらっては野菜室におさめ
すっ すっくとのび続けるスティックセニョール
濃き緑を頬張りながら
スッ スティックセニョール、セニョリータ!
まだ知らないメニューを探している
*1 志麻さん・・・タサン志麻さん。フレンチ料理店の料理人を経て「予約のとれない伝説の家政婦」として人気の料理家
*2 スティックセニョール・・・ブロッコリーと中国野菜カイランを掛け合わせて作られた茎ブロッコリーの品種の名
*3 種の会社・・・スティックセニョールを開発・販売する会社、サカタのタネを指す
雪ん子のようだと思った。
肌は透きとおるような白さで、真ん丸な眼鏡を通して見える目はくりっとして嘘偽りを知らないで生きてきたんじゃないかと思わせるようだった。
黒くショートカットな髪形もとてもよく似合っている。
彼女と友達になれたらなと思った。
職場の異なる職種の彼女。
フロアこそ同じだが、あいさつ程度の付き合い。
こんなご時世、飲み会もなければゆっくり話す機会もないんだろうなと思っていた。
そんなある日、事は動いた。
職場から徒歩10分位のところに街を一望できる公園がある。
昼食後、そこに散歩に出る人が何人かいるのだが、それに彼女はわたしを誘ってくれたのだった。
やや暑い初夏だったと記憶している。
突然のことで帽子も日傘もなかったので、とりあえずわたしはハンドタオルを頭にかぶせて歩いた。
行きは急な坂が蛇行しているのだけれど、彼女との会話は楽しかった。
この土地へはお互いよそ者同士。
悩みも似ていてなんだかほっとしたのを覚えている。
彼女は都会出身だ。
数年たっても田舎はまだ慣れないと言う。
わりと思ったことは口にするタイプだけれど嫌みが全くない。
自然体の彼女と友達になれたことがなんだかとっても嬉しかった。
世がやや落ち着いていたころ、仕事帰りに一緒にご飯を食べることになった。
わたしがいつも行くような所でいいと言う。
だけどわたしは、うーんと頭の中で悩んだ。
わたしが足しげく通っているのは、昭和感漂う定食屋だ。
70代のおじいちゃんが1人で経営していて、テレビはいつもNHKがついている。
味は申し分なく、揚げ物のセットがおすすめだ。
わたしはこういうお店が落ち着くので好んで通う。
だけど・・・・・決してお洒落ではないし、都会出身の彼女に本当にいいのかな。
少し迷ったけれどやっぱりここにすることにした。
彼女は予想に反して喜んでくれた。
店主もいつも通りニコニコと迎えてくれた。
初めこそちょっとよそよそしかったけれど、だんだんと会話が盛り上がった。
彼女は人知れず悩みを抱えていた。
わたしも悩みはある。
同世代どうし、その悩みをアウトプットすることで心の奥の何かがホロホロとそぎ落とされていった。
大人って難しい。
勉強さえしていればよかった学生とは違う。
なんだかとっても生きづらいなとモヤモヤすることが漫然とある。
そんな中でのこの定食屋でのひとときは生涯忘れないだろう。
その後我が家で一緒に飲んだほうじ茶の味も忘れない。
何もない我が家をモデルハウスのようだと驚愕していたあの悲鳴にもにた感想、断捨離を伝授してほしいと懇願された時の真ん丸に見開いた目、向かいの家の自転車屋の親父がご飯たべているところを一緒にくすくすと笑いながら観察していたあの瞬間、ドラム式洗濯機の楽さを伝えたときの真剣に耳を傾けるあの表情。
ずっとずっと覚えている。
物理的な距離ができたとしても、きっと。
この文章が公開される頃、彼女は都会の実家近くの病院のベットの上だ。
初めてのオペにものすごく心細い気持ちになってるはずだ。
面会も制限されているだろう。
いつもと違う白すぎるベッドのシーツ、見慣れない窓からの風景、毎日変わる病院のスタッフ、決して美味しいとは言えない食事、心はきっと落ち着かないだろう。
あなたにこの文章を送る。
寝て起きたら全て、きっと思い通りの結果になってるはず。
また屈託のない笑顔を見たいよ。
健闘を心から祈る。
高い塀の上に 有刺鉄線がめぐっている
一帯はどんよりと暗くまるで小さな森のようだが
塀の中から伸びるのは木ではなく
どこまでも高い鉄塔だ
両腕を水平に伸ばして掌を上に向け
巨大な 孤独な 体操選手のようにまっすぐに
黒い 冷たい空気の中に そびえている
「◯◯変電所」というプレートが貼られた街道沿いの入り口とは逆側に
この塀の中に入る別の小さな口があり
従業員の自転車が1台だけとまる
その口から 午後4時を過ぎたころ
小学生の女の子がひとり、またひとりと、塀の中へすべりこみ
鉄塔脇にある粗末な小屋の中に集まった
小屋は電気がなく薄暗い
「じゃあ、やろっか」
年長らしい子がひそひそ声で言うと
少女たちはスカートをはいたままパンツを脱ぎ
両膝を立ててしゃがんで 股を広げた
暗がりの中で 少女たちは自分の股をのぞきこみ
それから見せ合いっこをする
年長の子が床に顔をすりつけ 一人一人の股をいじくりながら評価する
少女たちはくすくす笑いながらそれを聞いた
「皺だらけのおばあさん」「納豆のにおい」「おトイレの紙が残ってくっついてる!」
酷評を受けるたび 少女たちは大笑い 股たちも一緒に笑って揺れ 尿がこぼれた
この単純な 遊びともいえない遊びを
少女たちはくりかえし くりかえすために何度もその小屋に集まった
学年も クラスも違い 名前も知らない 友だちですらない4人だった
厳重に目隠しされた塀の中で 変電所は24時間コソコソと働き
地域の家に 会社に 公共施設に そこで暮らす人間たちに 「でんき」という魔法をかけるのだった
その魔法からするりと抜け出し
少女たちはその 同じ秘密の塀の内側の暗がりで
灯りの下では見えないものを見て
それからゆっくりパンツをはいた
別れる時振り返り、どこまでも高い鉄塔を見上げ
「これ、寒そうだよね」
そんなことを言って思わず
足を広げ手を水平にのばして掌を上に まっすぐ冷たい黒い空気に立つ
股とパンツの間に入りこんだ冷気が 少しずつあたたまっていくのを感じる
それから それぞれの魔法の家に帰っていく
(1月某日、奥戸3丁目変電所裏で)