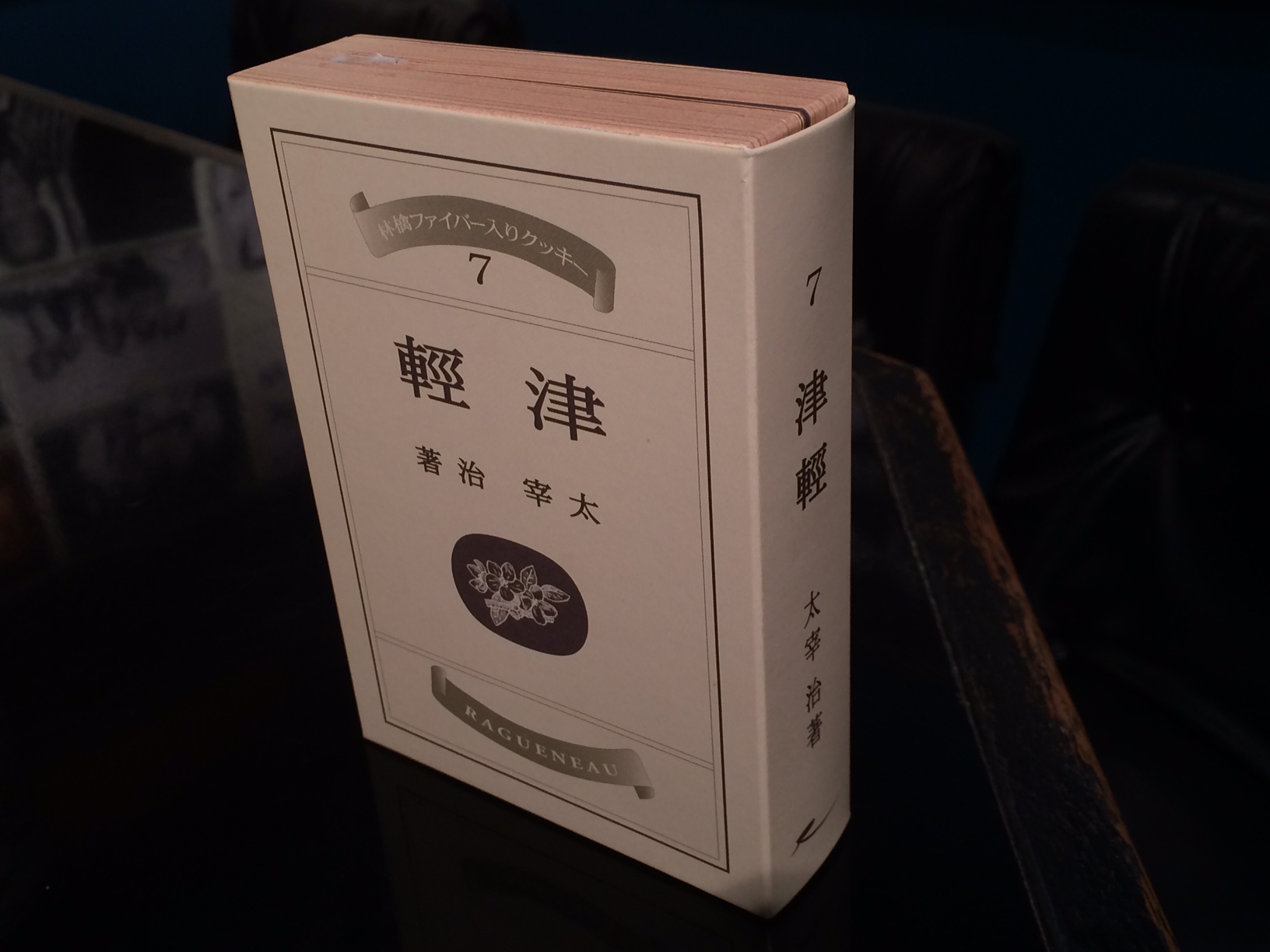根石吉久
結局何をやってきたのだろうとときどき思う。
若いとき、詩を書いたことがあったが、あれは詩だったんだろうか。もしかしたら、日本語を使った語学みたいなもんじゃなかったんだろうか。日本語で何か書いてみる練習みたいなことをしたんじゃないだろうか。
大学に入った頃に、自分が文章を書けないことに気が付いたのだった。書いてみると、書きたいことと言葉になっていくものとが、ずれる。いまだ言葉にならないもの、言葉にならずにもがくものと、実際に言葉になっていくものとが、ずれる。ずれるというより、もっと差がでかい。時によっては、うらはらじゃないかと思うくらいに違うものが出てくる。
一致することがあるのかと思った。学校じゃ、思った通りに書くだとか、考えたことを素直に書くだとか言っていたような気がするが。
考えたとして、考えたものはもう言葉になっているのか。言葉以前のものか。その両者が混ざり合ったものか。どうも混ざり合っている。ときどき言葉の断片みたいなものが動くが、シンタックスは待機状態であり、言葉の断片以外に動くものは、「充実したからっぽ」みたいなものだけだ。まだ言葉にならないが、言葉になる直前のもの、もがくもの。
言葉になろうとするものは動きはするようだ。この状態で思った通りに書くだとか、考えたことを素直に書くだとかはありえない。
「充実したからっぽ」をどう言葉に変換させるのかがあるだけだ。変換させるとき、「充実したからっぽ」がどこかを通る。どこを通るのか。
「充実したからっぽ」は、言葉というより言葉の芽みたいなものだ。まだ具体的な言葉ではない。同語反復みたいだが、からっぽというのは、言葉としてからっぽなのだ。具体的な言葉ではないから「からっぽ」なので、何かに充ちていたり、もがいたりする。
それが、どこかを通るようだ。一番わかりやすい言い方は、意識の浅いところ、中間のところ、深いところという3つくらいの層を言ってみることだ。あくまでも便宜的にそう言ってみるだけで、本当のところは何を(どこを)通るのかよくわからない。
新聞記事などを読むと、こういうものは意識の浅いところを通っただけの文章だなと思う。意識のもっとも深いところを通った言葉は、詩の言葉ではないだろうか。それよりもっと浅いところに、各種散文の言葉の出所があるのではないだろうか。
浅いところを通った言葉ほど、言語に攫われている。「人攫い」という言い方があるが、言語による「言葉攫い」が行われるのだ。新聞記事などを読んでいるとそう思う。言語は、シンタックスであり、構造であり、規則であり、言葉にとっての死でもある。
法律の条文などを読んでみれば、そこに言葉を感じることはない。こりゃあ、言語にすっかりやられた後の何かだと思う。用語が普通には目にしないようなものだから難しそうに、偉そうに見せかけているが、言葉としては最下等のものだ。その下等な質を水で薄めると、パターンに犯された新聞記事その他ができる。
この種の文は、「充実したからっぽ」が何かを通ったものだということはない。それが、あらかじめない。最初から、シンタックスや構造が記者に「書かせている」。記者は自分が書いているつもりなのかもしれないが、書かせられているのだ。新聞記事特有のシンタックスや構造やパターンというものがあり、それらが記者に「書かせている」のだ。何の事件について書こうと、もう最初からなにごとかが決まり切っているのだ。
新聞記者たちが、記者クラブという名前だったか、どこやらに集まって、警察の発表をそのまま記事にしてしまうのは、新聞記事の性質に根がある。言葉から遠く、言語に近い新聞記事の書記の性質には、疑う力を奪い、うすら馬鹿を作るものがある。記者をも読者をもうすら馬鹿にしてしまう性質がある。
新聞記者がうすら馬鹿にならないためには、記事を書くかたわらで、たとえ発表しない手記のようなものでも、意識の深みを通る言葉を書き続ける作業を手放すわけにはいかないのだが、不毛な忙しさの中でそれを確保する者の数はまるで少ないだろう。圧倒的にうすら馬鹿の数が多くなるだろう。
やっぱり、書こうとしたものとは別のものを書いている。書き始めた時、新聞記事のことなど書くつもりはまったくなかったのに、新聞記事のことなど書いている。そういうことが起こるのは、私の場合は、考えに枝葉が生えるからだ。生えたら繁茂させてしまうからだ。
やはり、書かされているのか。
学校で作文を書かされたことはあるが、いやいやながら何か書いた。何を書いたかすべて忘れた。書きたくて書いたわけではないから、何を書いてもよそごとというか、他人事というか、他人になって何か書いていたのだと思う。なんとなくこんなふうに書けば、よい子でいられるのだという感じだけはあって、作文を書いている間は、他人としてのよい子をやっていたのだと思う。しかし書いたものは、すべて忘れた。
一つ思い出した。
小学校の何年の時かは忘れたが、炬燵で宿題の作文を少し書いて、全然字数が足りなくて、続けて書くことがなくて、困っていた。親父がどういうわけかのぞき込んで、「俺が書いてやる」と言ったのだった。そんなことは前にも後にもない。親父は私の勉強なんかに興味を持ったことはなく、宿題だの作文だのにも関心はなかったのに、その日だけは違った。いや、その日だって、私の宿題や作文に興味があったのではなく、私が書きかけたものが牛についてのことだったからだ。
その頃、家では牛を飼っていた。乳牛ではなく、農耕用の牛だった。田植えの前に田の土を起こすのに、牛に鍬を引かせたのだ。牛のことはぼんやりと覚えている。全身が黒に近い茶色だったような気がする。
牛の出産の時のことの方が、牛の姿よりよく覚えている。祖母と母がお湯をわかして、大量のぬるま湯を作ったりしていたのは、生まれる牛の子を洗うためだったのかどうか。親牛の尻から(尻だと思っていた)子牛が下半身だけ出ている状態のことも覚えている。獣医も来ていて、大人の男二人で、子牛の体を持ってひっぱり出そうとしていたのも覚えている。ちょっくら出てこなくて、男二人は汗をかいて本気だった。なんとか無事にひっぱり出すと、子牛は小さい牛だった。かわいいと思った。
子牛はすぐ立てたのだったかどうか。しばらくは藁の上にでも寝ていたのだったかどうか。なんだかよろよろしているが、立っている子牛を見た覚えがあるような気がする。よろよろとして、やっと立っていた感じを覚えているような気がする。大人たちが子牛の体を洗ってやっているのを見た覚えがないから、祖母たちが作ったぬるま湯は母牛の膣を拭いてやるためだったのかどうか。私は人間のやる仕事をろくに見ていなかった。生まれてきたものが小さいのに完全な牛であるのを見ていただけだった。かわいいと思った。
子牛が雄だったら、子牛が売られていく。子牛が雌だったら、親牛が売られていく。とにかく、家には雌を残す。また子を産ませるために雌を残す。
作文には、親牛が売られた日のことを書いたのか。親牛が売られてからそんなに日数は経っていなかっただろう。
牛の世話は親父がしていたのだろう。餌をやり、糞の始末をやり、土手草を食わせるために、朝と夕に、家と土手の間を往復する時は、鼻輪につないだ細綱を親父が持って、牛が歩くのに合わせて、一緒に歩いたのだろう。だろう、だろうとやたら書いてしまったが、親父が牛と一緒に歩いているのを見た覚えがないのだ。見た覚えがないのに、親父と牛が一緒に歩く速度はわかるのだ。
子供の頃、私は「トヤンとした子供」だったそうだ。トヤンとした状態は、ぼうっとしている、放心状態になっている、心ここにあらずの状態であるということである。そのせいかどうか、とにかくいろいろのことをどんどん忘れた。とにかく、ほとんどのことが後に残らないのだ。残るわけがない。トヤンとしている子供には、外部というものが入ってこないのだ。入ってこないものを忘れることはできない。だからどんどん忘れたというのは、仮構された記憶であって、実際はただただぼうっとしていたということなのだろう。ぼうっとしている子供には、自分がぼうっとしているという自覚もないので、幼少の自分や小学校時代の自分というものは、ゆらめくかげろうそのものだ。意識に閉じこめられて、ただゆらめいていたのだ。何かよっぽどせつないことでもあったのか。
記憶というものは、果たして一つ二つと数えられるものかどうかわからないが、もし数えられるなら、私は人々の標準と比べて、圧倒的に数が少ないと思う。
今は、歳をとって、脳梗塞をやったり、脳虚血発作をやったり、そんなものをやらなくても、人の名前を忘れたり、階段を降りていく途中で、なにをしに階段を降りているのだかわからなくなったり、もうやたらと忘れたり、ものがわからなくなったりするが、子供の頃から、なにもかもどんどん忘れていくことは着実にやっていたのだ。仮構でもいい。とにかく私はどんどん忘れた。つまり世の中のことを忘れていた。
作文だって、唯一覚えているのは、その内容や文章ではない。私が書きかけていたものをのぞき込んだ親父が、俺が書くと言ったので、びっくりしたから、そのびっくりしたことを覚えているのだ。作文を覚えているのではなく、作文にかかずらった親父を覚えているのだ。
そうじゃなくて、あれは最後の牛が売られた時だったのかもしれない。いつからか、家には牛がいなくなった。あの時がその時だったのではないか。
子牛が生まれた後、親牛が売られたのなら、さびしい気持ちはあっても、子牛の世話をすることで紛れただろう。あれは、子牛が生まれた後に売られたのではなく、牛を飼うのをやめた時のことだったのかもしれない。そういう暮らしの変化なども、私はものごとに関連づけて覚えるということがないのだった。
いずれにせよ、親父はさびしかったのだ。長年牛と暮らして、牛がいなくなって、さびしかったのだ。だから、私の書きかけの作文を読んで、「俺が書いてやる」と言い出したのだ。書きたかったのだ。
今になって思えば、親父は私の作文を書いてよかったのだ。書きたい人が書くのが一番だ。私は書きたくはなく、どちらかと言えばおっくうでいやだったのだから、親父が書くのがなによりである。
それからまた一週間とか二週間がたった。学校の教室で、先生が私の名前を言い、いい作文だとほめてくれた。そうだろうと私は思った。親父は書きたくて書いたのだから、いい作文を書いたに違いない。親父が書いた作文を読んだのか読まなかったのか、それさえ私は覚えていない。牛が車に積まれて行ってしまったのか、他人に鼻輪を引かれて歩いて行ったのか、それさえ私は覚えていない。その両方がイメージとして記憶になっているのであり、どっちかと決める手がかりがない。
親父は何を書いたのか知らないが、字の手癖はどうしたのだろう。トヤンとした子供が書くような幼い字を親父が書けたはずはない。親父が別の紙に書いたのを、私が作文用のノートに書き写したのか。親父が口述するのを私が筆記したのか。しかし、そんな複雑なことをした記憶もない。なんにせよ、私はその作文を読んだ覚えがないのである。よくやったぞ、とうちゃん、とは思ったが、作文自体には興味はなく、何がどう書かれていたのかが全然わからないのである。
親の心というものは、子供にはわからないものである。
だいたい小学校3年か4年の頃だったと思うが、3年生なら3年生が、牛が売られていく日に何を見て、どう思ったかを親父は創作したのだろう。そういう創作をやって、淋しさを紛らわせたのだろう。わけもわからないほど激怒して怒鳴りつけるとき以外は、感情というものは見せないのである。
息子の作文の代筆をやった親父も親父だが、その作文を褒められて、自分が褒められたかのように、へへへなどと言っていた息子も息子である。
それが学校時代を通じて、作文について私が覚えている唯一のことだ。作文はたくさん書かされた覚えはあるが、ものの見事にすっからかんである。
私は19歳の時に、語学をやった。語学ばかりやっていた。半年ばかり、世界史の暗記をやり、それだけで大学に入った。国語というのもあったが、ほとんど何もやらなかった。高校の頃、国語だけはできて、廊下に名前が張り出されたりした。どうしてだろうと考えたら、思ったことを書かないからだなと気づいた。設問者がどう書かせたがっているのかを考えて、こういうふうに書かせたいんだろうと思って書くと点がいいのだった。自分の考えを書くのではない。設問者の考えを書くのだ。ある日、俺はいやなやつじゃねえかと思った。文章そのものを読んでるんじゃなくて、いや、それもやることはやるが、何よりも設問者の腹を読んでるだ。ろくなもんじゃねえ。自分をそう思った。自他共にそうであると思うので、今でも国語の点が取れるようなやつはろくなもんじゃねえと思うのである。
あの頃、語学がなんであんなに面白かったのだろう。
四六時中英語をやっていた。寝て起きて、英語をやって寝るという感じで、一日に15時間くらいやっていたんじゃないだろうか。半年以上かかったが、代々木ゼミナールという予備校の模試で、3万人中3番くらいになった。半年前までは、3流受験校の250人中240番くらいだったのだから、面白がってやると、がらっと変わってしまうもんなんだなと思った。
語学が面白かったのは、イメージが面白かったのだ。
英単語一つでも、日本語を媒介にしてイメージを作り、イメージを独在させて日本語を脱ぎ捨てるようにしていると、こういうものって初めて出会うな、というものがやたらにある。つまりは、イメージというものが作れるということ、作ってみるとそれまで知らなかった珍しいものができるということ、それが面白かったのだ。こういう言語を使う人たちのアタマの中は、こんなふうに動くのかということもうすらぼんやりとだが推測できる。これは、全然違うな。こんなふうな考え方で何か考えたことは全然ないな、こりゃ面白い、全然違うので面白いと、面白がってやっていたら、どんどん点があがったということで、英語をやっている間は大学入試のことは忘れていることが多かった。大学入試で要求されることがないようなこともやった。今から考えるとずいぶんおかしな音も混じっていたのだが、口の動きを鍛え込むようなことをやった。大学入試用に限定しないでやったら、結果的に大学入試用の点が伸びたので、本当にやったことは、面白がるということだけだった。
その後、大学に入って、自分は文章が書けないんだなとわかったのだった。それがわかったのは、語学をやったせいだと思っている。語学をやらなかったら、新聞記者かなんかになって、与太を書き散らしたかもしれない。言語に書かされるコトバをコトバだと欺いて、欺いていることにすら気づかず、欺かれていたかもしれない。お利口なあいつらのように。
言語は死だ。
幼少時にその死を内在させてしまうのが人間だ。
いや、そこから言葉が芽吹くかどうかだ。
人間は姿形のことじゃない。芽吹きのもがき。それが言葉にならないまま、発芽玄米のように食われてしまっても、芽吹きがもがいている時間は、そこに人間がいる。
学校の勉強がよくできたようなやつには、意識の表層だけをさっさと流れる言葉もどきを書くものが多い。
親父は、何を創作したのだったか。
創作したのだったら、ずいぶん手の込んだことをやったことになるが、あの親父にそれができたのか。
親父がとうてい学校の勉強ができたとは思えない。
なにしろ、激怒する時以外は、大人のくせにトヤンとしているのだ。はしこさがまるでないので、お袋は時に地団駄踏むようにくやしがった。
言語は欺く。言語は導く。
やってみなければ、言葉が芽吹くかどうかはわからない。
私は親父のことなど書く気は全然なかった。
いつのまにか書いていた。
牛のことも。
さて、タイトルを考えよう。
考えた通りに素直に書いてみよう。
一度くらいは、先生に言われた通りやってみなければ。