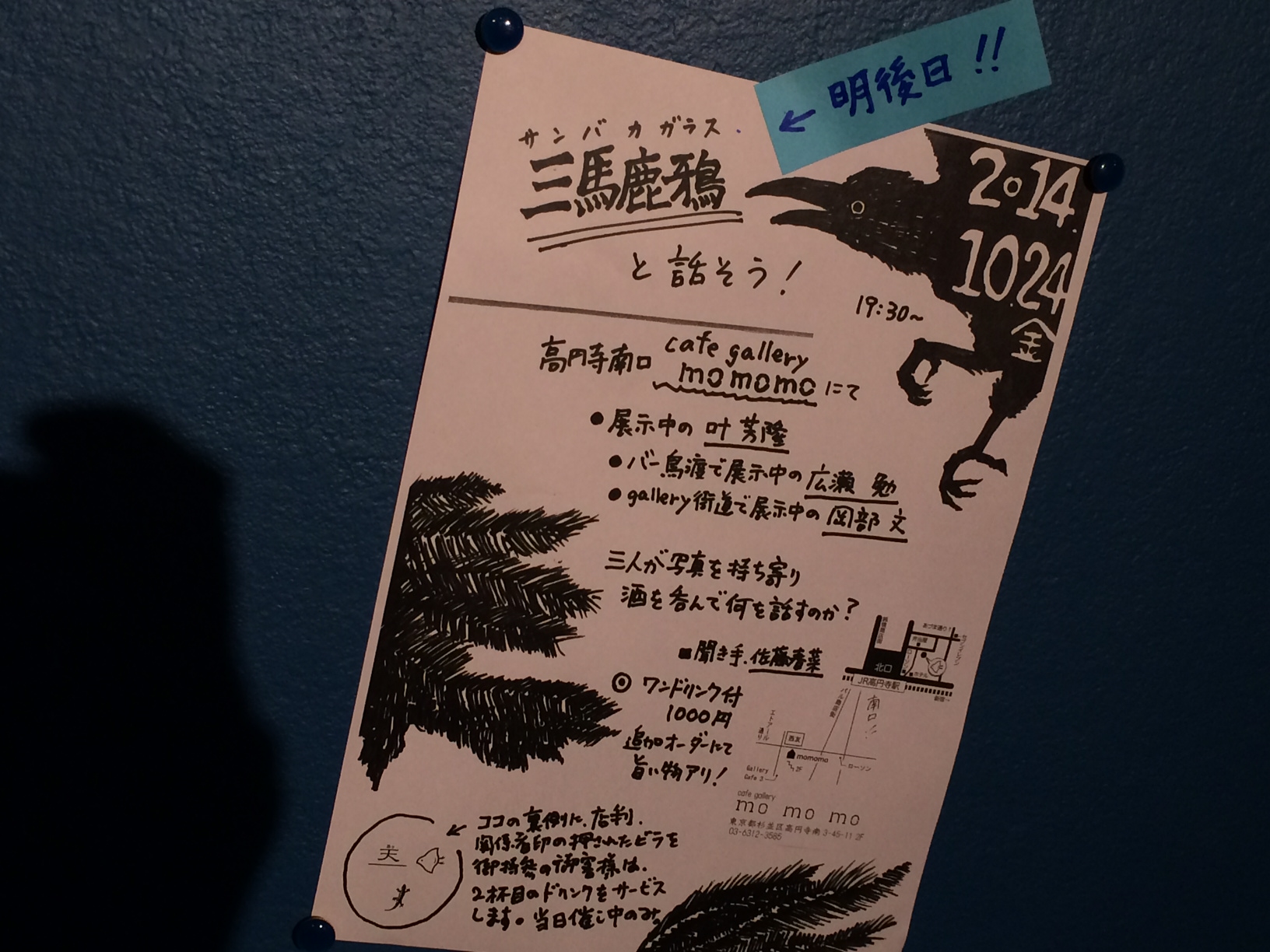佐々木 眞
西暦2013年卯月蝶人酔生夢死幾百夜


眉目秀麗な彼は、若者を代表して「風次郎」役に選ばれた。
この共同体のトップモードをさし示すという重要かつ誇らしい役目だ。
私は彼の補佐役をおおせつかり、丘の頂上に据え付けられたインカ帝国の祭壇のような席に座ると、古代の共同体の家や畑がアリのように小さく見渡せた。
全身紫ずくめの奇妙な恰好をした「風次郎」はすっくと立ち上がり、「これが俺たちの新しい制服だあ!」と叫ぶと、しばらくしてその声は、こだまになって帰ってきた。
絢爛豪華な着物の裾から手を入れて、豊かな乳房を鷲づかみすると、彼女は厳しい目で私を睨みつけたが、かといって、自分から逃れようとはしないのだった。
まだ春だというのに、夏型の大きなヒョウモンチョウが、原っぱをゆらゆら漂っている。この品種らしからぬ緩慢な動きだ。しかも巨大なヒョウモンの翅の上に別の種類の小型のヒョウモンチョウが乗っている。
私がなんなくその2匹のヒョウモンチョウを両手でつかまえ、これはもしかして2つとも本邦初の新種ではないかと胸を躍らせていると、半ズボン姿の健君も別の個体を捕まえて、うれしそうに私に見せにきた。
それは確かにヒョウモンチョウの仲間には違いないが、いままでに見たこともない黄金色に輝いており、国蝶のオオムラサキを遥かに凌駕するほどの大きさに、興奮はいやがうえにも高まるのだった。
私たちはバタバタと翅を動かしてあばれる巨大な蝶を、懸命に両手で押さえつけていたのだが、それはみるみるうちにさらに大きな昆虫へと成長したので、もはや彼らを解放してやるほかはなかった。
しかし巨大蝶は逃げようとせず、その長い触角をゆらゆらと動かし、「さあ私のこの柔らかな胴体の上にまたがってみよ」、とでも言うように、その黒い瞳で私たち親子をじっと見詰めたので、まず半ズボン姿の健ちゃんが、ひらりと巨大蝶の巨大な胴体の上にまたがった。
息子に負けじと私も別の巨大蝶にまたがり、そのずんぐりとした黒い胴体をつかんでみると、あにはからんや、それはくろがねのような強度を持っていた。
私たちがそれぞれの大きなヒョウモンチョウに騎乗したことを確かめると、2匹の巨大な蝶はゆっくりと西本町の子供広場から離陸し、狭い盆地を一周すると、見はるかす下方の片隅に、見慣れた故郷の街や家や寺や山、銀色の鱗に輝く由良川の流れが見えた。
それから巨大な蝶は、猛烈なスピードで故郷の街を遠ざかり、波がさかまく海をわたり、大空の高みを力強く飛翔しながら成層圏に達し、そこからまた猛烈なスピードで下降した。
ぐんぐん地表がちかづいたので、よく見るとそれは教科書の写真で見たことのある万里の長城だった。気がつくと巨大蝶の姿は消え、私たち二人だけが大空の真ん中にぽっかりうかんでいる。私たちは思わず手と手を握り合った。
しかし墜落はしない。無事に飛行は続いている。私たちはそのまま元来た空路をたどって故郷に帰還すると、そこには仲間の巨大蝶が勢ぞろいしていた。
その後蝶たちは、住民の飛行機としての役目を半年間にわたってつとめたのちに、南に帰っていった。
私は岡井隆ゼミに出ている学生なのだが、前回は風邪で欠席したので今日の内容が全然わからない。先生がもう一人の女子学生に動詞の活用や終止形について親切に教えている姿を、私は妬ましく見詰めていた。
私が生まれて初めて撮った映画「福島原爆」は、青空に放り投げられた無数の魚たちの骨がレントゲン写真のように透けるシーンから始まる。
1945年3月11日、米軍のB29特別爆撃機は、東京に投下するはずの原爆を誤ってこの地に投下したのだった。
当然現地ではその後の広島・長崎と同様の凄まじい惨禍をもたらしたが、幸か不幸かそこは無人の海岸だったので、当事者である米軍と日本軍、近くに住む一握りの人々を除いて広く知られるところにはならなかった。
それは恐らく日米両政府の陰謀によるもので、彼らはこの大事件を知る者がいないことを利用して長い年月に亘って秘密を隠ぺいしていたが、はからずもこのたびの震災による放射能流失で恐るべき実態が明るみに出されたのだった。
大学1年生の私が文学部へ行こうとすると、法学部の2人の学生が「そっちじゃない、こっちだ」と無理矢理別の路へ連れてゆこうとする。
しばらく成り行きにまかせていた私だったが、腹に据えかねてそのうちの強引な一人を押し倒し、ボコボコにしてやると、そいつは動かなくなってしまった。
私たちはさまざまな外界の現実音を採録してから、このスタジオに集まった。
お互いにその音をダビングしあって新しい電子音楽を創造しようと試みているのだが、A子だけはなかなかその複写を許そうとしなかった。
夢の中でやっと会えたというのに、A子ときたら昔とおんなじことをいうのだ。
「ダメダメ、でも奥さんと別れる気があるなら私に触れてもいいわ。」
広報課長と部下の女性が、その企業の重要な記者発表をどちらが行うのかで微妙な駆け引きを演じていた。
実力と自信のある女性は、自分ですべてを担当したいのだが、無能な管理職がそれを阻止しようと、しきりにいやがらせをするのだ。
ラスカルという名のロシア男は、自分は音楽と体操のたいそうな名人であると吹聴しながら、私を小馬鹿にするように見詰めた。
知り合いの女性が企画したダンテの「神曲」の煉獄観光ツアーが好評だというので、私も参加させてもらった。
原作を(もちろん翻訳で)読んだ時にはじつに退屈な脅迫による宣教本に過ぎないと思って馬鹿にしたものだが、実際に現地を訪れると大迫力で興奮した。
流行の最先端をゆくこのデザイン事務所で、あろうことかシラミが大繁殖。
あれやこれやの方法で駆除しようと試みたが、どうしても出来なかったので、スタッフ全員が地下の暗渠に投げ込まれ、東京湾の藻屑と消えた。
その囚人が不敬な言葉を吐きだす度に、その巨人は自分の目や耳にガムテープを張って見ざる聞かざるを決め込むのだが、それは怒りに駆られた彼が、囚人をひねり殺してしまわないためだった。
我ながらいい短歌が出来たと思ったので、いちど毎日新聞に投稿しようと思った。けれども私は毎日は取っていない。急いで近くのミニストップに行ってみると、ほとんどがスポーツ新聞で、私の大嫌いな産経と読売はあったが毎日も東京もなかった。
私の狭い家の中には、なぜだか広告代理店の人間がいっぱい押しかけてくるので、いつも牛ぎゅう詰めになっている。
その大半が私の知らない顔だが、電通の長谷川という男は良く知っていて、いつでも挨拶を交わす仲なのだが、その長谷川がときどき白い犬に変身してしまうので困る。
東北から北海道を制覇するんだということになり、おじに率いられてわたしも新幹線に乗り込んだのだが、途中で検札に引っかかった。
切符をおじに預けていた私は、途中の駅でつまみだされ、全員集合に間に合わなかったのだが、それはおじの陰謀だったのかもしれない。
ようやく青森につくと、私はおじの運転するロールスロイスに乗せられた。
おじは大通りで車を停めると、交差点の向こうにそびえる教会堂に向かって巨大な鏑矢を射た。それはひゅるひゅると音を立てながら飛んでいき、鐘楼に突き刺さった。
砂漠の族長が私たちに与えたのは、真っ白い包帯でグルグル巻きにされた2つの物体だった。その包帯を時間をかけて解いていくと、ひとつからは人間の姿かたちをしたきらめく黄金、もうひとつからはいままで映画の中でも見たことが無いようなイスラム風の絶世の美女が姿を現した。
演奏会の度にステージに立って、「私たちを警察に突き出して、「あいつらはもしかして殺人犯ではないか」と報知してほしい。そうすれば3人とも無罪であることが明明白白になるから」と聴衆に告げているのだが、笑うばかりで誰もそうしようとはしないので、いつまで経っても私たちの心は晴れないのだった。
ついさきおととい、髪も髭もぼうぼうぼうできたない乞食のような中年男が、ヴェネチアの運河のほとりをほっつき歩いていた。
ところがまさにその男が、今朝のミラノでのMTGにトム・フォードのスーツを一着におよんで、にこやかに私の右手を握ったので驚いた。
広場には大勢の人たちが集まっていたが、彼らの表情には不安の色が浮かんでいた。
そこで一計を案じた私は、仲間のドイツ人たちと一緒に広場に乗りこんで、彼らを落ち着かせようとした。
身軽なドイツ人の若者は、音楽に合わせてマイケル・ジャクソンを凌駕する完璧な幽体移動の必殺技を繰りだすと、次第に暗欝な雰囲気が崩れて笑顔が戻って来た。
そこではいままさにアジア、いな世界最大の万博が開催されており、広大な会場には自然館と商品館の2つの球形のパビリオンが並んでいた。
自然館はそのまま地球の7つの大陸がそっくり内蔵されており、商品間で買い物をした大勢の客たちは、レジを終えるまでに数時間も待たされていた。
久しぶりに妻君と旅行に出かけたが、同じ車両の中に彼女に会わせたくない女性が2人も乗り合わせていることが分かったので、私はもはや旅行気分などどこかへ吹き飛び、戦々恐々として目を泳がせているのだった。
会社の図書室に配属された私が、その狭い部屋に行くと、山口君の姿が見えない。
きょろきょろ探していると、彼と事務の女性の2人が、狭い部屋に山積みされた雑誌類の上に机を置いて執務していたので、「ここは図書室なのだろう。誰か借りに来るのかい」と尋ねたが、誰も一度も来ないという。
国家教育局に続いて、国家映画局の統制がはじまった。
どんな映画も、あの暗黒の1940年代と比べてもハンパなく検閲されている。
本編のみならず予告編や広告の映像やキャッチフレーズについても、官憲の気狂いじみたきびしい統制が繰り返されるので、私は映画界から逃走することにした。
客の要望に応えてクラシック音楽を流している純喫茶を訪ね、私はフルトヴェングラーが指揮する「トリスタンとイゾルデ」をリクエストするのだが、どの店に行っても第3幕第3場でイゾルデが歌う「愛の死」の箇所のレコードが無い。
もうすぐ朝がやってくるので私は焦った。
中国本土を侵略中の皇軍兵士を慰安すべく、私たちはサーカスのキャラバンを組んであちこちを巡業していた。そのとき突然敵が来襲し、銃弾が飛んできた。
私はとっさに私がひそかに好いている女性のほうを見ると、彼女は巧みな宙返りで敵弾を避けていた。
そろそろ死期が近づいてきたことが分かったので、私はそのためにあらかじめ準備していた眺めの良い場所にやってきた。
ところが緊急時に使用するための人工臓器が無くなっているので、きょろきょろ周囲を見回すと、悪戯そうな瞳の若い女と目が合った。
電車から降りて無人の改札口を出たところで、前を行く白いチョゴリを着た若い女が幼女と共に道端の渓流に飛び込むのを目撃した。
私は一瞬躊躇したがザブリと川に飛び込み、まず少女を救い、次いでぐったりとなった女を胸に抱いて水から引きあげた。
蒼白の女は、眉が細く美しい容貌をしていた。
私が「しっかりせよ」と声を掛けても目を開かず、一言も発しないので、盲目かつ聾であることが分かった。
娘とも妹ともおぼしき少女の泣き声だけが、白昼の荒野に響いていた。
「ほら、ほら、ほら」と言いながら、みんなは吉田君からもらった異様に大きな林檎を私に見せつけた。
きっと私の分は無いのだろう。
悲しい気持ちに沈む私の傍を、思いがけず昔の思い人が通り過ぎていった。
なにも言わないで。
私の両側には、2人の女が横たわっていた。
これって前に読んだ村上春樹の小説とおなじシチュエーションだなあ、と思ったのだがそれ以上なにも起こらず、朝になると誰もいなかった。
追い詰められた私たちは、階段を登ろうとしたが、その階段は途中で終わっていたので、階段のたもとまで下って、階段の左の脇道を進もうとしたのだが、そこでにっちもさっちもいかなくなってしまった。
私の顔の前に彼女の顔があった。ので余儀なく私は彼女を抱いた。
金曜日の朝、渡辺派がいよいよ私を粛清しようとしている気配を察知した私は、大聖堂めざして急な坂道を駆けのぼった。
無人の大聖堂をいっさんに駆け抜け、私はその裏道を急いだが、どうも誰かが私の跡をつけているようだ。
真っ暗な小道をひた走りに走ると、いつのまにか異人街に辿りついた。教会では大柄な人々がクリスマス・キャロルを歌っている。
明日は大学試験の初日だというのに、僕たちは夜遅くまで夢中になって話しこんでいた。色々な地方からやって来た受験生の中には、女性体験の豊富な若者もいて、僕らは目を輝かせて、いつまでも彼のレポートに耳を傾けたのだった。
市役所の広報課長はわけがわからぬ男だった。
市に有利な情報だけをマスコミに流そうとして経済、社会、健康、人口、衛生、文化、教育などにかんするありとあらゆるデータの、おのれに有利な部分だけを取り出して、それをごった煮にして公表するのだった。
集英社の編集者に採用された私は、辣腕のヴェテランスタッフたちから軽侮されながら仕事を続けていたが、とうとう編集をクビになって、書籍の荷造り係りに降格されてしまった。
しかしそれでも私は、「なにくそ啄木だって朝日新聞の校正係で妻子を養っていたんだ」と、流星群が降り注ぐ九段坂の夜空を見上げたのだった。