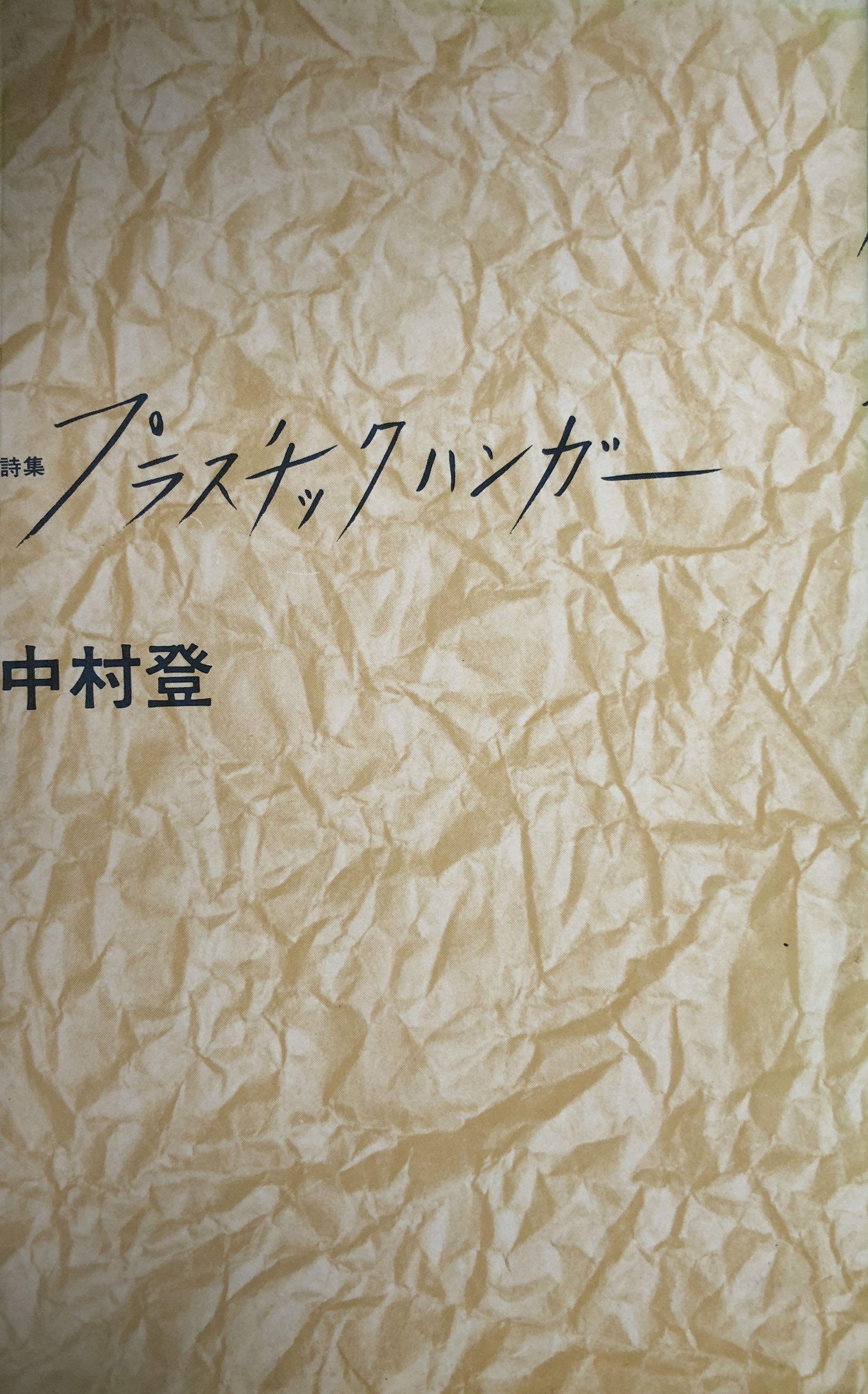今井義行
1 始まり
わたしは、今から「私的な詩論」を試みようとしているが、これは、あくまでも「私の経験」に基づいて書いていくものなので、この論考を書くにあたり、サイトや図書館等で調べたりという事は、行なってはいない。
調べると「ああ、この箇所は、いかにも、きっと調べたんだねえ・・・」という事が、読者に伝わってしまうからだ。後々に述べる事に関係するのだが、わたしは「詩集」は、殆ど読んではこなかった。「現代詩文庫」も、殆ど読んではこなかった。
この論考を書くに際して、わたしが思った事は、わたしは詩を書いてから30年以上経つが、詩に関する散文は殆ど書いてこなかった。わたしは、最近になってわたしが数年経つと還暦になるという事を知って、驚いてしまった。そこで「わたしは、わたしなりの「私的な詩論」を書いておきたい」と思ったのだった。
わたしは、小学生から高校生まで、国語の教科書以外では「詩」を読んだことはなかった。単行本としての「詩集」を読んで感銘を受けたという事もなかった。小学校中学年に、誕生日のプレゼントに、親から「宮沢賢治作品集」を買ってもらった事があった。そこには「童話」の他に「詩」も収められていたが、それらは、独特の文体だった事もあって、途中で読めなくなってしまった。
わたしが小学校中学年の頃に熱心に読んだのは、最近亡くなってしまった、日本のファンタジー作家「佐藤さとる」氏の「コロボックル・シリーズ」というファンタジー作品だった。それは、面白かったので、夢中になって読んで、わたしなりに「コロボックル・シリーズ」を真似て童話のようなものを書いてみたりした。しかし、物語を創作するという事は難しいもので、タイトルばかりは考えたものの、その物語が完結するという事はなかった。そこから「文学というものは難しいものだ。」という、先入観ができてしまったようだ。
しかし、その後、数年経った中学2年生のとき、たまたま、中央公論社編の文庫本「現代詩アンソロジー・上巻」を書店で見つけ、購入し、読んでみたのだった。そこには、戦後から1950年代までの現代詩人たちの代表的な詩篇が収められていた。「田村隆一」氏の代表的な詩篇は、とても格好良かった。また「谷川俊太郎」氏や「黒田三郎」氏といった詩人たちの代表的な詩篇は「何処が、とは説明出来ないのだが、その説明出来ないところが、とても良いなあ。」と感じられるものだった。何よりも、それらは「創造的」であると同時に、とても「解りやすい」詩篇でもあった。わたしはそのときに「現代詩」というものがあると知ったわけなのだった。けれど、その後「現代詩アンソロジー・下巻」を買う事がなかったので、1960年代以降に書かれた詩篇を読む体験は持たなかった。とはいえ「現代詩」というものがあるのだと知ったわたしは、書店で「現代詩手帖」という雑誌を立ち読みしてみた。そして、そこに載っていた詩や論考が、あまりにも難し過ぎて、わたしには、さっぱり理解できなかったので、それから「詩」という文学からの興味は、またわたしから離れていってしまった。
──それから随分と経ってから、わたしは、大学の法学部に進学した。そしてわたしは、法曹サークルではなく「児童文学」のサークルに入り、また童話作品の創作をしてみた。そのときに、わたしは、久しぶりに文学体験をしたというわけである。何故その後に、わたしが童話作品の創作から離れていってしまったかというと、わたしは「児童文学」に関わっているというのに、実は「子供が好きではない。」という事に気づいてしまったからだ。
ちなみに大学生になると、まるで、決められた事のように文豪の作品「罪と罰」のような作品に手を出してみたりするが、わたしは、それら有名な小説を、それなりに読み通しはしたものの、何が「罪と罰」なのだかさっぱり解らず、その内容は、きれいさっぱりと忘れてしまった。
話は戻るが、わたしは高校を卒業してから、大学の法学部に進学したわけなのだった。しかし、わたしは、法曹を目指していたわけではなかったし、公務員を目指していたわけでもなかった。ただ浪人をする余裕が家庭になかったので「将来的に潰しがきくだろう。」という理由だけで、合格した大学の法学部に進学したのだった。この事は、今になってつくづく思う事だが、進学をする場合「どこの学校に進学する。」のかという事が大切なのではなくて「何をやりたくて学校に進学する。」のかという気持ちが、本当に大切なのだという事だ。わたしは今、いろいろな経緯があって、「精神障害者年金」というものを受給しながら、また福祉的なさまざまな支援を受けながら、生活をしている。また、一般的な就労はもうできないため、殆ど寝たきりに近い生活をしている合間に、ベッドで詩を書いて、定期的な通院をしながら、住んでいる地域の「作業所」に通所して、日々を営んでいる。わたしは、精神疾患を持ってはいるけれども、この環境にようやくたどり着いて本当に良かったと感じている。
「作業所」に通所しているメンバーは、30歳台から70歳台までの精神疾患者であり、メンバーは、わたしのように「精神障害者年金」を受給しながら生活をしている人たちもいれば「生活保護」を受給しながら生活をしている人たちもいる。わたしたちは、軽作業をしながら一緒にできたての温かい昼食を取り、月に1回、僅かではあるけれども「工賃」を受け取る。わたしが「作業所」に通所していて思うのは、「作業所」のスタッフがとても心優しい人たちであり、そのスタッフたちが「直接的に社会の役にたちたい。」という動機から、福祉的な仕事を敢えて選択しているという事が伝わってくる事だ。「スタッフたちの給与は、それほど高いものではないだろう。」と察するのだが、スタッフたちは笑顔を絶やさないし、1日を精神疾患者たちと一緒に過ごす。
「作業所」には、割合頻繁に、福祉学校の生徒たちが実習生として訪れて、わたしたちと一緒に一定期間を過ごす事がある。なぜ実習生たちが福祉の仕事に就きたいという考えに至ったのかは、1人1人異なると思うのだが、はっきりとしている事は、高校在学中から「福祉的な仕事に就こう。」と明確に定めていたのであろうという事だ。これは、とても大きい事だ。将来的にやりたい事が決まっていれば、自ずと、どのような学校に進学したいのかが、決まってくるからである。わたしは、わたしに関わることがらを、後悔しない性質の人間だと思っているが、唯一、今、わたしには思う事があって「わたしは、直接、人々を支える事ができる「福祉の仕事」を、なりわいにすれば良かったな。」という事である。
2 「詩作」への入り口
わたしは、大学卒業後、民間の中小企業に就職した。初めの内は、何事も新鮮に感じられたし、やはり、わたしにとって嬉しかったのは、今まで手にした事のなかった給与を受け取る事ができた事である。その給与で、わたしはわたしなりの望むような生活がある程度可能になったし、実家に一定額のお金を渡す事もできた。
ところが、働いている内に、わたしは、1つの事に気がついた。社員の誰もが自分の部署の仕事に邁進しているように見えていたのだが、社員が担当している仕事が完結しつつあるというのに、どういうわけか、上層部の決裁により、簡単に人事異動が行われてしまうという事だ。もう少しで、出来かかっている仕事だというのに、その仕事を奪われてしまって、担当していた社員は「とても悔しい思いをしているだろうなあ。」と思った。そのような事は、わたしには、とても理不尽に感じられた。わたしは「わたしなりの仕事を完成させていってみたいと思っても、簡単にそれを奪われてしまう可能性もあるのか。」と思った。わたしは「何者にも奪われない、自分だけのものを得たいものだ。」と望むようになっていった。
その頃、わたしの勤務地は渋谷にあって、そして、渋谷の駅前には東急のビルがあった。会社から帰宅するとき、何気なく、そのビルの上階に昇ってみた。するとそこには「東急BE」というカルチャー・スクールがあって、講座のパンフレットを眺めてみると「現代詩講座」という講座があった。講師は、わたしの知らない「鈴木志郎康」氏という現代詩人だった。そのパンフレットには、このような事が記されていた。「詩を書いてみましょう。詩を書くと、毎日の生活が活き活きしたものになります。」その文章を読んで、わたしは「これだ!」と直感的に感じたのだった。(結局、生きていく上で最も大切な事は、そういう事なのではないか。)と思った。そしてわたしは、その講座を受講してみる事に決めたのだった。
3 現代詩人「鈴木志郎康」氏と創作仲間との出会い
わたしは、講師の「鈴木志郎康」氏という現代詩人の事は、何1つ知らなかった。そこで休日に神田の書店街に出向いて「思潮社」から出ている「現代詩文庫・鈴木志郎康詩集」という本を買って読んだのだった。けれども、その詩は、よく解らなかった。「解らないのに、講座を受講して大丈夫か?」という思いがよぎったが「とにかく、勇気を出して、受講してみよう!」という気持ちになったのだった。
実際に「現代詩講座」を受講する事となって、参加した初日、教室には、「鈴木志郎康」氏が座っており、その周りには受講者たちが座っていた。講座の進め方は、受講者が予めコピーしてきた詩作品をその場で読んで、感想を述べ合う合評会の形式だった。今でも忘れられないが、初めて参加した日の講座で合評する事になった詩作品は、詩人「北爪満喜」氏の「白色光」という作品だった。わたしは、それを読んで、すぐに「ああ、これは難しいな。」と感じてしまって、感想を述べる順番がわたしに回って来たとき、どうにもならず「・・・パス。」と言ってしまった。そうしてわたしは、他の受講者たちが「北爪満喜」氏の詩作品の感想を思い思いに述べているのを見たのだった。正直なところ、わたしは、面食らってしまったが、その後になって、とても物静かな佇まいの「北爪満喜」氏の使う言葉が、詩の中では、跳ねて動いているように、強く感じられたのだった。わたしには、現代詩というものが、普段使っている日本語から成り立っているにも関わらず、別の構造を持っている造形物として強く感じられて、やや萎縮もしたのだが、やはりその事よりも、現代詩への大きな関心の方が遥かに上回った。そうして「わたしもわたしなりに詩作品を書いて、提出してみたい。」と思ったのだった。
わたしは、その後、アパートの自分の部屋で、わたしなりに、原稿用紙に、初めて「詩」を書いてみた。その初めての「詩」は、現代詩を知らないわたしによる、初めてのものだったので、あくまで、日常的な日本語で書いた「詩」だった。
そのときに、今でも忘れられない出来事が起きた。──ビリビリと、わたしの頭の先から足の先まで、電流のようなものが、激しく突き抜けたのである。そのような出来事は、わたしにとって、今までに1度も起きた事のない経験だった。翌週、わたしは、わたしの書いた詩をコピーして「現代詩講座」に緊張しながら持っていった。わたしは、「鈴木志郎康」氏と受講している人たちに、わたしの書いた詩を配って、わたしは、その詩を朗読した。ぐるりと、受講している人たちがわたしの書いた詩について、感想を述べてくれた。その感想が、おおむね好意的な感じだったので、わたしは、胸を撫でおろし、本当に嬉しかった・・・
わたしは、詩を読む事や詩を書く事から「詩の世界」に足を踏み入れた者ではないけれど「詩の世界」に足を踏み入れて、自分の好きなように、詩を書き始めた。「鈴木志郎康」氏は、講座の中で「詩は、勉強するものではない。」と受講者たちに言った。だから、わたしは、「現代詩文庫」を買い揃えて、貪欲に有名詩人の詩作品を読む事は少なかったし、今では閉店してしまったが、その当時、渋谷にあった、詩の専門店「ぱろうる」で、熱心に詩集を立ち読みしたり、詩集を買ったりする事も少なかった。
それでもわたしは「現代詩講座」を受講しながら、詩を書き続けていく事にしたのだった。何故なら「詩作」は、わたしの日常生活を、とても活性化させたからだ。毎週「現代詩講座」が終了した後も、みんなで、喫茶店に移動して、その日提出された詩作品について、長い時間、感想を述べ合って、その時間も、とても熱気が籠もっていた──
4 「詩壇」というものについて
そうした生活の中で、わたしは、詩の世界には「詩壇」というものがあるらしい、という事を知った。
今、考えてみて「詩壇」というものがあるとするなら、それは詩集の出版社の最大手「思潮社」が形造ってきたものと言って良いと思う。詩集に「思潮社」マークが入ると、詩人として認められるところがあり「思潮社」が発行する「現代詩手帖」の中で、それなりの役割=原稿執筆等の仕事を果たしていくと「詩人は「新人詩人」から「中堅詩人」となり、「中堅詩人」から「ベテラン詩人」になっていくという構造になっているのだ。」と思った。その結果、詩人たちの作品は「現代詩文庫」に収められて、絶版になった詩集も、その中で読む事ができる。「ベテラン詩人」として認知されると、その詩人は、他の文芸出版社からも詩集を刊行していく事にもなり、広くとは言わないが、詩人は、社会的にも認知をされていく。その事は「詩の世界の中での「会社」のようなものだ。」とわたしは思った。しかし、それは、別に悪い事でも何でもない。例えば「中堅詩人」というものは、会社で言うところの「中間管理職」のようなものだと言えるだろう。
わたしは、「鈴木志郎康」氏の紹介によって「書肆山田」という出版社から、第1詩集を出版する事になった。詩集のタイトルは「SWAN ROAD」というもので「現代詩講座」で発表した詩を纏めたものだった。その詩集の出版の打ち合わせのために渋谷の喫茶店で、わたしは「鈴木志郎康」氏と待ち合わせをして、詩集用の原稿の束を「鈴木志郎康」氏に渡して、1通り読んでもらった。「あなたは、今、何歳?」と尋ねられて、わたしは「27歳です。」と答えた。「鈴木志郎康」氏は「第1詩集を出すのには、ちょうど良い年齢だね。・・・でも、この詩集は、あまり評判にはならないかもしれないね。」と言った。
わたしは、その頃「思潮社」から刊行されている月刊誌「現代詩手帖」をときどき読むようになっていて、その12月号は「現代詩年鑑」というもので、その中には、「今年の収穫」という記事があり、それは、その年度に出版された中で、アンケート結果によって、良かったと判断された詩集が、特集されるというものだった。わたしは、その「今年の収穫」を閲覧して、わたしの第1詩集「SWAN ROAD」の名を探したが、たくさんのアンケート回答者の中で、わたしの詩集を挙げてくれた詩人は、2名だけだった。まさに、「鈴木志郎康」氏の予想通りになってしまった。
その後、わたしは、5年後に、主に俳句や短歌の句集を刊行している「ふらんす堂」という出版社から「永遠」という第2詩集を出版し、それからまた3年後に「思潮社」に連絡をして「詩集を発刊したいのですが、引き受けてもらえるでしょうか?」と告げた。すると「はい、解りました。1度、編集部に、原稿を持って打ち合わせに来てください。」と言われた。「思潮社」の編集部は、有楽町線の「護国寺」のマンションの2階にあって、わたしは、原稿の束を持って、発行者「小田久郎」氏の次男である「小田康之」氏に会った。「小田康之」氏は「とうとう、訪れましたね。」と、わたしに言った。
わたしの第3詩集のタイトルは「私鉄」と決まった。12月号の「現代詩年鑑・今年の収穫」に間に合うように、制作を始めたはずだったが、結局、詩集の完成は「今年の収穫」には、どうしても間に合わなかった。「思潮社」から届いた年賀状に、発行者「小田久郎」氏からの1筆があって、大きな現代詩賞の1つである「高見順賞の推薦に1票投じました。」という事が書かれてあった。わたしは「高見順賞」の発表式に出席して、受賞詩集の発表の成り行きを見ていた。その結果、わたしの詩集の名が読み上げられる事はなかった。他の詩集の名が読み上げられたわけだが、そのとき、わたしは、選考委員長が受賞詩人に向かって「壇上から、目配せをした。」のを、はっきりと見てしまった。(こういう事を見つけるのが、わたしはとても早い。)そのとき、近くにいた「小田久郎」氏が「詩の賞なんて、つまらないものだ。」というような事をつぶやいていたのを記憶している。わたしはその後、何冊かの詩集を「思潮社」から出版していった。その行為の中でわたしが考えていた事は「やはり、何らかの「詩の賞」を受賞して、詩人として「それなりの、自分のポジション」を獲得していきたい。」という、言わば、1つの野心であった。しかし、先に述べた、1例としての「高見順賞」のように、何らかの「「詩の賞」を受賞するためには「ある程度有名な詩人との繋がりが、かなり必要なんだな。」と感じてもいて「その事は、あくまで「「個」としての「自分」にこだわって、詩を書いていきたい。」という、わたしの考え方とは、かなり相反する事のようにも感じられた。また、わたしはやはり個人的には、受賞していく詩集での詩の書かれ方や「現代詩手帖」に掲載されている詩の書かれ方の多くには、何らかの大きな違和感も感じていた。すべてとは言わないが、それらの詩の多くは、難解な言葉で造形されていて、ある意味「格好良いじゃないか。」と思わせる部分もあったのだが、よく読んでいくと、「詩人の手つきは見えるのだが、書かれた詩篇からは「人の姿が、何故だか、あまり感じられない。」という事だった。その違和感とは、何だったのだろうか。それは、言葉による「オブジェ」という感じだったろうか?
しかし、言葉によらなくても、美術作品にも「オブジェ」と呼ばれるものは数多く存在する。「オブジェ」という存在を見て、その形に惹きつけられる場合、見た者は、何に惹きつけられてその形を「面白い」と思うのだろうか?・・・わたしには、その「オブジェ」という存在は、ある形を成しているわけだが「その形とは、まず表現者の頭の中に概ねの形のイメージがあって、そこから、表現されていくものなのか、それとも、表現してみようという意識や無意識の中で次第に、ある形が表れてくるものなのか。」という考えを持った、そして「現代詩の形の場合も、そのような2通りのプロセスのどちらかをたどりながら、その形が成り立っていくのだろうか?」と、わたしは、想像をしてみた。
5 現代詩講座での「鈴木志郎康」氏による詩の書き方についての指導の行われ方とその後のわたしの現代詩に関わる足跡
話は戻るのだが「鈴木志郎康」氏の現代詩講座での、詩についての指導の行われ方について、これから書いていきたいと思う。
先に述べたように「現代詩講座」での、講座の進められ方というものは、受講者たちが予めコピーしてきた詩作品を合評会形式で感想を述べ合っていき、最後に「鈴木志郎康」氏が講評を述べるというものであった。そこで大変に印象的だった事は、提出された詩に対して「鈴木志郎康」氏が、いきなり「技術論」を語って詩の添削をしていくのではなくて、書かれた詩には「何らかの欠点」が含まれているわけだが、その詩の作者が、その詩に於いて「一体、どういう事を言いたがっているのか。」という事から入っていって、その実現のためには「どのような工夫が必要なのか。」という形での指導がなされたという事である。そして、この事は「現代詩講座」受講のパンフレットに記されていた「詩を書いてみましょう。詩を書くと、毎日の生活が活き活きしたものになります。」という文言に、まさに符合するものであった。「誰だって、自分が言い表したい事が形になっていく事は、とても嬉しい事ではないか。」わたしは「この指導の仕方は、とても優れた方法ではないか。」と強く感じた。
しかし、その指導の徹底的に厳しい行われ方は、生半可なものではなかった。「詩の作者が、その詩に於いて「一体、どういう事を言いたがっているのか。」という事から入っていって、その実現のためには「どのような工夫が必要なのか。」という事への作者との対話が細かくなされていった。その結果「この詩は、何回書き直してもこれ以上進む事はないから、次の詩へと向かっていった方が良い。」という発言さえあった。また、あまりの指導の厳しさに泣き出してしまう受講者もいた。けれども「ダメなものは、ダメ。」という事なのであった。
「現代詩講座」は、一定の期間を以って終了し、その後も継続して受講するのかどうかの判断は、参加してきたそれぞれの人たちに委ねられる事になるのだが、1期間だけで満足して辞めていく人たちもいたし、指導が厳し過ぎて辞めていく人たちもいたようだ。「鈴木志郎康」氏の指導は大変に厳しいものではあったけれども「もっと上達して、自分自身の書き表したい事を、実現させていきたい。」という参加者たちは、継続して「現代詩講座」の受講を続けていった。わたしも、そのように強く願っていたので、継続して「現代詩講座」の受講を続けていく事にした。
その一方で、受講者たちの有志によって、盛んに詩についての合評会が重ねられて、その結果を「卵座」という同人誌にまとめ、現代詩に関わる多方面の人たちへ発送しては、その反応を楽しみにした。但し、同人誌を発行して、それを、現代詩に関わる多方面の人たちへと発送して、または、逆に発送されてきて、その反応を楽しみにしあうという行為は「詩に関わる人たちの間での循環」ともなる。それは、それで有意義な事なのだが、偶発的に、わたしたちにとって、未知の詩の「読者」との出会い=接点を生み出す事は、稀であった、と言えよう。
わたしは、その後、いくつかの同人誌活動を転々としながら、詩集の出版も盛んに続けた。出版した詩集は、これまでに数冊となったが、今はもう同人誌活動をするつもりもなければ、詩集を出版するつもりも持ってはいない。(その間に、わたしは、46歳のとき、会社という組織の中にいる事がつくづく限界に達してしまって、精神疾患となり、会社組織から追われる事になったのだが、その事は、わたしを、つくづく、安堵させた。)わたしはもう、同人誌活動も、詩集の出版も行わない。この事は、わたしの経済的な状況によるところもあるけれども、もっと積極的な意味合いを持っている。
6 「現代詩」が盛んに読まれていた時代があったと言う
わたしは、中央公論社編の文庫本「現代詩アンソロジー・下巻」を読まなかったので、1960年代以降に書かれた詩がどのような詩だったのか、解らなかった。ある日、知り合いの65歳くらいの元コピー・ライターの男性から「1960年代の末頃に「詩」が盛んに読まれた時代があったのだけれども「詩」って、今どうなっているの?」と尋ねられた事があった。その男性の話によると「その当時盛んだった学生運動とリンクして、映画や演劇や文学書や思想書や漫画が観られたり、読まれていたりしていた。」という事だった。
そこでは「鈴木志郎康」氏の詩も盛んに読まれていたし、わたしが現代詩講座を受講した後に知る事となった「吉増剛造」氏や「天沢退二郎」氏や「清水昶」氏らの詩作品も数多くの読者に支えられていたという。また詩人・思想家「吉本隆明」氏の著作物や、短歌・現代詩等の詩歌、「天井棧敷」での演劇、前衛的な映画等多方面で活躍した「寺山修司」氏の活動もとても大きく支持されていたそうだ。わたしは、先述の、65歳くらいの元コピー・ライターの男性に、自分が出版した詩集を贈ってみたのだけれども、彼から見ると「今は、もう「現代詩」という分野の文学は、殆ど存在していないのではないか。」という見解になるのだった。
それは「現代詩」というものが、1980年代半ば以降から、しばしば語られていたように「現代詩を読む人たちよりも、現代詩を書く人たちの方が多い。」という状況を指し示しているのではないか、という事にも解釈できた。その一方で、わたしは「「詩を書いてみましょう。詩を書くと、毎日の生活が活き活きしたものになります。」という、わたしが「現代詩講座」を受講する事になった、現代詩の在り方は「基本的な事」であり、それで、充分なのではないか。」とも強く考えた。あくまでも「詩というものは、1個人の、何らかの生活上の出来事から発生する気持ち=素朴な表現意欲を出発点として、詩という言葉にしていけば良いのであって、それが、何かしらの「詩壇的現象化・社会的現象化」をしていく必要等は、ないだろう。」と、彼と話していて、わたしは考えたのだった。
7 「詩人」を名乗る事と現代詩の「賞」について
ここで「詩人」を名乗るという事について考えてみる。まず「詩人を名乗るという事」は「詩集」を出版している人たちを指しているという事なのか?
わたしは、そのようには思わない。詩集を発行する事は、自費出版による事が殆どなので、ある程度経済的に余裕がないと、それは実現しない。「詩人」は、出費ばかりが、かさむので、職業にはならない。わたしは独身生活を続けてきたので詩集の出版が可能となったが、家庭を持っていて子どもがいる人たちにとっては、詩集を出版するための費用を捻出する事はかなり難しい事であり「詩を書き続けてきてはいるけれど、一生に1度くらいは、自分の詩集を出版してみたい、と願っている人たちは数多くいるだろう。」とわたしは想像した。詩を書き続けていて「わたしは「詩人」だ。」と名乗れば、その人は、もう詩人なのだとわたしは思う。また「詩人」は「詩を書く才能」がある人がなるのだろうか?「詩を書く才能」とは、何なのか?「詩」を書くには、ある程度、持って生まれた資質というものもあるのかもしれないとも思うが、文章を書くのが、巧いという事とは、まったく違うと思う。形が「いびつ」でも構わないとわたしは思うし、やはり「詩をどうしても書いてみたい、という動機こそが「詩を書く才能」へと向かって、繋がっていくのではないか。」とわたしは思うのだ。そこには「生活の中の切実さを乗り越えていきたい」という事もあれば「生活の在りかたをもっともっと豊かなものにしていきたい」等、さまざまな事があるだろうが、そこには「詩」を書いていく、強い意志と粘りが必要とされる。但し、何の意識も持たずに、言葉を改行して、それを「詩」としてしまうのは「安直である。」とわたしは思う。言葉を改行する事には、言葉を改行するための積極的な意識が必要なのであり、そこを外してしまうと「詩」にはならないと思う。
ところでわたしは、何冊かの詩集を出版してきた。その行為の中でわたしが考えていた事は「やはり、何らかの「詩の賞」を受賞して、詩人として「それなりの、自分のポジション」を獲得していきたい。」という、言わば、1つの野心ではあった。そこで「詩人」が得るものは「ステイタス」というもので、それは「詩人たちの「詩壇」で認められたい。」という欲望を満たす。わたしは、「詩の賞」を「あらかじめ、受賞者が決まっているのかもしれない。」というような疑問を持っている事を書いたが、それは、すべての「詩の賞」に当てはまる事ではないかもしれない。ただ、選考委員会は、ベテラン詩人と中堅詩人で構成されており、中堅詩人は賞の候補になった詩集を丹念に読み込んではくるが「やはりベテラン詩人の意向が強く反映されていくのだろうなあ。」という思いは、個人的には拭い切れない。詩人の名が冠された「詩の賞」等は、概ね、詩人の出身地域の文化振興とも大きく関わっていると思うので「純粋に「詩という文学」について与えられるものでもない。」とも想像する。
そのような事もあって、わたしは、わたしの詩壇での評価は、どうでもよくなってしまった。
上昇志向=有名詩人になる、という考えを持つ事は、別に非難されるような事ではなく、そのような志向に向かって努力をしている詩人たちを非難するわけではないけれども、あくまで、わたしは、そのような考えを持つに至って「自分の好きなように、詩を書ければ、それでもう充分である。」というふうに感じたのである。その時期、わたしは、わたしの持病である、精神疾患が悪化していってしまったので「詩壇」で、多くの詩人たちと交流する事から遠ざかってしまったし、また住所も非公開にしてしまったので、詩人たちから詩集や同人誌が送られてくる事も激減してしまったのだった。そしてわたしは「もう、それで良い。自分の好きなように詩を書いていければ良い。そして、身近な詩友たちとの間で熱心に詩について考えを交わし合えれば、それで充分なのではないのか。」という考え方を持つに至ったのだった。
そうしてわたしは、その後、詩人「さとう三千魚」氏の主催するネット詩誌「浜風文庫」に詩を掲載させてもらう事になったのだった──
8 わたしから見た現代詩に見られる書法の特徴についてと詩が発表される「媒体」について
現代詩の書かれ方=書法には、代表的なものが、複数存在すると、わたしは考えている。まず、それらを列挙していってみようと思う。
「「現代詩」は、難解である。」と、しばしば指摘される。けれど、必ずしもそうとは言えないので、現代詩の在り方をひと括りにして、考える事はできない。そういう事を踏まえて、わたしは、わたしなりに、「現代詩」の書かれ方について、整理してみた。
① 作者と詩の中の話者が一致しているか、限りなく距離が近い詩。
※ 生活の場面に即したり、身近な風景に即したりしながら、素直に書かれている詩ではあるが、作者と詩の中の話者が一致しているか、限りなく距離が近いため、詩の作者の経験の範囲に基づく詩となり、詩の中の話者が動き回れる範囲は狹くなる詩。
② 主に「直喩」から造形化されていて、その中に「人の姿」が見える詩。
※ ①の詩に近いが「〜のような」という「直喩」の修辞が多用される詩。詩で表現される言葉の世界が、①の詩よりも、大きく拡げられる詩。
③ 主に「暗喩」から造形化されているが、その中に「人の姿」が見える詩。
※ 「直喩」を使わずに事物そのものを「暗喩」として例えるが、その技法の奥に「作者」または、詩の中の「話者」の姿が見える詩。造形化されていても、その中に「人の姿」は見える詩。
④ 主に「暗喩」から造形化されているが、その中に「人の姿」があまり見えない詩。
※ あくまで「暗喩」から造形化されている詩。形式を重んじて、作者の意識を投影しようとする意識はあるのかもしれないが、それが、充分にあるいは殆ど投影されずに、詩が形骸化されてしまう危うさを持っている詩。現在「現代詩手帖」に掲載されている詩作品は、このタイプのものが多いように、わたしは感じている。何故、そういう事になってしまうのだろうか?③のタイプの構造の詩が「模倣されて、模倣されていき、」その結果、書き手の手つきばかりが残ってしまい、そういう事になっていってしまうような気がしてならなかった。
➄ 作者と作品中の話者が分離していて、詩の中の話者が作者の想像力によって、自在に動き回れる詩。
※ 作者は作者として在り、話者は話者として在り、作者と分離した形で書かれる詩。書き手の生活体験、生活範囲は限られているわけだが、詩の書き手の想像力を駆使すれば、詩の中の話者は自由に動き回る事が出来る詩。
わたしは、今は、⑤の方法で詩を書いている。何故なら、わたしの生活と共に、詩作に於いても、「さらに「自由」になっていきたい。」と願っているからだ。そうする事によって「書いていて楽しくなれるし、おそらく読んでくれる人たちも楽しい気持ちになれるのではないか。」と思うからだ。
わたしは、ある日、詩人「辻和人」氏が、ツイッター上でこのようなツイートをしているのを見つけた。それは、このような1文だった。「「現代詩」ではなく「現代の詩」ではないか。」わたしは、ツイッターはツイートが流れる速度が早過ぎて疲れるため、滅多に見ないのだが、わたしは、このツイートは「とても重要な事を、言い表しているのではないか。」と思ったのだった。
詩の書かれ方、①②では、もちろん書き手の姿が充分に見えるけれども、詩としては素朴過ぎる事を免れない。けれど、人の生活を端的に切り取るという面では充分に有効だ。③では「現代詩手帖」に多く見られる書法であり、言葉によるオブジェのようなものではあるが、その向こうに「人の姿」は見える。④では、これも「現代詩手帖」に多く見られる書法で、言葉の形はあるものの、その向こうに「人の姿」はあまりよく見えない。この書法では、書き手の意識が詩に投影される力が薄い、もしくは存在していないかのように見えるので、詩が形骸化して、読者を詩を楽しむ事から遠ざけてしまう危険を孕む。③④のような詩の書かれ方が、現在、最も多いのではないか。その理由は「詩としての姿形=言葉の配置のフォルムが「スタイリッシュ」だから、好まれるのではないか。」と、わたしは想像する。さまざまな詩集や同人誌では、詩の書かれ方は、まちまちかもしれないが「現代詩手帖」では、しばしば、そのような詩が掲載されているように、わたしには感じられる。
最近、しばしば「ネット詩」という言葉が使われる事がある。往々にして「ネット詩」というものは「紙媒体」で書かれた詩とは異なり「扱いが便利なインターネット上に書かれた、何処か薄っぺらい詩」のような解釈も多くされているようだが、わたしは「決してそうではない。」と思う。「「紙媒体」で発表された詩も、「インターネット上」で発表された詩も、同様に「詩」なのであり、「詩」が存在している、その在り方が、かなり大きく異なっているのではないか。」とわたしは考える。また、詩の書かれ方が、それまでの「縦書き」から「横書き」になるため、あくまで頑なに「縦書き」にこだわる書き手からは、敬遠されるのではないか?では、「紙媒体の詩」「ネット媒体の詩」それぞれの媒体で書かれる「詩」の在り方とは、何か?
「紙媒体」の詩は、主に「見開き単位」で考えられている事が多く、また「本のツカ」が厚くなり過ぎてしまうため、ある程度、1篇毎の詩の行数が意識されなければならないという面がある。そして何よりも、詩集や、わたしがかつて所属していた同人誌「卵座」に見られるような書物の発送先が、「詩人」や、詩の「同人誌」や、詩の「出版社」等に限られてきてしまうため、詩に関わる媒体の中での循環となり、それぞれの詩集や同人誌間での「感想」のやりとり」となってしまう事が多い。「鈴木志郎康氏」は「詩は、感想を言い合うのは良いけれども、批評をしあうのは良くない。」という事を言っていた。それは何故なのかと言えば「「紙媒体」同士でのやりとりでは、書き手同士が対面して、リアル・タイムで話を交わす事がなかなか出来ないし、発送等の関係で、詩を読み合うまでの間に「時間差」が生じてしまうから、詩人同士の「「コミュニケーション」に「制約」が出てきてしまう。」という事ではないだろうか?
また「現代詩手帖」には「詩誌月評」「詩集月評」というものがあり、ここでは、選者の嗜好による「選ぶ、選ばれる」という関係性での批評がなされ、取り上げられた「詩誌」や「詩人」は、その事で一喜一憂するような傾向が見られる。
現在は、既に、SNSの時代である。わたしは今、SNSの中でも「Facebookが「現代詩ではなく現代の詩」を発信する事に於いて、最も適しているのではないか」と思っている。Facebookは、参加者が、ウェブ・サイト上で、名前や顔(存在)を示し交流しあっていく、という性質を持つものである。
わたしは今、Facebook上にある、詩人「さとう三千魚」氏が主宰するウェブ詩誌「浜風文庫」の場を借りて、詩を発表させてもらっている。そこでの詩の在り方は、「ネット上の空間に詩が固定されている。」というよりも「ネット上の空間に詩が浮遊している。」という感じだ。ここで、わたしが「良い事だな。」と思う事は、詩人「さとう三千魚」氏の手腕によるところが、とても大きいのだが、ウェブ・サイトへのアクセス数が大変に多くなってきているそうで、それは、自分の書いた詩を、普段、詩を読み書きしない人たちを含めたところまで、読んでもらえる可能性を多く含んでいるという事である。また、何処からか訪れる詩人の投稿詩が多くなってきているそうで、その事も「ネット詩」の可能性を大きく示唆していると言えるのではないか。また、発表された詩がアーカイブされる仕組みを持つ事も出来る、という特長もある。
ここでは「紙媒体」で書かれる詩と「ネット媒体」で書かれる詩の、どちらが上、どちらが下、等という比較をするつもりは、さらさらないが、時代の潮流としては、良くも悪くも情報の伝達方法はインターネットが主流となってきている。インターネット上の情報は、誤りも多く持っているかもしれないが、昨今の新聞やテレビ等の媒体が、かなりイデオロギーに支配されている事を考えると、その有効性は図りしれないところがある。
わたしは、持病を持っているので、基本的には「ベッドの中」で、詩を書いている。スマホのメモ帳アプリで詩を書いていき、それをメールでパソコンに送って、ワープロで清書、推敲というプロセスを経て、詩を仕上げていく。わたしは、パソコンの前に座っていられる時間が体の関係で30分くらいに限られているので、その方法は、わたしにとってありがたいものだ。「わたしには、出来ない事がいろいろとあるけれども、ああ、こうやって、詩を書いていけるんだな。」という喜びがある。
Facebookには、「コメント欄」という決定的な特長があり、詩を読み合った「感想」のみならず「批評」もリアル・タイムで書き込み合う事が出来る。但し、それが実現されるためには、「詩のサイト」の参加者が、積極的に、そのような意識を持ち合う事が必要になってくる。「黙っていては、何も進展しない。」のだ。「詩のサイト」の参加者が、参加者同士での単純なコミュニケーションに留まってしまうと、結局「紙媒体」の同人誌内で行われる「合評会」と同じ事になってしまう。ネット詩誌「浜風文庫」では、参加者が知らないところで詩が読まれている可能性が大いにある。「現代詩手帖」に詩を掲載している詩人たちが「浜風文庫」を閲覧してくれている事も増えてきているような傾向も見られ、時には、コメント欄に書込みをしてくれる事もある。また、わたしは、Facebookフレンドをどんどん増やしていけば良いと思う。最初は、躊躇があるかもしれないが、「シェア機能」を活用して、FacebookフレンドからFacebookフレンドへと「詩の読者」を増やしていく事が出来るし、実際、わたしの書いた詩をめぐって、FacebookフレンドとそのFacebookフレンドが感想を言い合ってくれたり、意見を交わし合ってくれたり・・・というような、嬉しい出来事も起きたりしている。
「コメント欄」を大いに活用して「「浜風文庫」のレギュラーメンバーのみならず、投稿者やまわりで閲覧してくれている多くの詩人たちが、幅広く、詩をめぐっての「対話活動」を盛んに行なっていければ良い。」とわたしは思う。
そのようにしていけば、あくまで現在に於ける可能性だけれども、作者の手を離れた詩について、参加者、読者同士の間で、その詩について語り合える喜びが次々に生まれていくようになっていくのではないか。
「現代詩手帖」では、ベテラン詩人による「鼎談」がしばしば行われているが、ベテラン詩人以外の詩人による「詩」についての考え方の声=議論が、あまり見受けられないような気がする。この事は、残念な事だと、わたしは思っている。また、投稿作品に対しても、ベテラン詩人が2名いて、感想や意見を語っていき、最終的には「現代詩手帖賞」が選ばれる仕組みとなっており、主に「現代詩手帖」の熱心な若い読者たちが、それを目指して、詩を投稿していく形となっている。そこには、ベテラン詩人と詩の投稿者との対話は成り立っていないように思うし、投稿作品の多くが、ベテラン詩人の作風の模倣になっているような感じもあり「詩誌内での詩の執筆者と執筆者、詩誌内での詩の読者と読者との「対話」も、生じにくいのではないのではないか。」とわたしは思う。
ここで「わたしは、現代詩手帖」の在り方の、批判をしているわけではない。「紙媒体」で書かれる事への「限界性」について、書いている。
ところで「「現代詩」ではなく「現代の詩」ではないか。」という指摘は「さまざまな、詩をめぐる境界を打ち破れる可能性を持っているのではないか。」とわたしは思っている。それは「詩」に於ける「平和的融和」について、広く考えていけるという事だ。
「「現代詩」という呼称は、「思潮社」が発明したものである。」とわたしは思う。この呼称は、今後も、長く用いられていく事であろう。しかし、「「現代詩」ではなくて「現代の詩」」という風に、解釈を拡大すれば、今書かれている「「現代詩」と「現代の詩」との垣根は、取り払われて、もっと自由に行き来する事が出来るようになっていくのではないだろうか?」と、わたしは、そのような事を願っているのだが、どうであろうか?「現代詩手帖」と「詩と思想」という「紙媒体」の雑誌同士での交流は、生まれ始めているようだ。理想論かもしれないのだが、そこに「ネット詩誌」も加わって、より広い「詩人同士の交流」「詩同士の交流」が生まれていくというのはどうであろうか?少なくとも、わたしが「紙媒体」の編集者だったなら、そういう事を提案してみると思う。何故なら、その方が、お互いにしあわせな「言葉の交流」を図れる事になると考えるからだ。
9 最後に
数年が経てば、今まで長く活躍してきたベテラン詩人たちが次々と逝ってしまう事になるのだろう・・・それは「とても寂しい事だ。」とわたしは思う。しかし、寂しい事ではあるけれども、わたしたちの世代、また次の世代・・・というように「進んでいかなければならない。」と思う。
わたしは、30年以上、詩を書いてきたが、還暦近くになっても「詩論は、書いてこなかったな。」と思う。その事に関しては「わたしは、もしかして、怠惰だったのかもしれない。」という思いもよぎる。けれども、その理由は、はっきりとは解らない。だから「これからでも、きっと間に合う。」というつもりで、わたしは、詩にも詩論にも、向かい合っていこうと思うのだ。
それを引き受けて「詩は、「現代詩」ではなくて「現代の詩」」としての拡大解釈が有効になっていくのではないか。」とわたしは思っている。